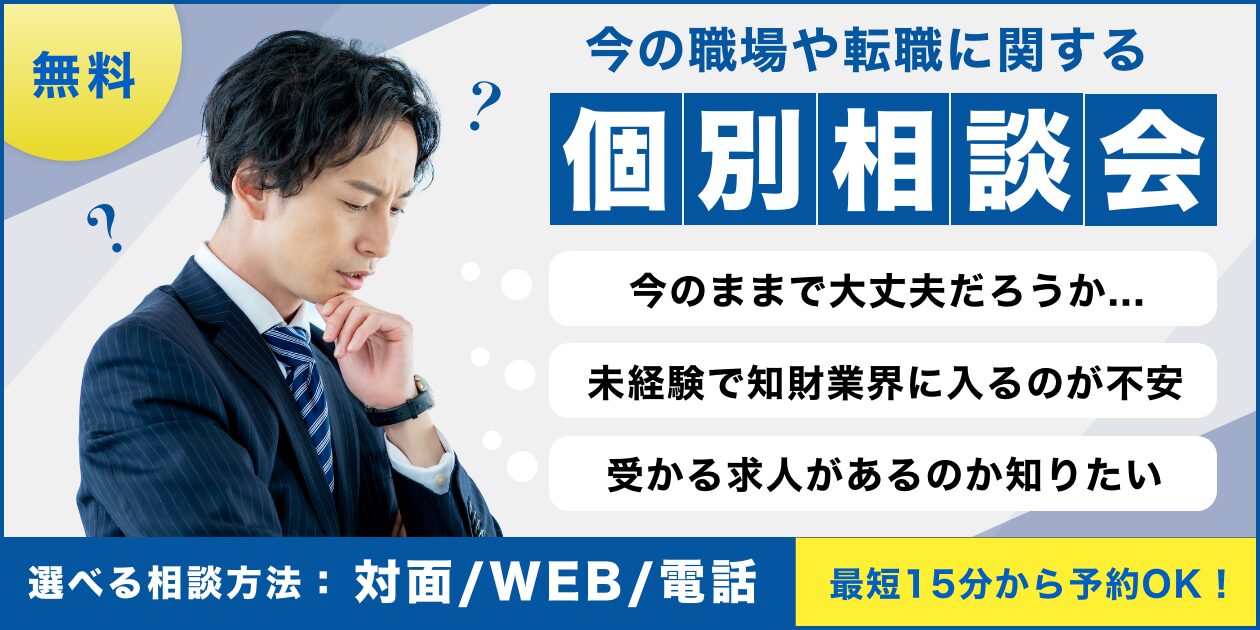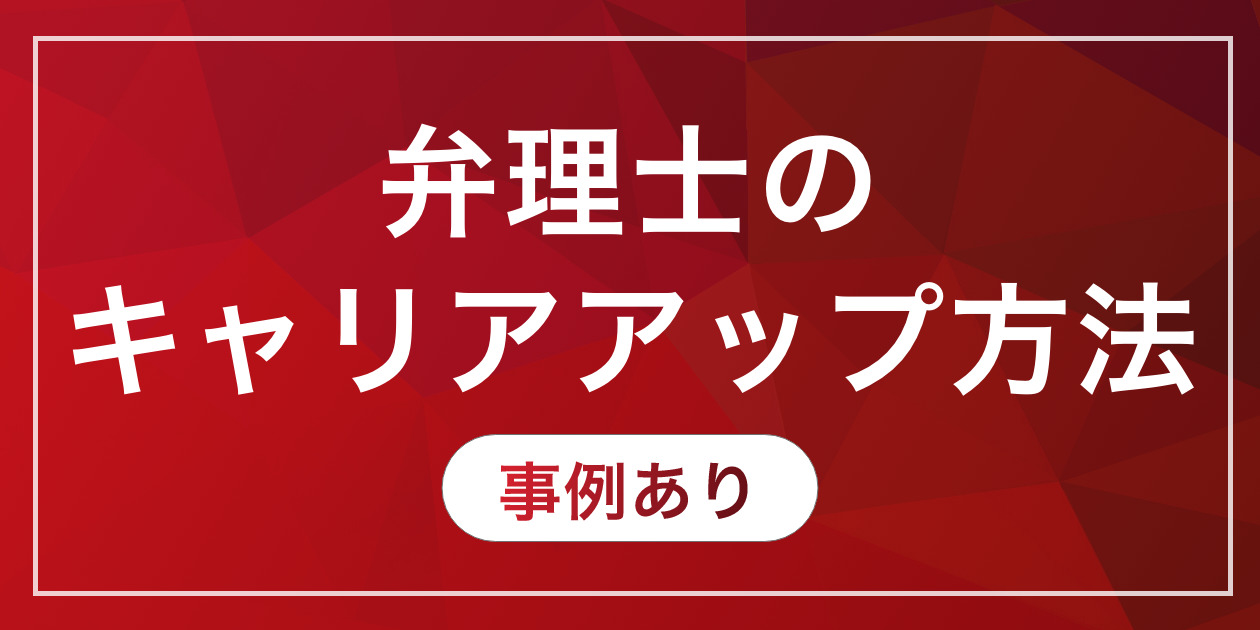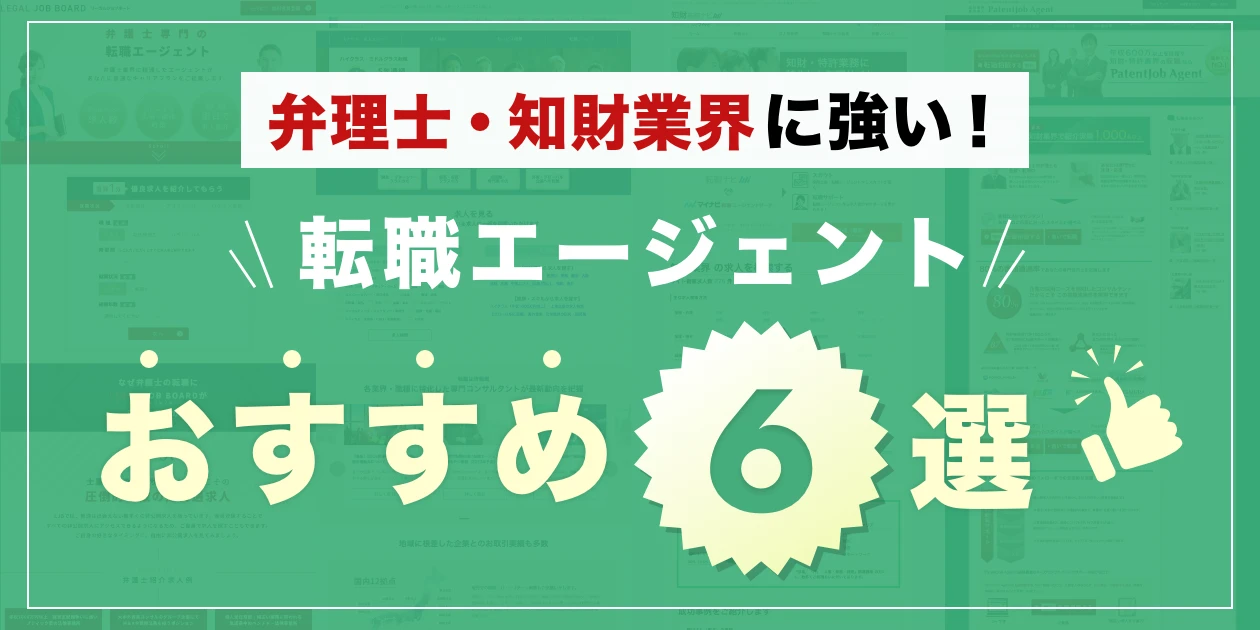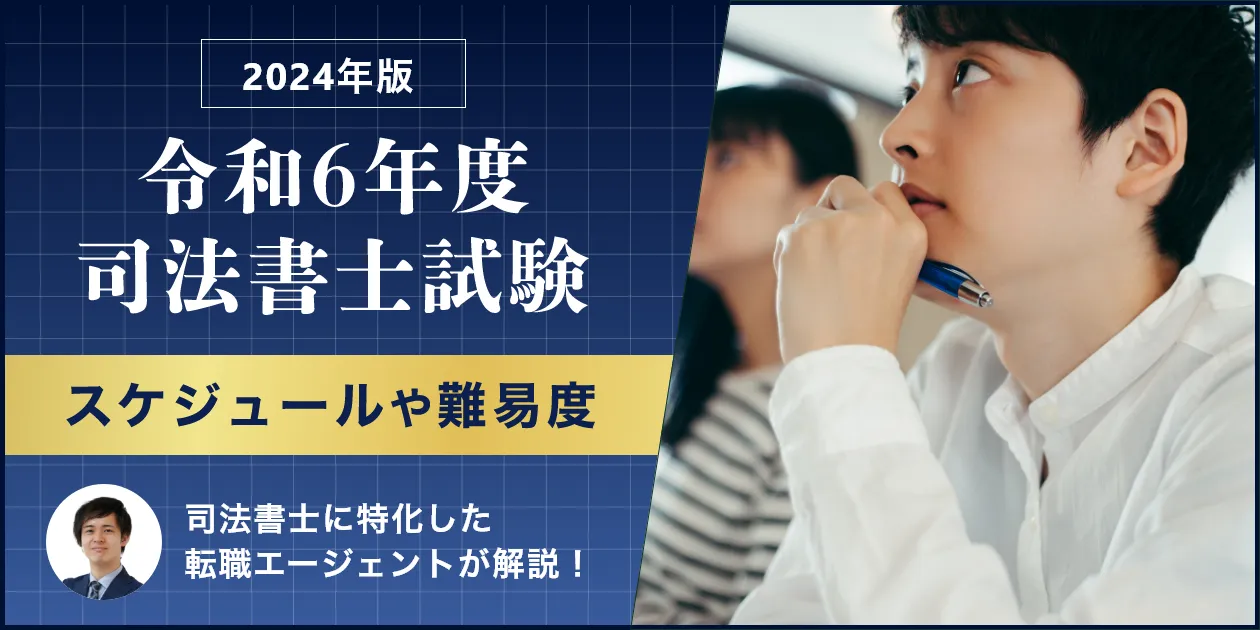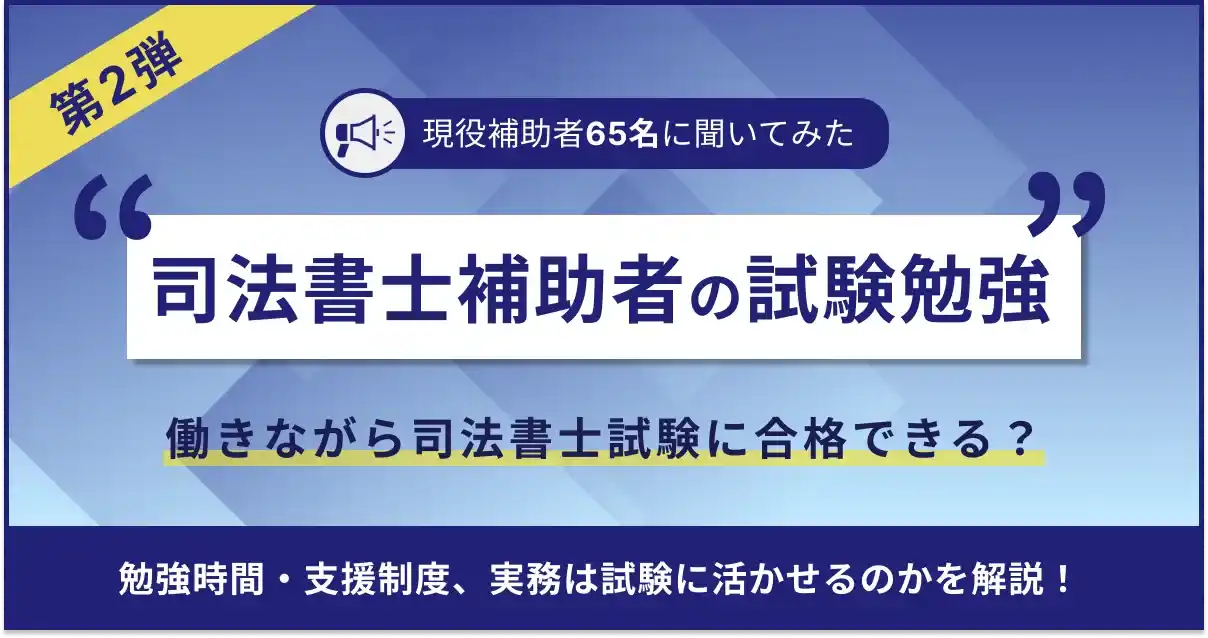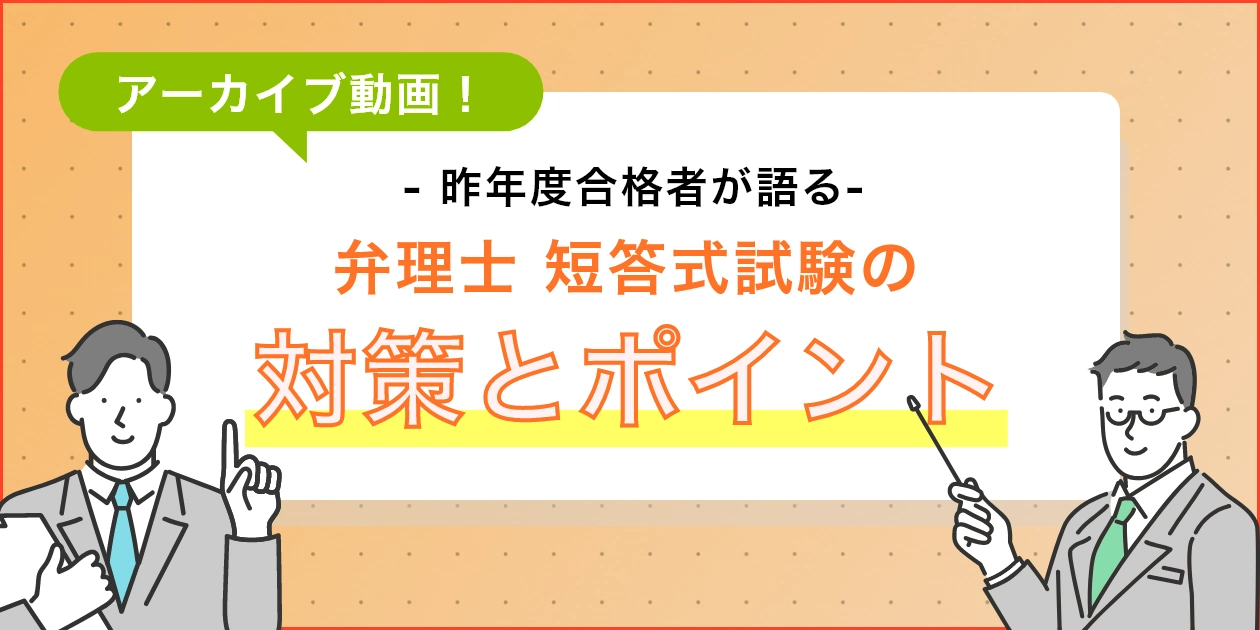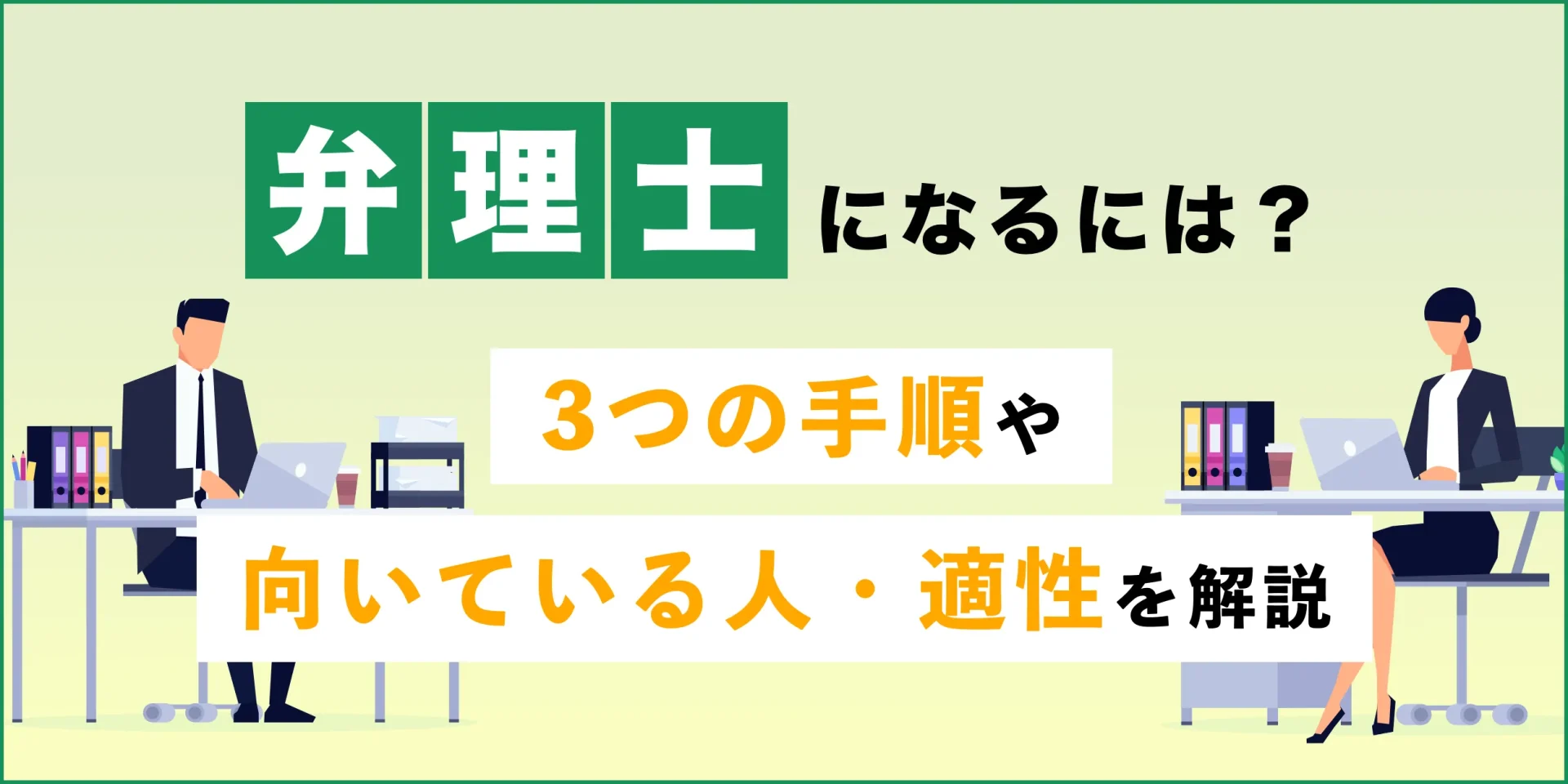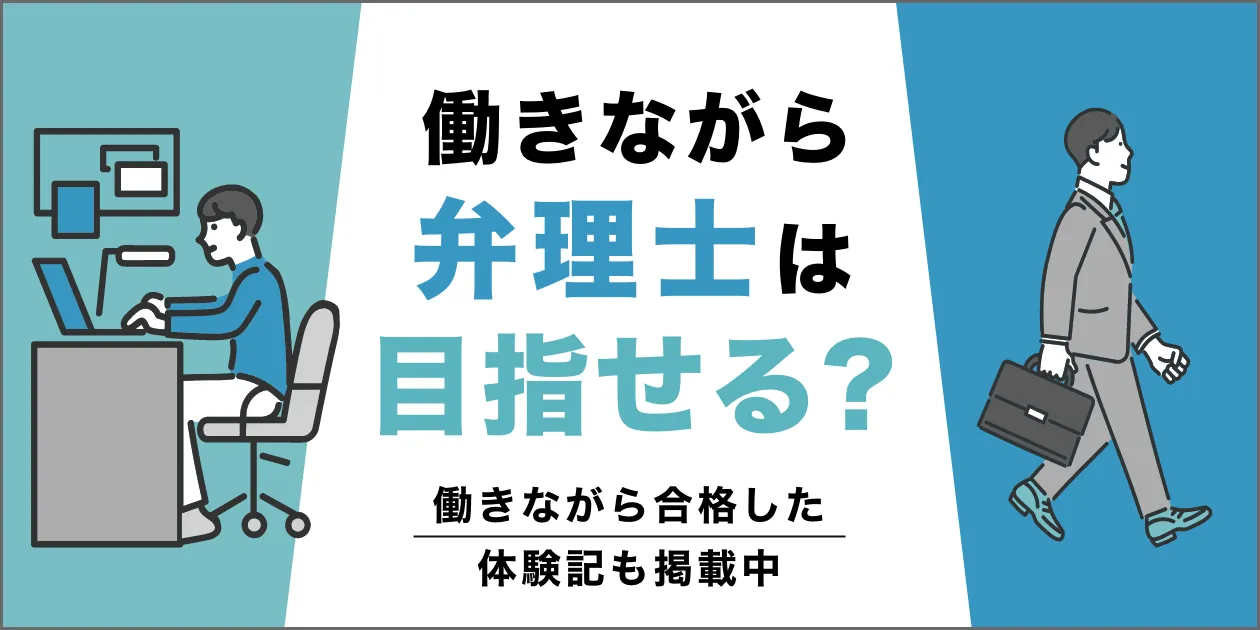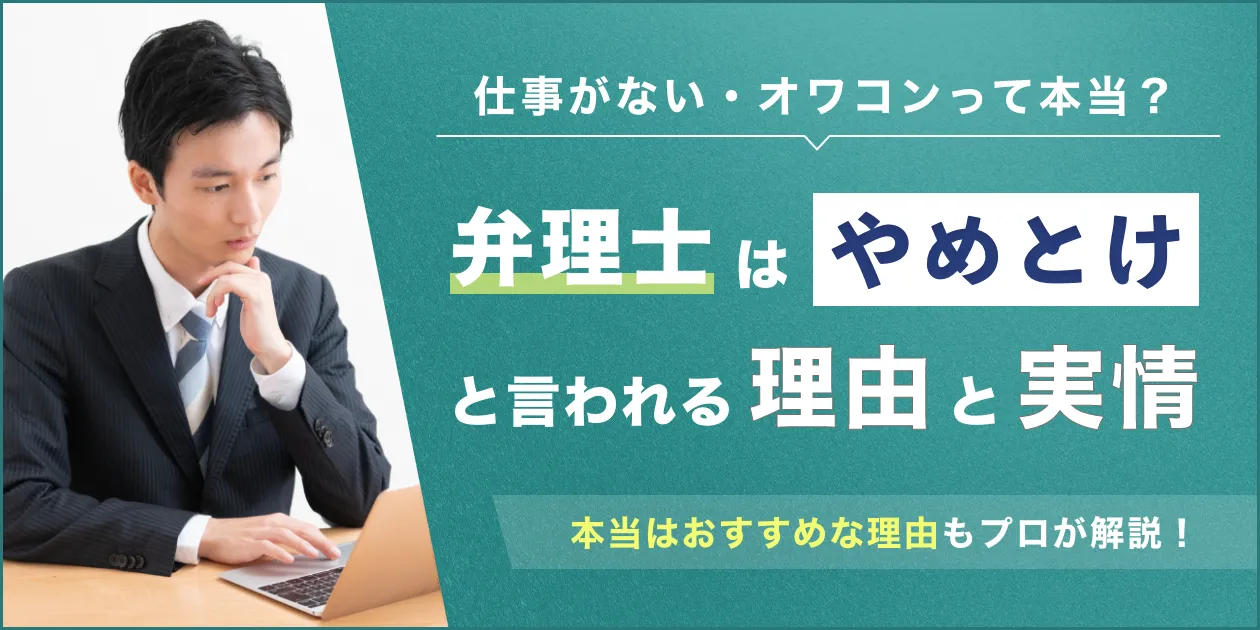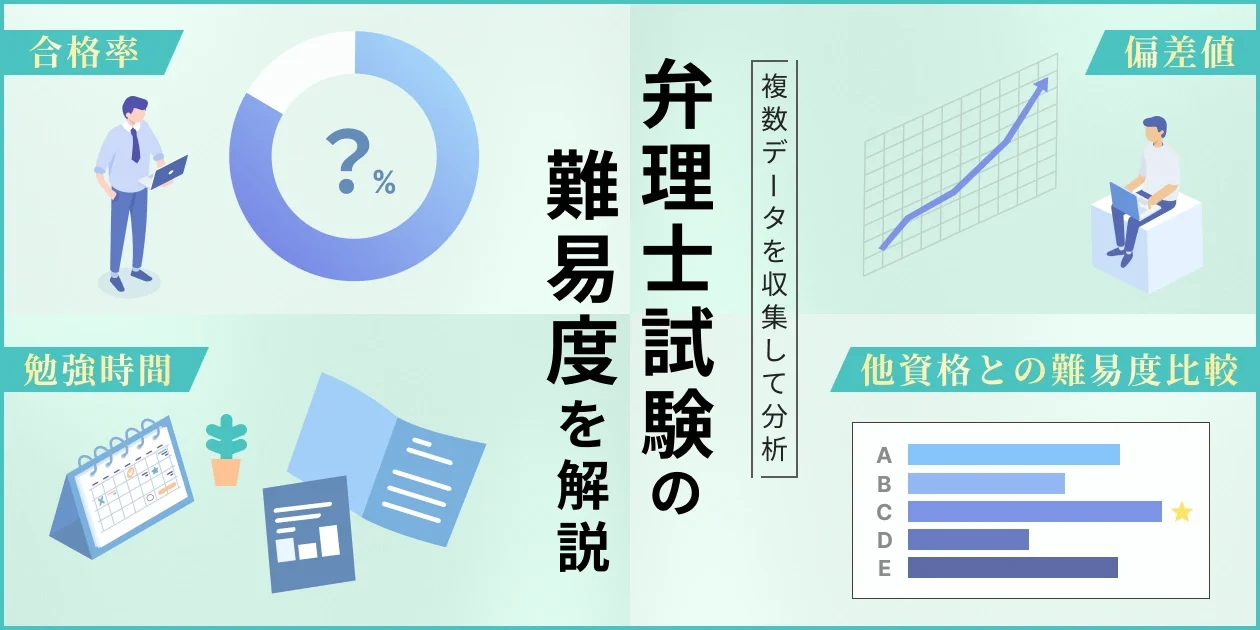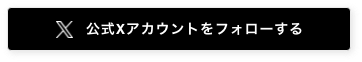付記弁理士とは?なり方やメリット・業務内容を解説|訴訟案件が豊富な求人もご紹介

by LEGAL JOB BOARD 三島善太
転職エージェント
- 担当職種:

こんにちは。弁理士と特許技術者の転職エージェント「リーガルジョブボード」の三島です。
本記事では、「付記弁理士になる方法や、付記弁理士を目指すメリット」などを解説します。付記弁理士に関する情報を網羅的に把握することができる内容となっています。
「訴訟案件が豊富な特許事務所や法律事務所」への転職をご検討されている方は、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。
▼個別相談を受付中です
付記弁理士とは?
付記弁理士とは、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるための権利を持った弁理士のことです。
付記弁理士は、特定侵害訴訟(特許、実用新案、意匠、商標もしくは回路配置に関する権利の侵害または特定不正競争による営業上の利益の侵害にかかわる訴訟)において、訴訟代理人を務めることができる弁理士です(※)。
付記弁理士となるためには、研修を受けた後、特定侵害訴訟代理業務試験(付記試験)に合格し、日本弁理士会に申請を行わなくてはなりません。
この申請が認められると、日本弁理士会の登録名簿に、前述の試験に合格した旨が「付記」されることから、特定侵害訴訟において訴訟代理人を務められる弁理士は付記弁理士といわれています。
※弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その事件の訴訟代理人となることが可能であり、弁理士の出廷についても、共同受任している弁護士との共同出廷が原則となります。
付記弁理士はどのくらいいる?
日本弁理士会が公表している「2021年登録・抹消・付記」のデータによると、弁理士のうち特定侵害訴訟代理業務の付記を受けているのは3,430名で、全11,700名の弁理士のうち約29%です(2021年10月20日時点)。
ちなみに司法書士にも、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた「認定司法書士」がいますが、2021年4月1日時点で司法書士のうち78%が認定司法書士となっています(出典:日本司法書士連合会「会員数他データ集」)。
諸条件が異なることもあり一概には言えませんが、認定司法書士に比べると、付記弁理士の割合は少ないように感じられるかもしれません。
「付記弁理士を目指すべきか迷っている」「訴訟案件が経験できる事務所を知りたい」といった方は、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。
付記弁理士になる方法
付記弁理士になるためには、まず弁理士であることが大前提ですが、
- 民法・民事訴訟法の基本的知識の習得
- 日本弁理士会が実施する能力担保研修の受講・課程修了
- 特定侵害訴訟代理業務試験(付記試験)の受験・合格
- 日本弁理士会への付記申請
といった手順を踏む必要があります。各項目について、詳しい内容などをご紹介します。
※それぞれの詳細やスケジュールなどに関しては、日本弁理士会や特許庁から発表される情報をご確認ください。
民法・民事訴訟法の基礎知識の習得
付記弁理士になるための特定侵害訴訟代理業務試験(付記試験)は、受験資格として、能力担保研修を修了した弁理士であることが定められています。
能力担保研修を受講するために必要な条件が、「民法・民事訴訟法の基礎知識の習得」です。方法は具体的に3つあります。
- 研修所による「民法・民事訴訟法に関する基礎研修」(eラーニング)を受講
- 研修所が過去に販売した「民法・民事訴訟法に関する基礎研修」のDVDを視聴・レポート提出
- 大学、専門学校等で民法・民事訴訟法の知識を習得・レポート提出
この3つから自身に合った方法を選択し、「民法・民事訴訟法の基礎知識の習得」ができなければ、能力担保研修に進むことはできません。
能力担保研修
能力担保研修は、前述した「民法・民事訴訟法の基礎知識の習得」が認められた弁理士に受講資格が与えられています。
弁護士や裁判所判事・書記官が講師を担当し、講義は民事訴訟に関する実務的なものを中心に、弁理士が特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるために必要な学識及び実務能力に関する内容となっているほか、自宅起案やレポートなどの課題も。
定められた45時間の講義を全て受講し、自宅起案4件を期限までに提出することで「能力担保研修を修了」することができます。令和3年度の能力担保研修は、4月~8月にかけて、東京・大阪・名古屋・札幌会場で行われました。
受講料は20万円(各種テキスト、副読本代を含む)と決して安価ではないこと、研修後にさらに付記試験に合格しなくてはならないことがネックとなり、能力担保研修の受講をためらう方もいるようです。
特定侵害訴訟代理業務試験(付記試験)
「民法・民事訴訟法の基礎知識の習得」と「能力担保研修の修了」を経て、ようやく「特定侵害訴訟代理業務試験」の受験が可能になります。
試験内容は「民法、民事訴訟法その他弁理士法第2条第6項に定める特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項」で、事例問題2問が出題され、試験時間は1問あたり3時間。過去の試験で出題された問題は、特許庁が公開する「過去の試験問題」から確認できます。
試験は10月中旬から12月下旬に東京・大阪で実施され、受験手数料の7,200円を特許印紙で納付しなくてはなりません。
令和2年度は70人が志願して56人が受験、31人が合格しており、合格率は55.4%でした。その前年の令和元年には181人が志願して159人が受験、114人が合格しており、合格率は71.7%と、年によって受験者数や合格率に幅がありますが、ここ最近の傾向としては、受験者数は減少傾向にあり、合格率は50%前後を推移している模様。
弁理士試験に比べると合格率は高く感じられますが、受験者は能力担保研修を修了した弁理士であることを考慮すると、比較的難易度の高い試験であるといえるでしょう。
付記申請
特定侵害訴訟代理業務試験に合格した場合、日本弁理士会に「付記申請書(特定侵害訴訟代理業務の付記申請書)」と試験の合格証書を提出します。
この付記申請が承認されることで、日本弁理士会の弁理士登録に特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記を受けることができ、付記弁理士としての業務も可能になります。
付記申請の際には、手数料として6,800円を日本弁理士会に納付しなくてはなりません。
合わせて読みたい記事はこちら
付記弁理士を目指すメリット
付記弁理士になるためには、試験の受験資格を満たすための研修など、複数の過程が必要で時間と費用がかかりますが、付記弁理士を目指すべきなのでしょうか。
特別な仕事を行うことができる
付記弁理士は特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となる権利を付与されています。
特定侵害訴訟代理業務について、「弁護士が同一の依頼者から受任している事件」「共同受任している弁護士との共同出廷が原則」といった制限はあるものの、付記弁理士が特別な仕事を行える存在であることは確かです。
実際に特定侵害訴訟において、付記弁理士として活躍できる機会は現状そこまで多くありませんが、担当する場合は弁護士とともに仕事ができることもあり、とても貴重な経験となるでしょう。
民法・民事訴訟法の知識を身につけられる
特定侵害訴訟代理業務はなかなか経験できるものではありませんが、付記弁理士になる過程で習得した「民法・民事訴訟法の基礎知識」は弁理士業務においても役立つ可能性が高いです。
弁理士としての専門知識や経験に加え、民法・民事訴訟法の知識を持ち合わせていることで、クライアントからの訴訟の相談や、権利・利益侵害の相談などに対応することも可能になります。
そういった意味では、付記弁理士を目指すことや勉強の過程で知識を身につけることは、他の弁理士との差別化を図るための手段としても有効です。
「付記弁理士を目指すべきか迷っている」「訴訟案件が経験できる事務所を知りたい」といった方は、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。
訴訟業務を経験したい弁理士の方へ
付記弁理士を目指す・権利を取得するからには、訴訟業務を経験したいという方や、弁護士との仕事を経験したいという方もいらっしゃるかと思います。
弁理士専門の求人サイト「リーガルジョブボード」では、特定侵害訴訟代理業務を扱っている法律事務所などの求人もご紹介可能です。
- 付記弁理士として訴訟代理業務が経験できる事務所を知りたい
- 付記弁理士を目指すべきか迷っている
- 現状のスキルを整理して、さらなるキャリアアップを目指したい
といった方は、ぜひ「リーガルジョブボード」にご相談ください。
エージェントを利用するメリットとして、
- 自身に適したスケジュールで転職活動が進められる
- 希望に沿った求人の紹介、書類添削、面接対策などが受けられる
- 複数の選考を並行しながら、効率よく進められる
- 業界知識や裏事情を把握しながら就職活動ができる
などがあります。ぜひご活用ください。
エージェント利用のメリット