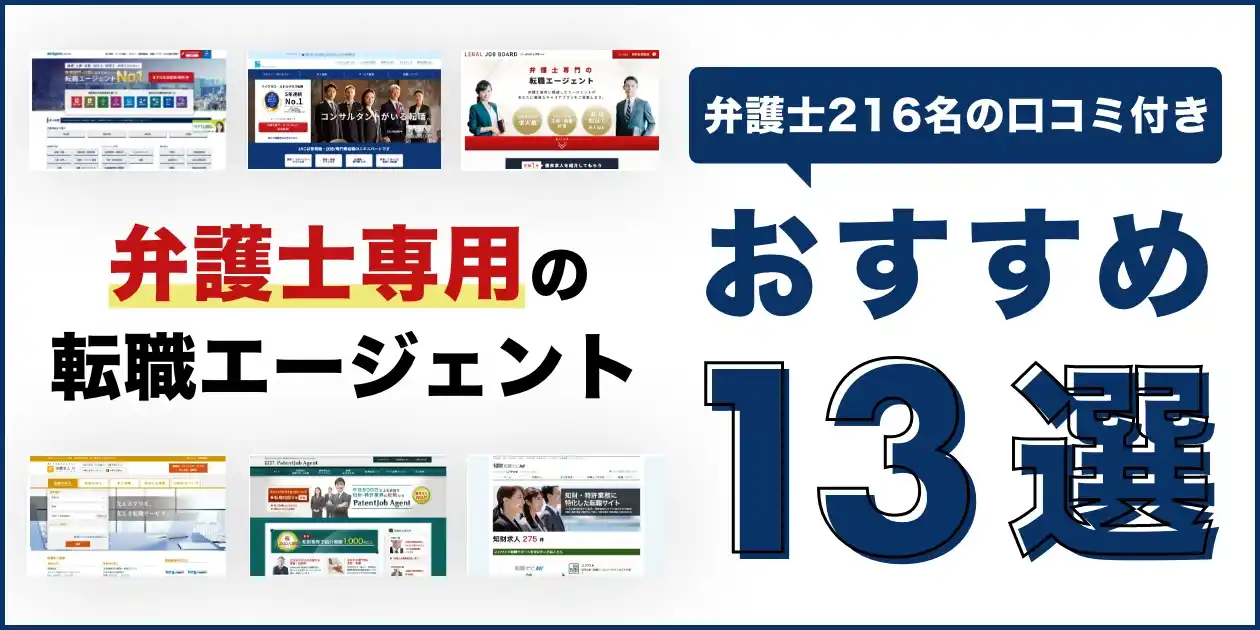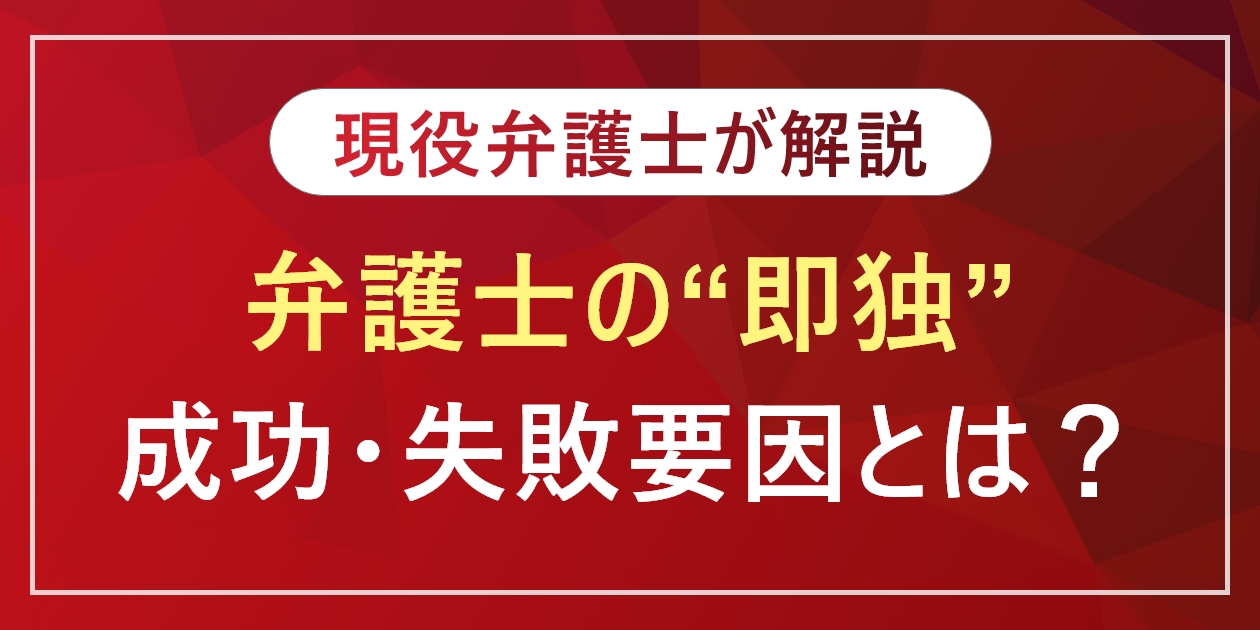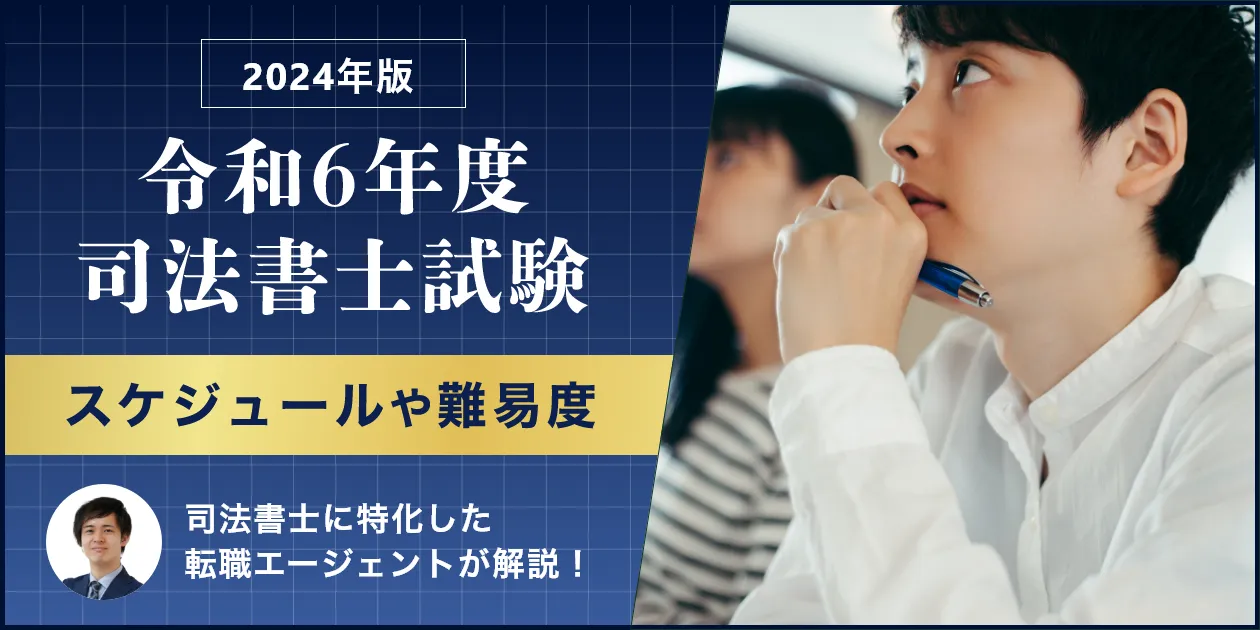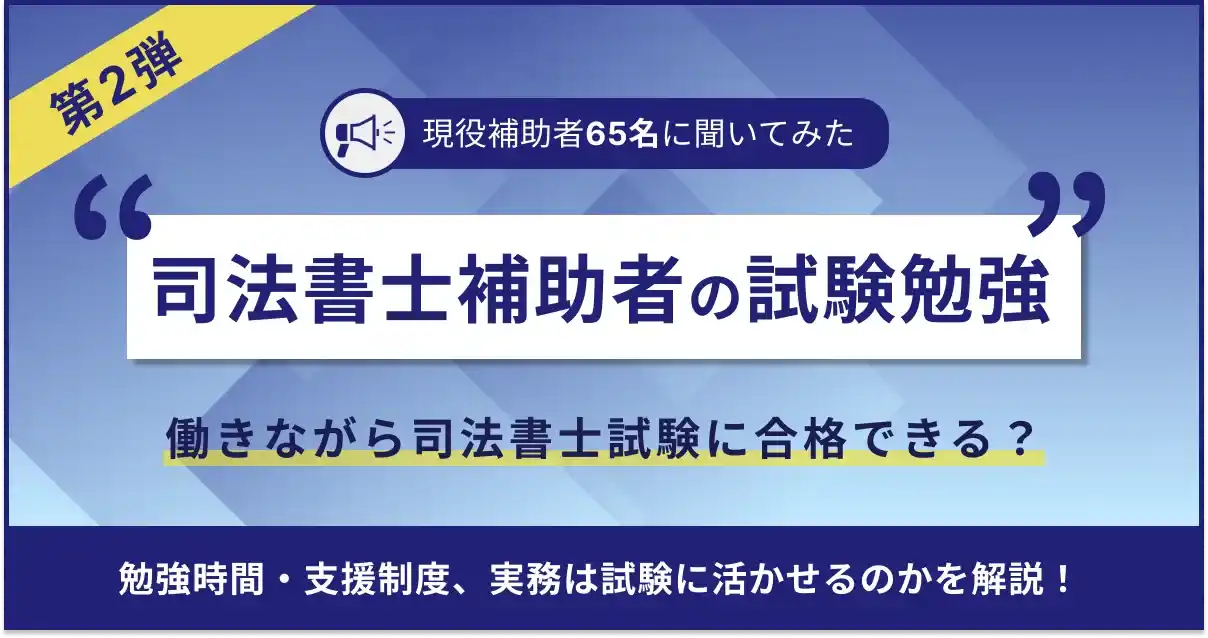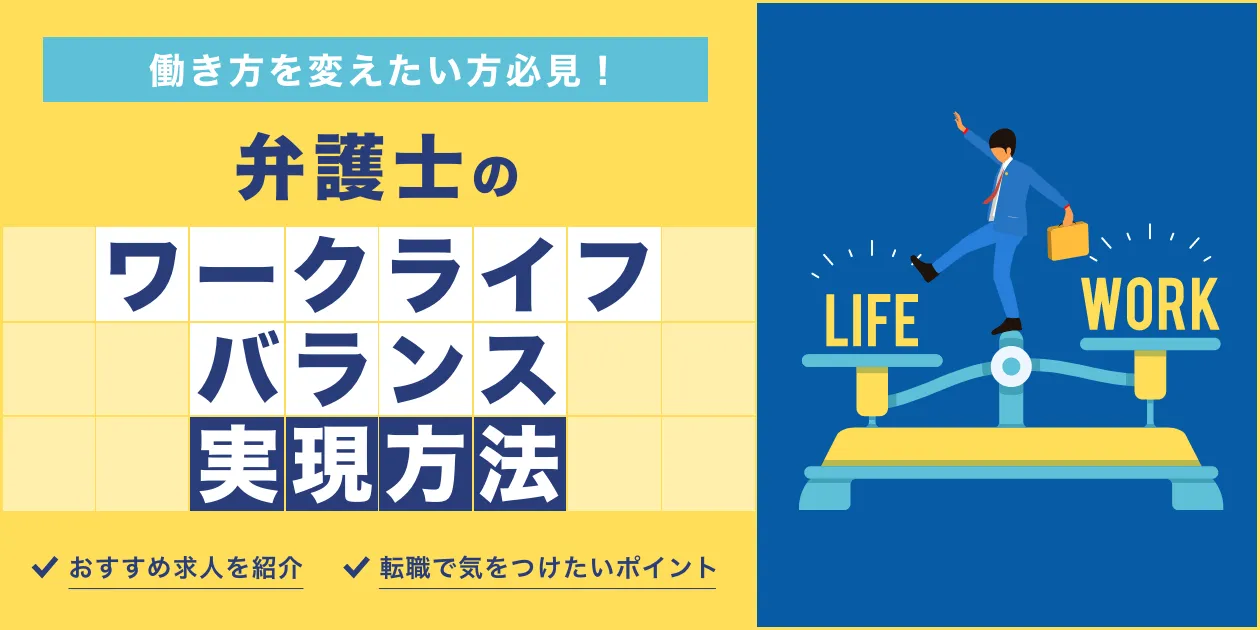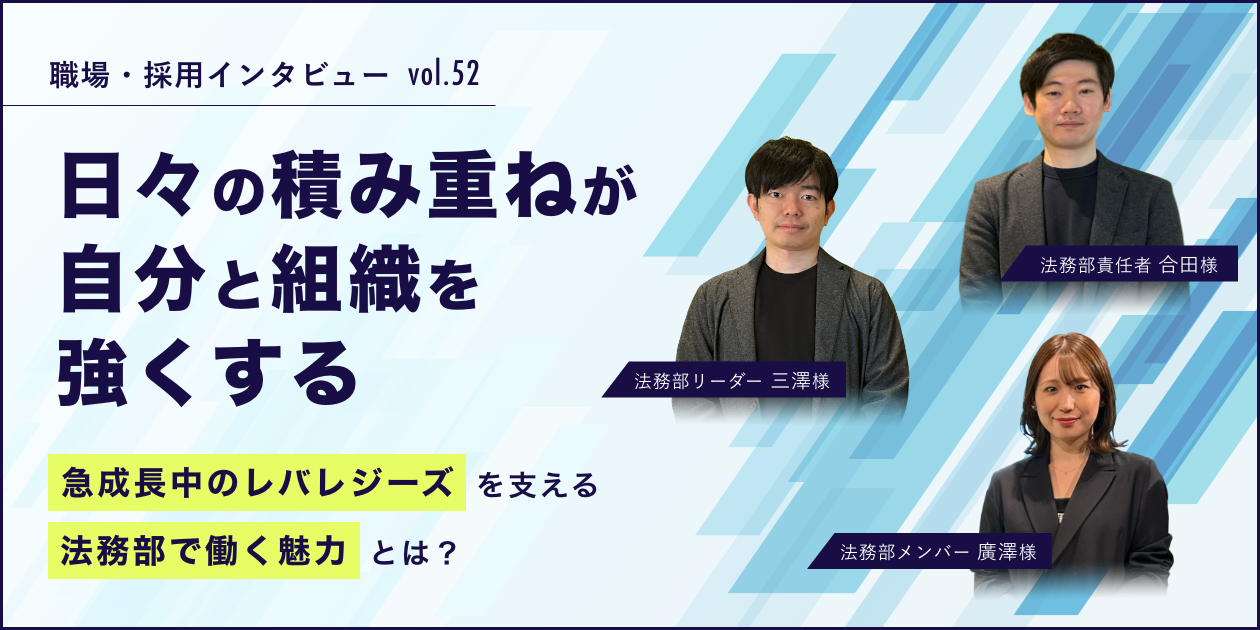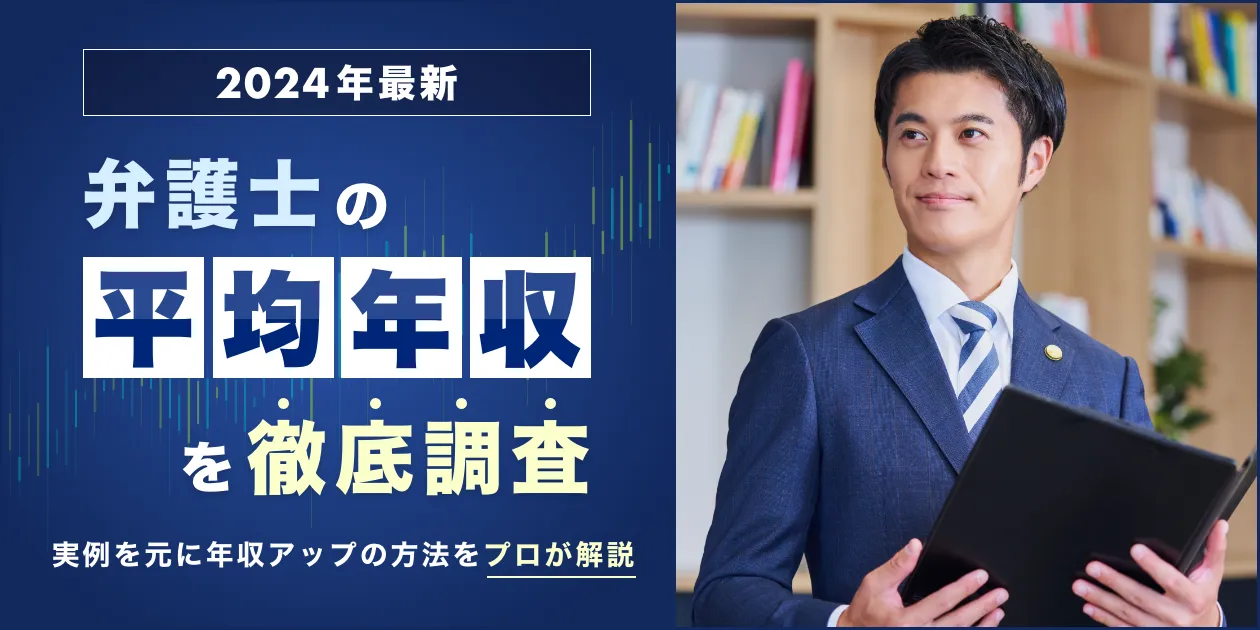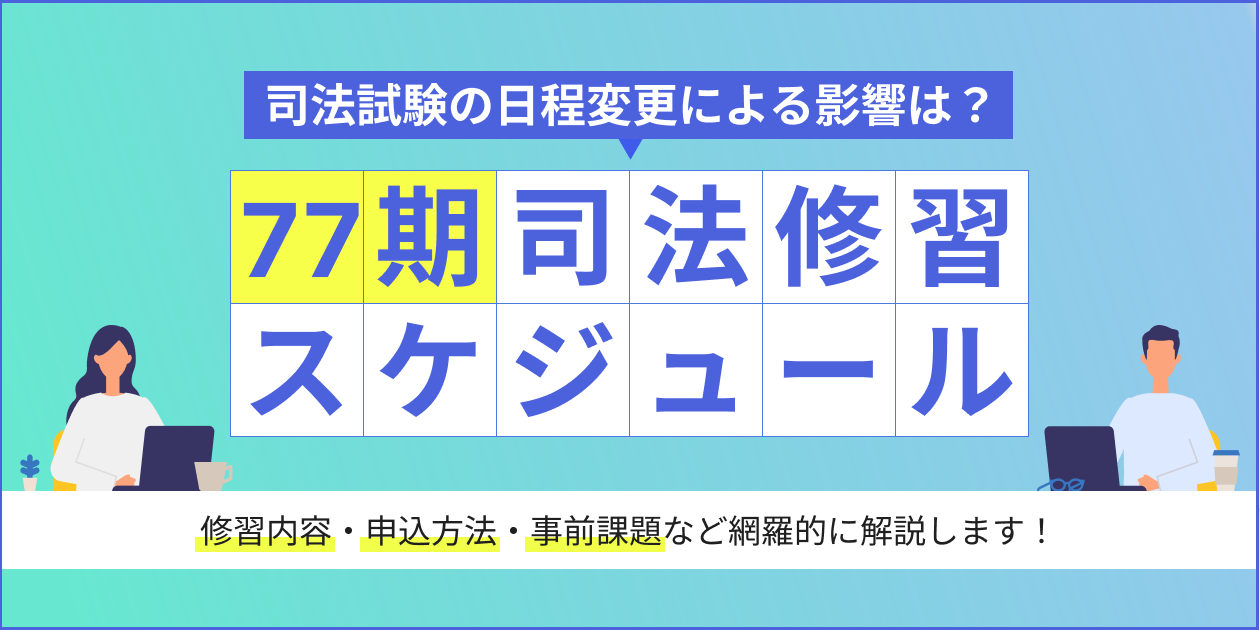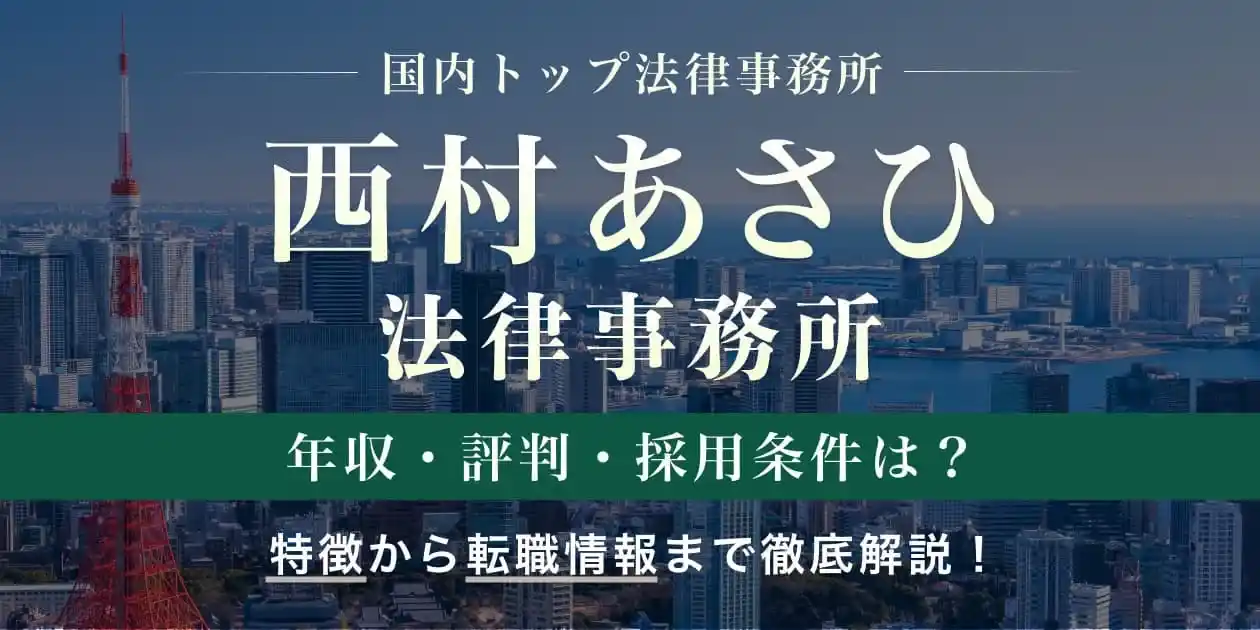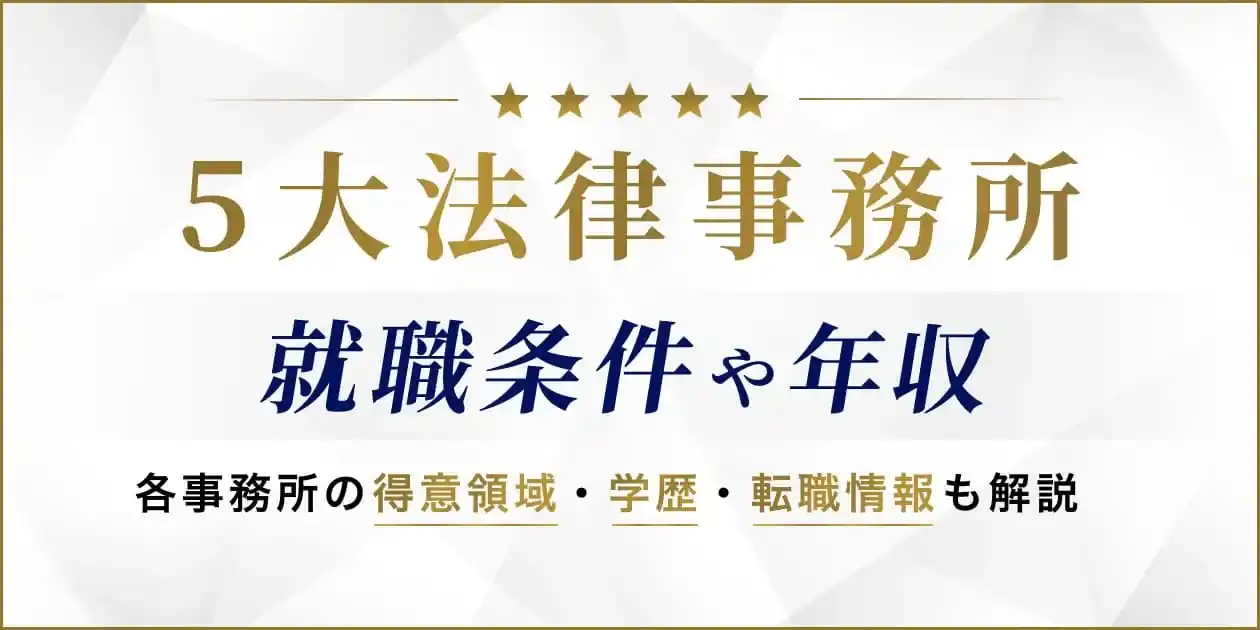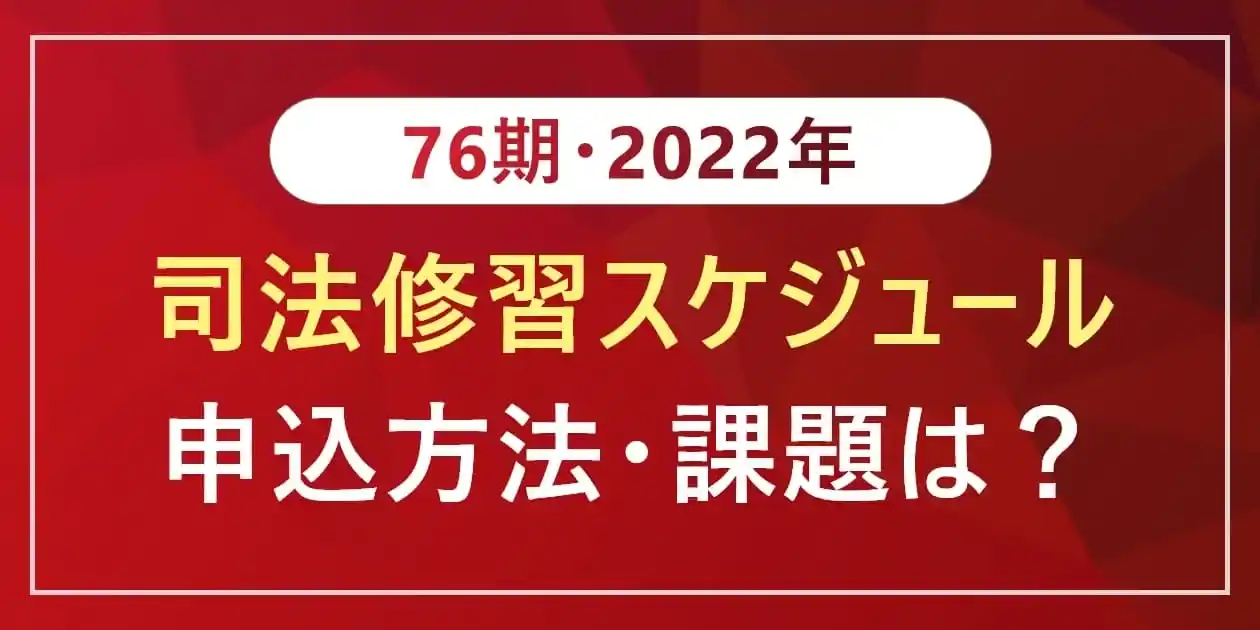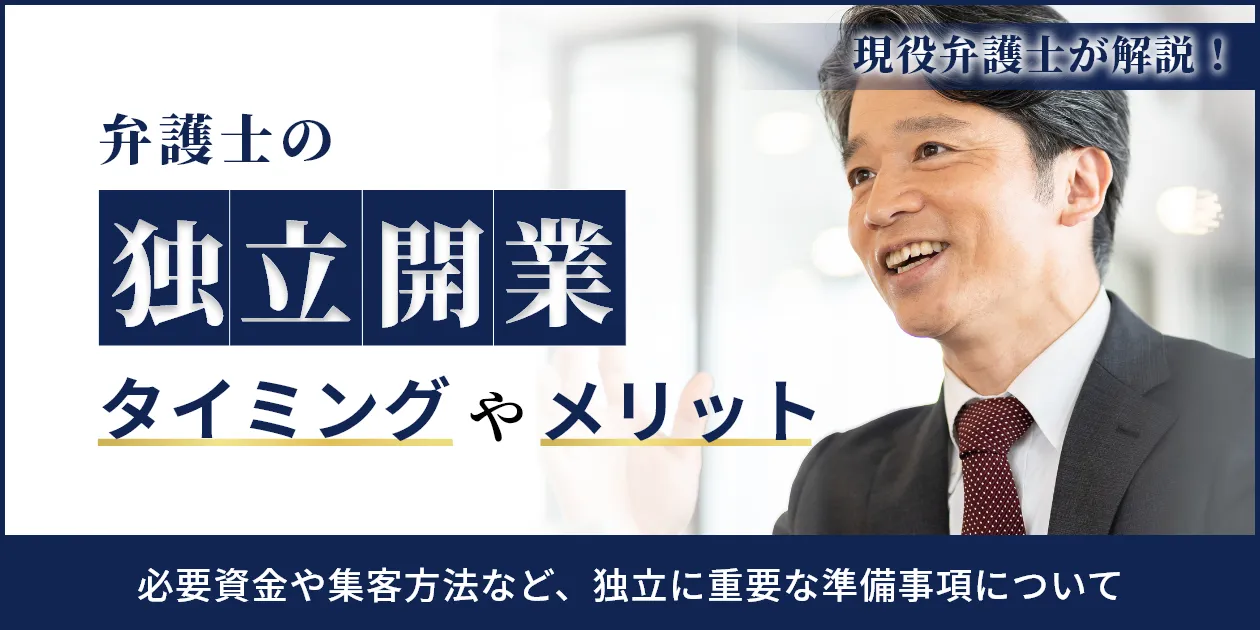
弁護士の独立・開業は何年目がおすすめ?準備事項や費用、メリットを解説

by 大阪弁護士会所属 弁護士M
弁護士(14年目)
- 担当職種:
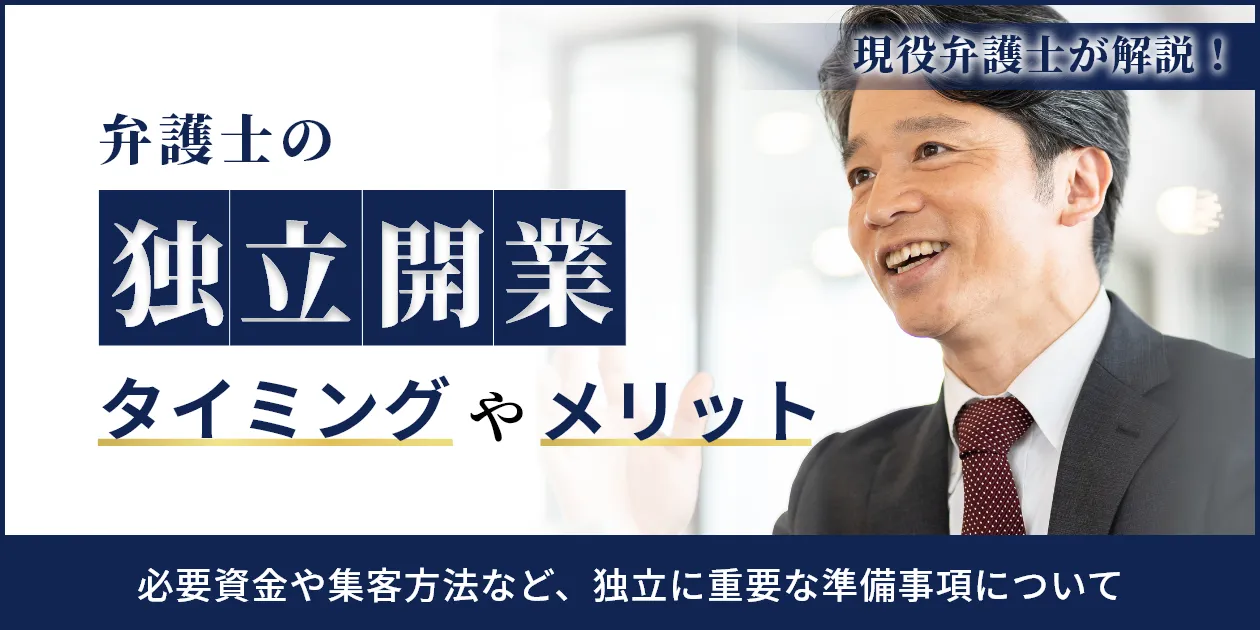
本記事では、現役弁護士の私から「弁護士の独立のメリットやタイミング」について解説します。
この記事を通して、ご自身にとってベストな独立のタイミングをご検討いただけますと幸いです。
また、独立に向けてキャリア形成をしたい方はぜひ弁護士専任の転職エージェントへご相談ください。独立歓迎の求人や今後必要なスキルなど詳しくお話させていただきます。
この記事の目次
弁護士が独立・開業するタイミング
結論から言うと、独立するタイミングは「弁護士登録から5〜10年後」がベストです。
2018年に日弁連が全国の弁護士を対象に行ったアンケート調査によると、登録5年未満の弁護士におけるアソシエイト弁護士の割合が約67%であるのに対し、登録5年~10年のアソシエイト弁護士の割合は約28%と大幅に減少しています。このデータから見ても、「登録から5~10年経過した段階で独立している弁護士が多い」ことが分かります。
アソシエイト弁護士として弁護士キャリアをスタートさせた人は、数年勤務して独立してパートナー弁護士となる人が多いということですね。
ただし、弁護士登録後5年が経過すれば誰でも独立できると言えるわけではありません。厳密には、「独立の準備が整ってきた段階」が独立のタイミングです。
逆に言えば、5年が経過しても、独立の準備ができていなければ独立は難しいです。5年が経過すれば独立の準備が大体整っているであろうということで「5年」と表現しています。
独立に向けて考えておくべきこと・準備事項
独立する際には開業資金、ランニングコストの資金面での計画を立てる必要がありますが、それに加えて、独立開業後のビジネスプランも考えておくことが必要です。
顧客確保の土台作り
顧客確保の見込みが立っているかは、独立する上で重要です。弁護士の顧客確保はやはり人間関係によるところが大きいです。
アソシエイト弁護士として勤務している間に依頼者や顧問先の方と信頼関係を築いていれば、独立しても新しい事件を依頼してくれたり、依頼者を紹介してくれたりします。また、弁護士会の活動などで他事務所の先輩弁護士との繋がりがあれば、その先輩弁護士が利益相反で受任できない場合などに紹介を受けられる可能性があります。
とはいえ、事務所からすると顧客が取られてしまう可能性もあるため独立を歓迎していない可能性もあります。今働いている事務所が独立に対してどのような考えなのかは知っておいた方がいいでしょう。
独立を考えているのであれば、出来る限り「独立歓迎」の事務所でアソシエイト弁護士として勤務すると独立がスムーズです。
独立後の取扱事件の内容をどうするか
自分がどのような事件を取り扱う弁護士になるかを検討することも重要です。これには、勤めていた法律事務所でどのような事件を扱ってきたかという、それまでのキャリアも影響します。
知財事件や企業法務を専門に扱ってきた人は、それまでのキャリアを活かし、独立後もそのような事件を取り扱った方が良いでしょう。
他方で、自分のできる範囲を拡大したいという人は、それまで扱ったことのない分野に取り組むのもありでしょう。その場合、該当分野の弁護士会の研修を受けたり、委員会に参加したり、書籍を読んだりと、研究の時間が必要になります。
独立後の集客方法
安定して仕事を得るためには、独立後の集客方法についても考えておく必要があります。
まずはホームページを作り、どのような事件を取り扱ってきたか、自分はどんな弁護士なのかといった内容を盛り込み、自身をアピールしましょう。
資金に余裕があれば、駅の看板などのポスティングによる広告を出してみるのも良いでしょう。最近では、テレビやラジオ等のメディアで宣伝活動をしている法律事務所もあります。
また、起業家の集まりや異業種交流会に参加し、色々な人と知り合うのも一つの集客方法です。できれば一度限りの会ではなく、月1回など定期的に行われる会で顔と名前を売り込みましょう。
さらに、弁護士会の研修や委員会に参加することも重要です。近年では、どういう研修をどれだけ受けたかによって、法律相談や事件を優先的に回してもらえたりします。また、委員会に参加すれば、委員会の事件を共同で受任できる可能性があります。
報酬基準をどうするか
弁護士報酬は、かつては弁護士会報酬規程に拘束されていましたが、現在は自由化されています。
そのため、事務所によって料金体系は異なります。着手金無料で完全成功報酬型を採用している事務所もあれば、着手金を多めにして、その分報酬を低くするなどしている事務所もあります。
基本的には、旧弁護士会報酬規程を参考にしながら、自分の事務所ではどのような料金設定にするのかを考える必要があります。
事務員(パラリーガル)を雇うかどうか
弁護士にとっては、書面作成や証拠の選別といった法律業務に専念するため、事務員の存在がとても重要です。しかし、当然ですが、事務員を雇うには人件費がかかります。
事務員は法律の知識がない人でも可能ですが、できれば他の法律事務所での勤務経験があるなど、ある程度は手続きの流れを知っている人が良いでしょう。そのような人材を雇うにはそれなりの人件費を覚悟しなければなりません。
独立当初は仕事がほとんどないことが予想されますので、安定するまでは事務員を雇用せずに事務作業も全て自分でやるのも選択肢の一つです。
弁護士の独立にかかる費用はどれくらい?
日弁連が発行する「即時・早期独立開業マニュアル(第三版)」によると、開業資金として「自宅開業なら50万円、執務場所を自宅以外に求めるのであれば100万円~300万円あれば開業は十分可能である」とされています。
具体的には、以下のような初期費用が想定されます。
- 新しく事務所を借りる場合は保証金
- 購入する場合は購入資金、事務所内の内装費用
- コピー機
- パソコン
- ソファやテーブル等の応接セット
- 仕事で使うであろう書籍
また、独立後に経営が安定するまでのランニングコスト(賃料や人件費)として、半年くらいは仕事がなくても支払えるだけの資金を準備するのが望ましいです。
どんな場所を借りるかで賃料は異なりますが、月額10万円の物件を借りた場合、水道光熱費、コピー機のリース代や判例検索システムの月会費、弁護士会費等も含めて考えれば、最低でも月20万円の経費が必要です。半年分となると、120万円は準備しておいたほうが良いでしょう。
あくまで目安ではありますが、開業資金と併せて200万円~400万円ほど準備できると安心かもしれません。
独立に失敗するケースや理由
よくある独立失敗の理由は、以下のようなものが多いです。
- 顧客確保がうまくできなかった
- 経験不足・能力不足だった
- 資金が回らなかった
詳しくは以下の記事で解説しています。
弁護士が独立・開業するメリットとデメリット
まずは独立開業するときのメリット、デメリットを解説します。
メリット
最大の独立のメリットは「自由な働き方ができる」という点です。
働く時間はもちろんですが、どんな事件を受任するのか、どこを拠点にするかなど事務所の方針を自身で定めることができます。
また、自身が可能な限り案件を持てるため勤務弁護士として働いていたころよりも年収が上がったという方も多くいらっしゃいます。
デメリット
デメリットは、売上のすべては自分に委ねられているという点です。案件を獲得するため営業活動を行う必要があったり、勤務弁護士をやっていた時より多忙になることもあります。
案件をこなせばこなすほど売り上げは上がり、自分の動きがダイレクトに収入に反映されますが、逆に言うと「案件がなければ収入もない」ということです。
また、自身がトップになるため事件処理の相談を出来る同僚や先輩が他にいないという点もデメリットです。
退職する際に必要な手続き・円満退職のポイント
アソシエイト弁護士が独立開業する際には、どのようにして辞めるかも非常に重要です。勤務していた事務所と円満な関係をキープできれば、退職後も事件を回してくれる可能性があります。
ここでは、退職に必要な手続きや円満退職のポイントを解説します。
口頭で退職の意思をパートナーに伝える
アソシエイト弁護士が辞めるための手続きは、特に複雑なことはなく、ただ「退職の意思を明確に示す」ことができればOKです。
退職意思を伝える先は、基本的にパートナー弁護士です。口頭で伝えることが多いですが、はっきりと辞めるという意思を伝える方が良いです。
退職時期・引き継ぎを行う旨を伝える
また、退職意思を伝える際には、退職時期も明確にすべきでしょう。一般的は、退職の6ヶ月くらい前に退職意思を示すケースが多いように思います。6ヶ月あれば、引継ぎも十分に可能でしょう。最低でも3ヶ月ほど前には伝えた方が良いです。
円満に退職するためには期間の余裕をもって、「他の弁護士に引き継ぐか」「自分が独立後もそのまま引き継ぐか」などを事務所と話し合えるようにしておくべきです。
注意すべきこと
退職・独立にあたり、勤めていた前の事務所の悪評を言って、依頼者を引き抜くようなことは信義に反します。勤務していた事務所への背信行為はやめましょう。
勤務していた事務所の依頼者からの信頼により、独立後もあなたに依頼し、受任すること自体は問題ありません。あくまで他事務所との関係が悪くなるような行為・言動は控え、良好な関係を築けるようにしましょう。
独立支援を行う事務所で働くと独立しやすい
「独立したいが、具体的に何から始めれば良いのか分からない」「独立が向いているのか分からない」という方は、独立支援・独立歓迎を掲げる事務所で働いてみるのも選択肢の一つです。
独立を歓迎する事務所で働くと、以下のようなメリットがあります。
- 独立の手続きやノウハウを教えてくれる
- 顧客やクライアントの獲得の仕方を教えてくれる
- 独立のための退職申し出を気持ちよく迎えてくれる
弁護士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」では、独立支援・独立歓迎の法律事務所の求人を多数ご紹介できます。