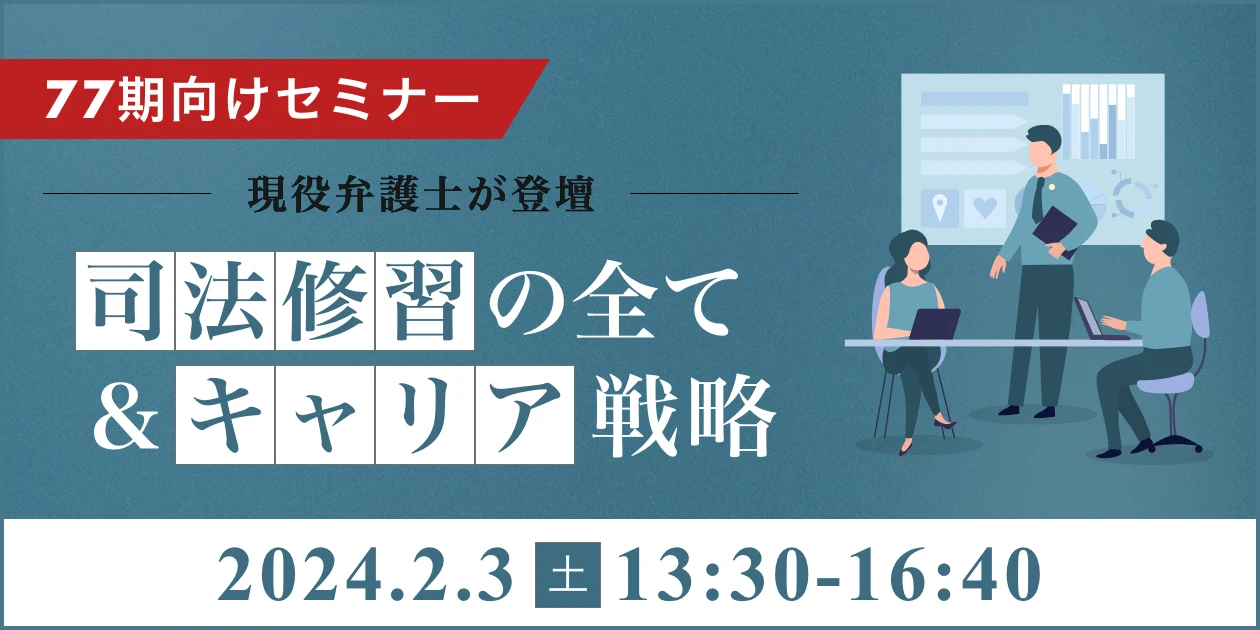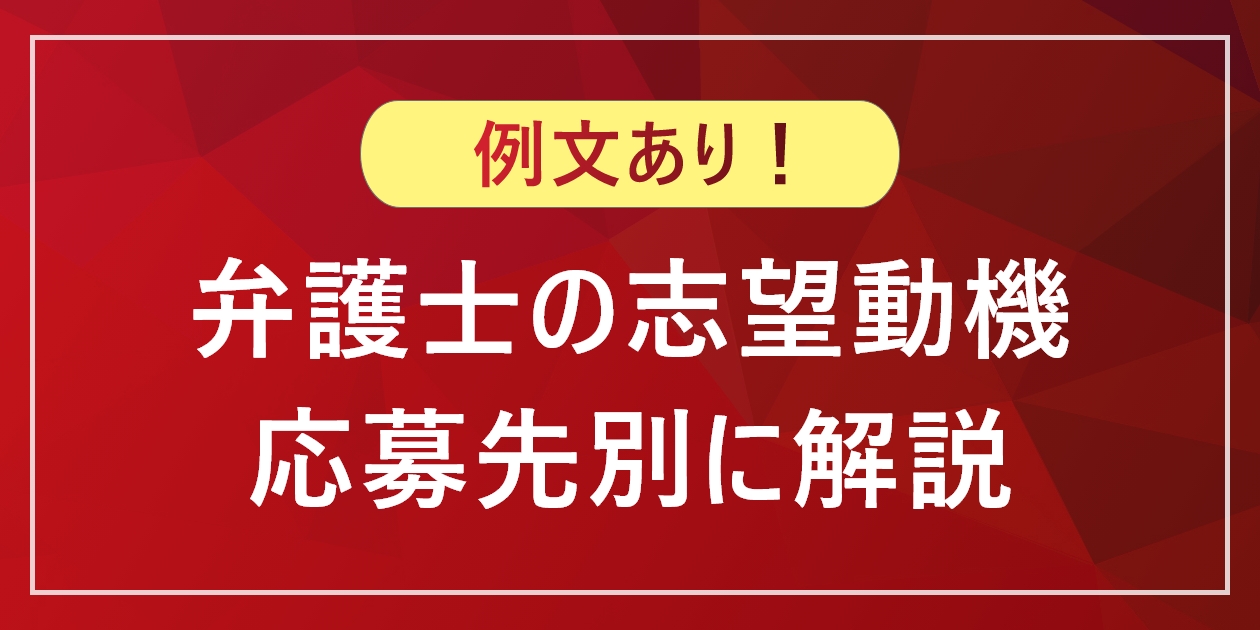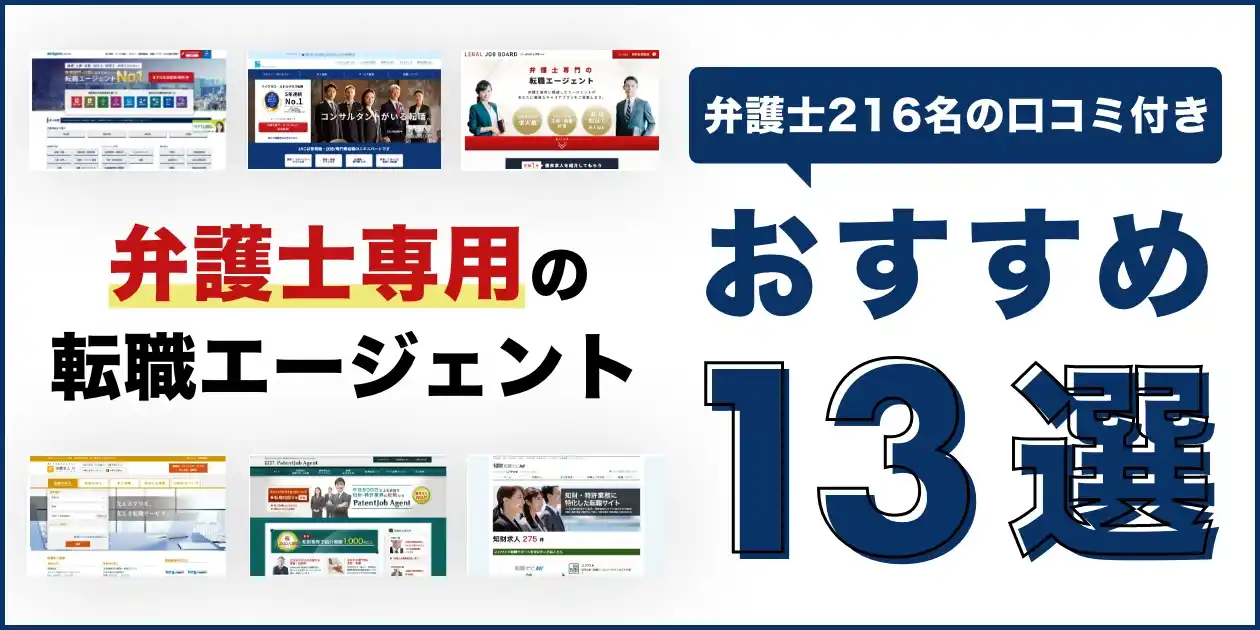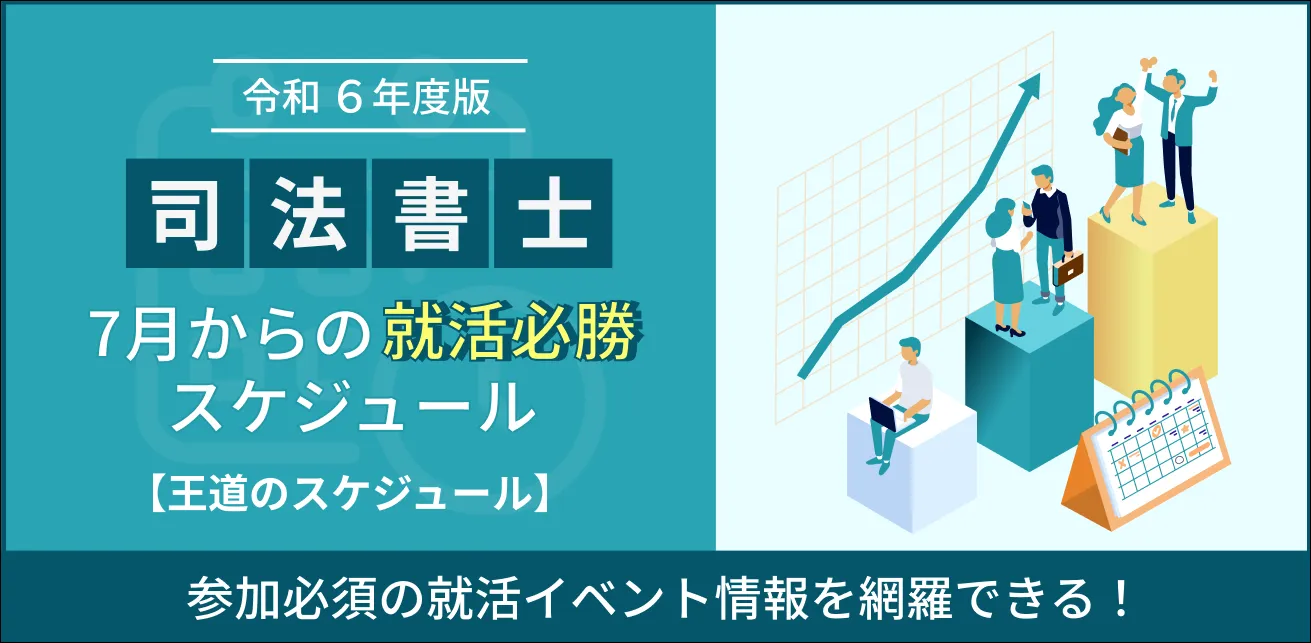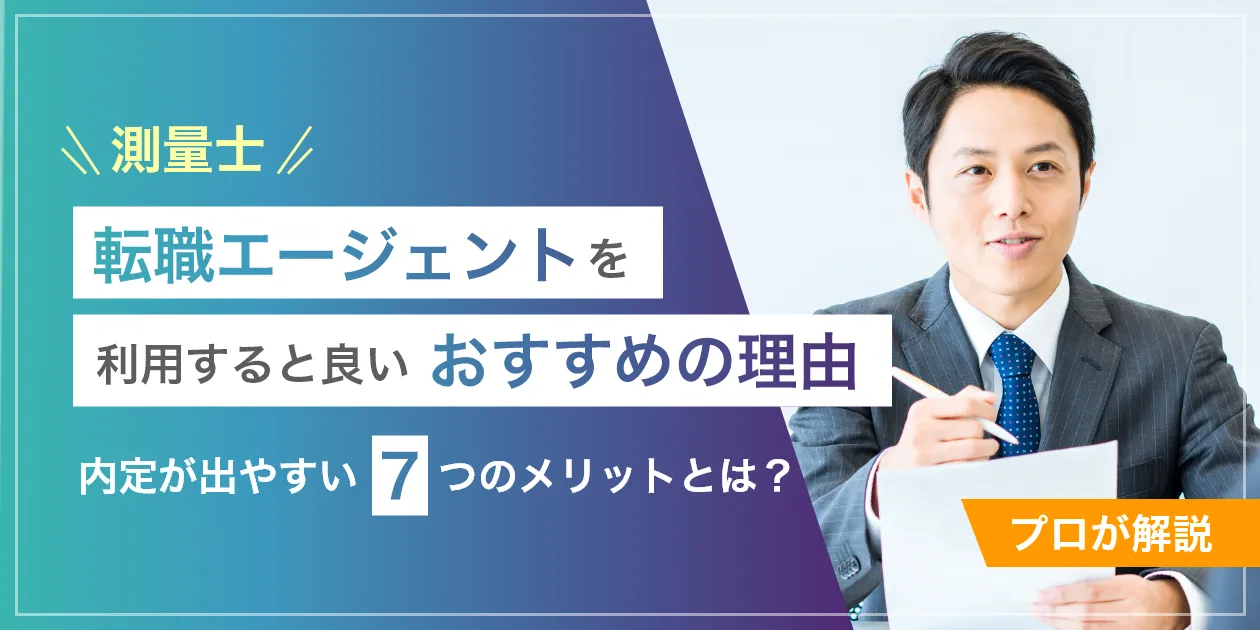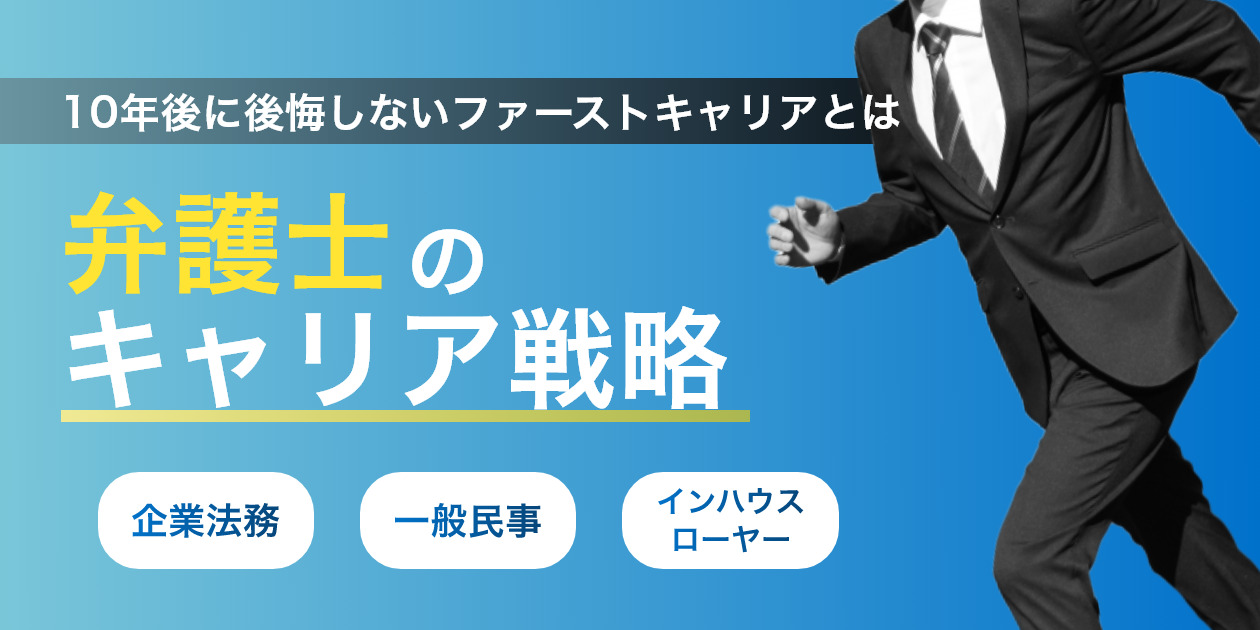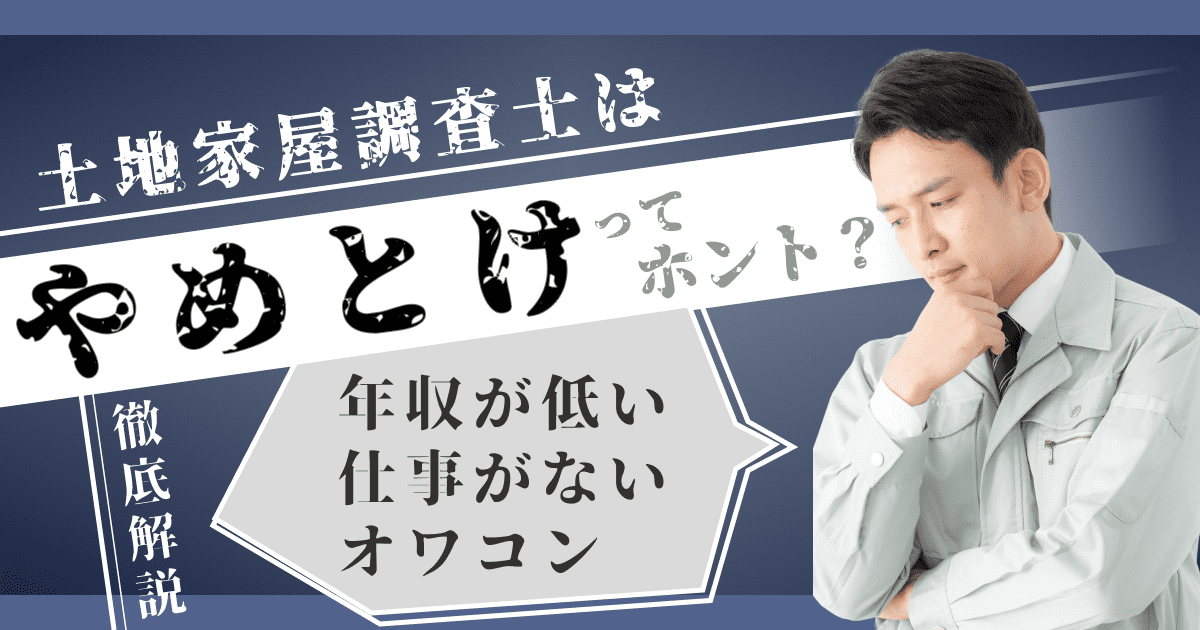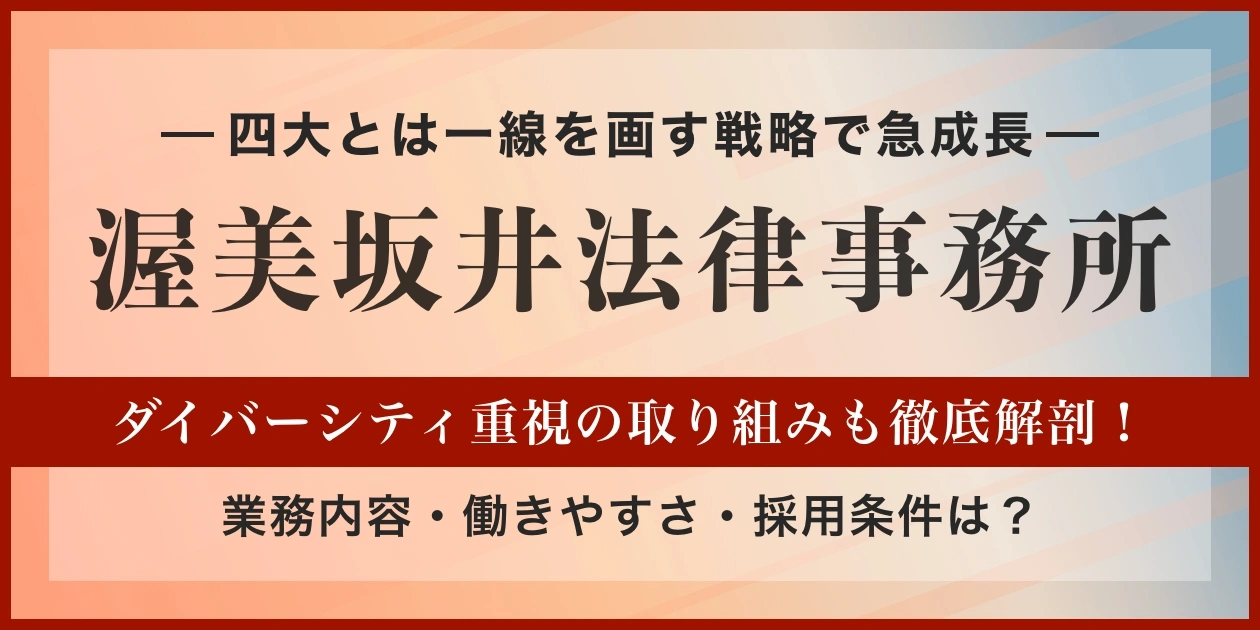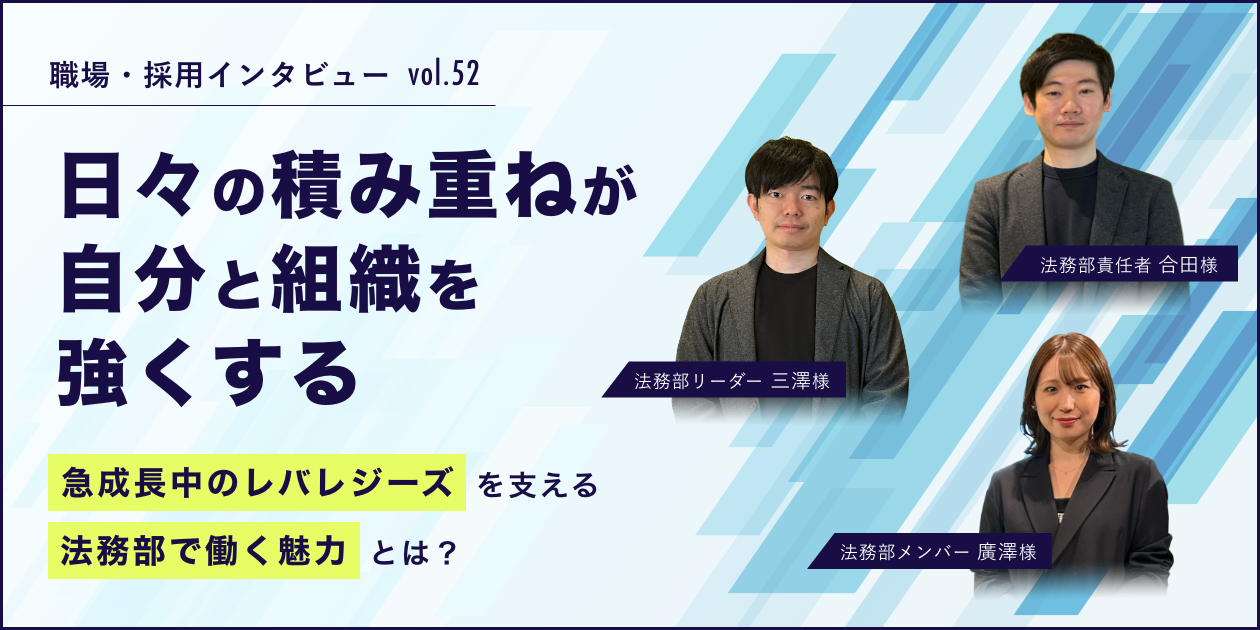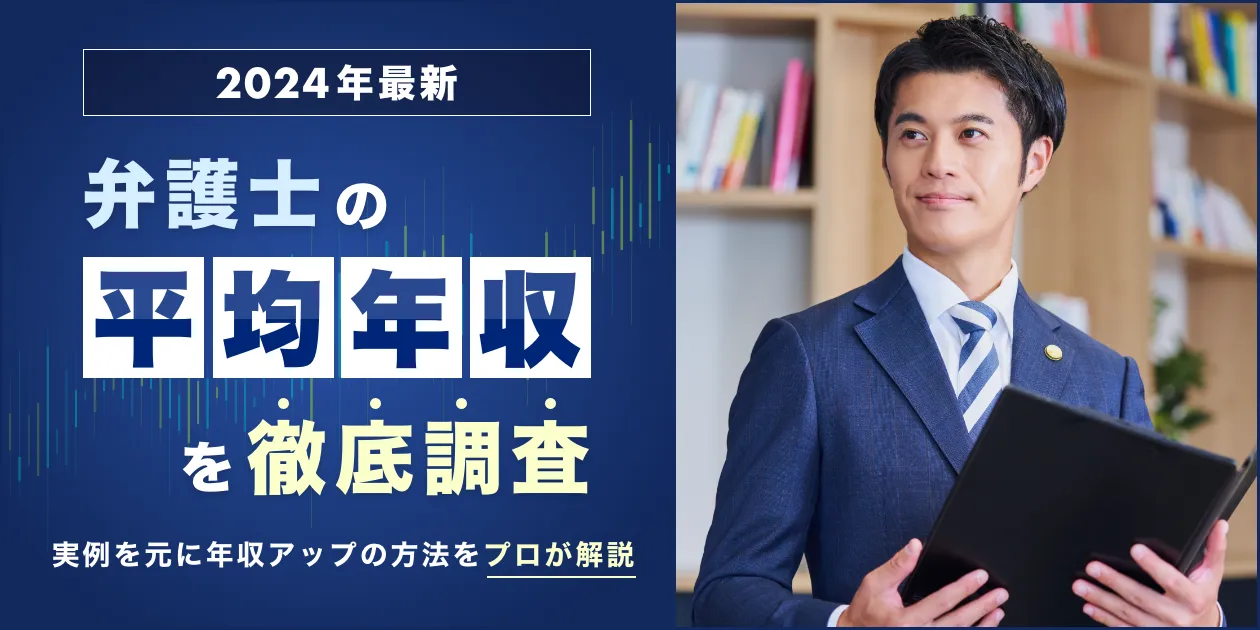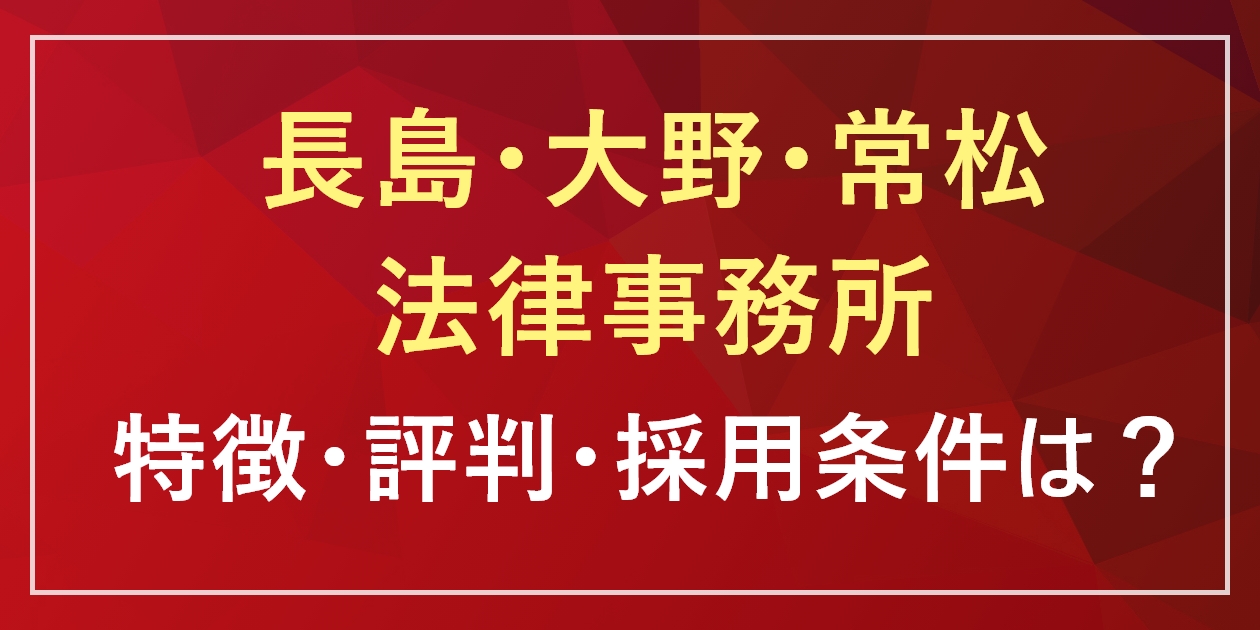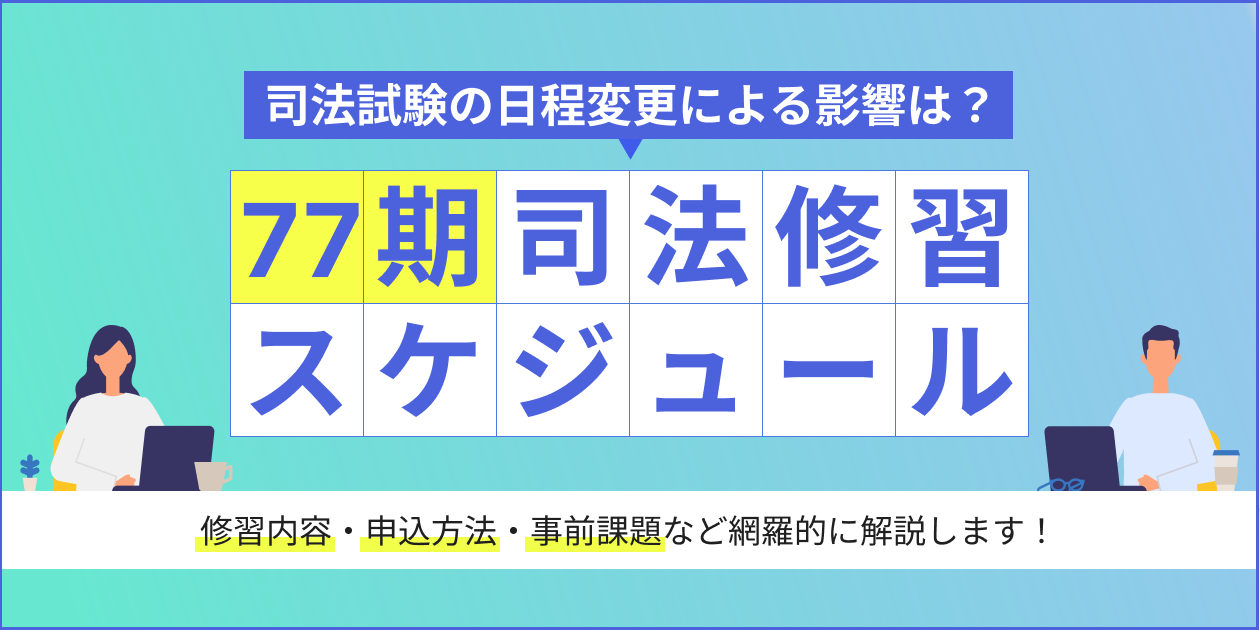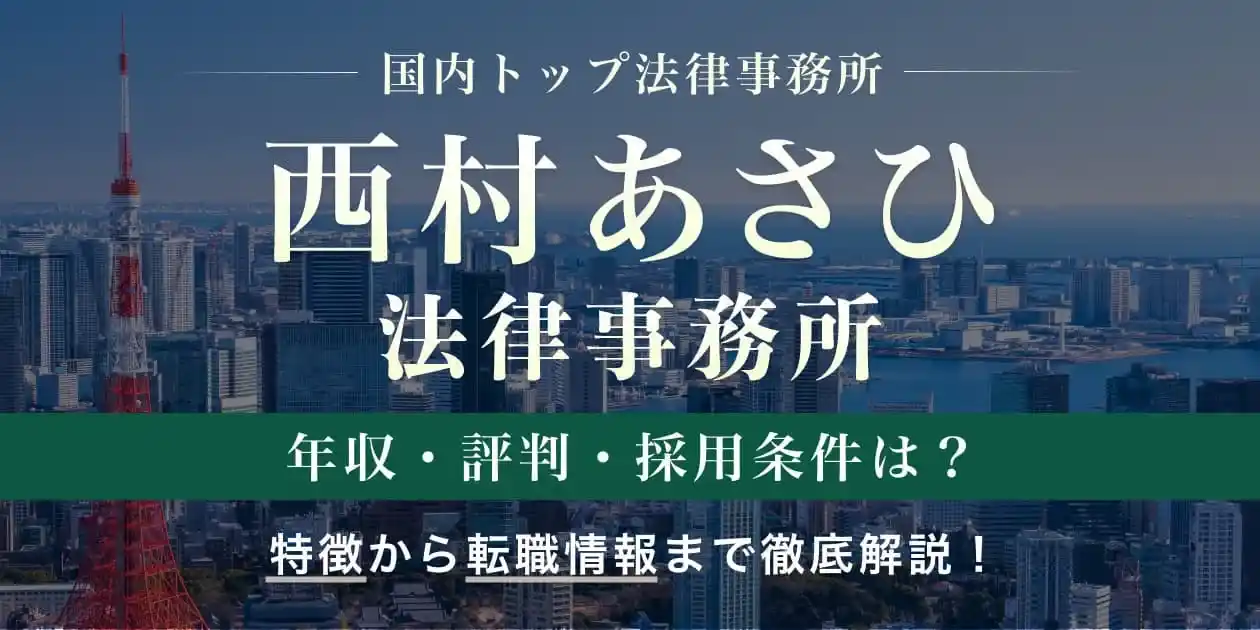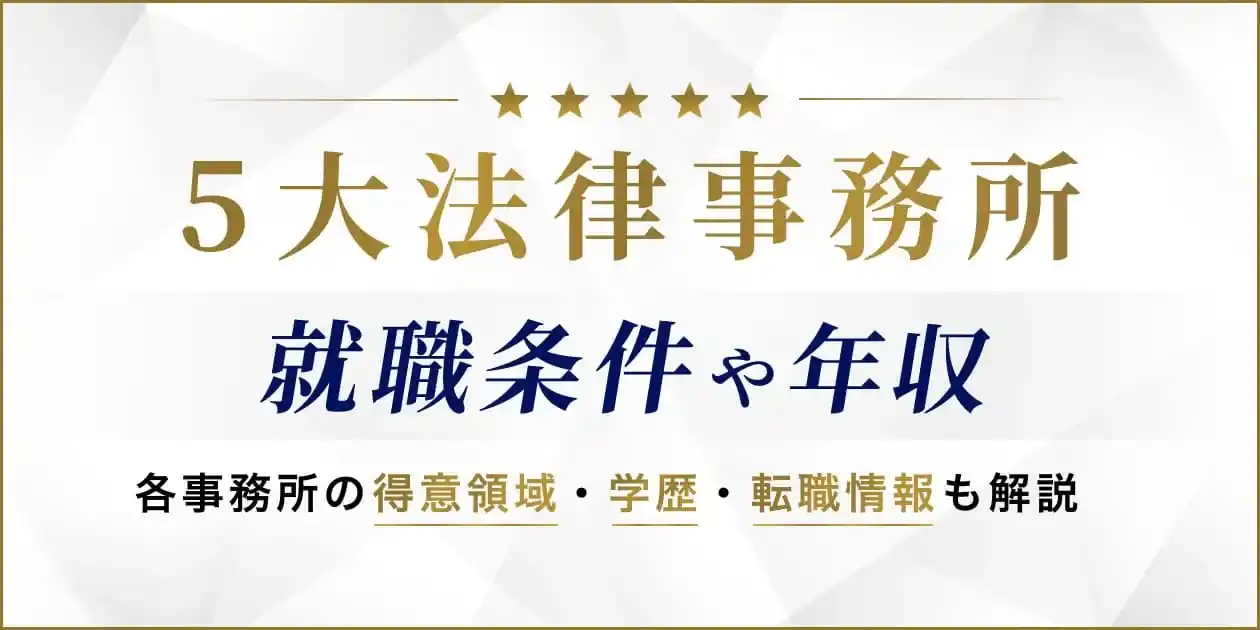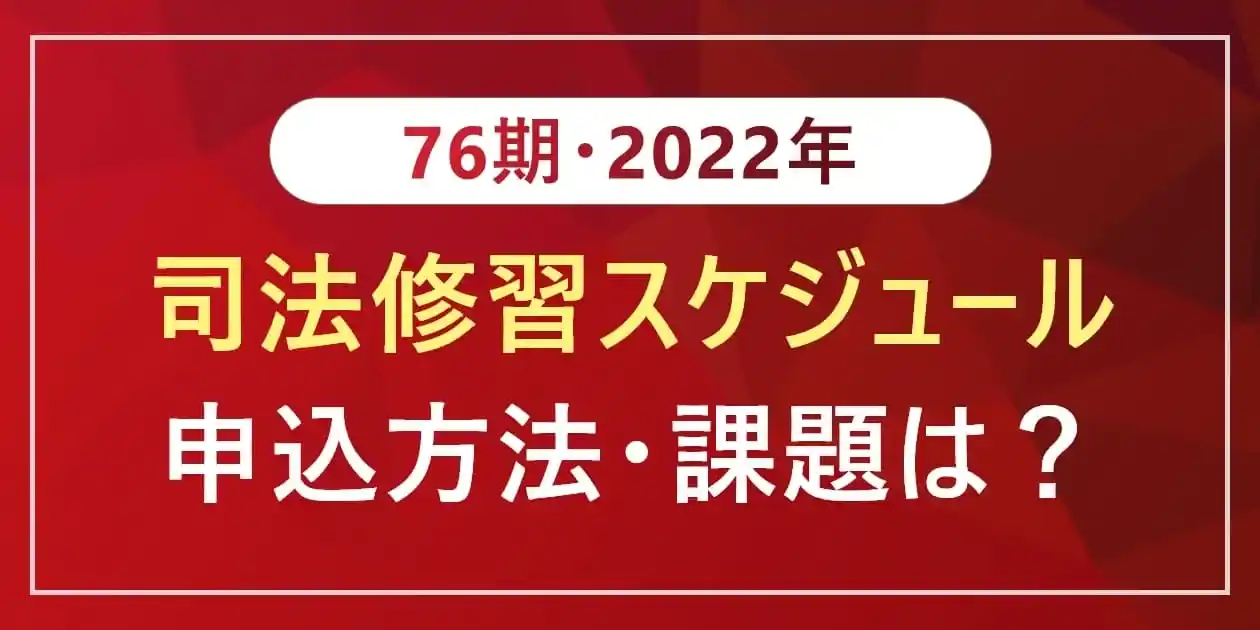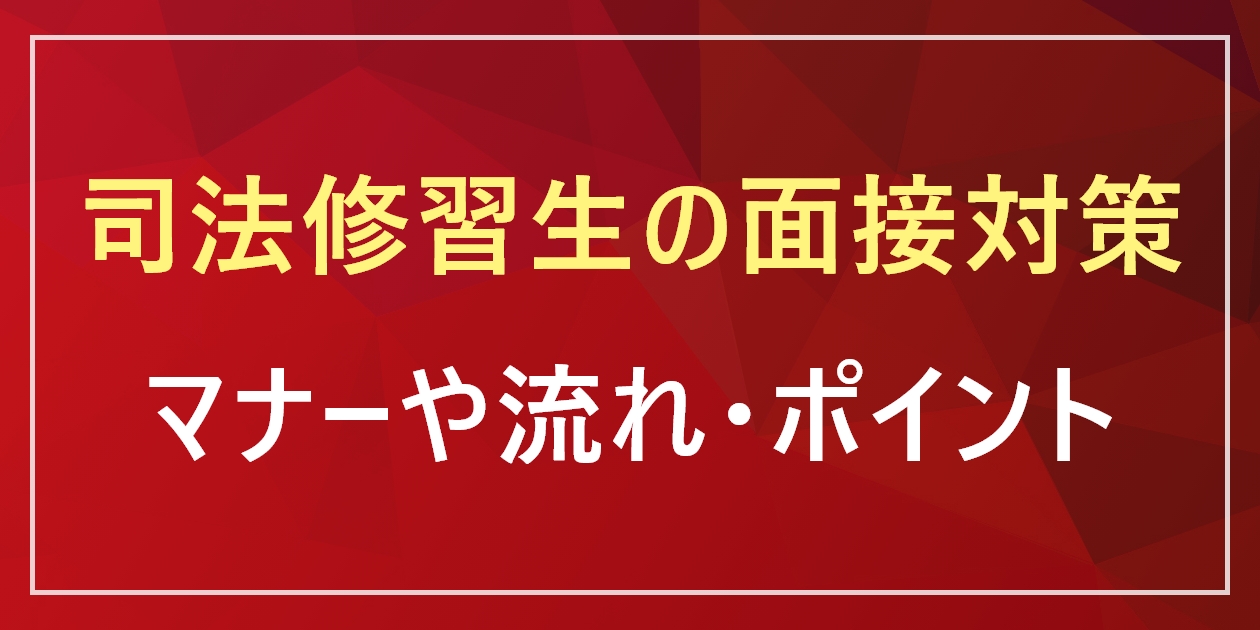
司法修習生の面接対策|入室からお礼メールまでの流れ・内定獲得のためのコツ

by LEGAL JOB BOARD 森田
転職エージェント
- 担当職種:
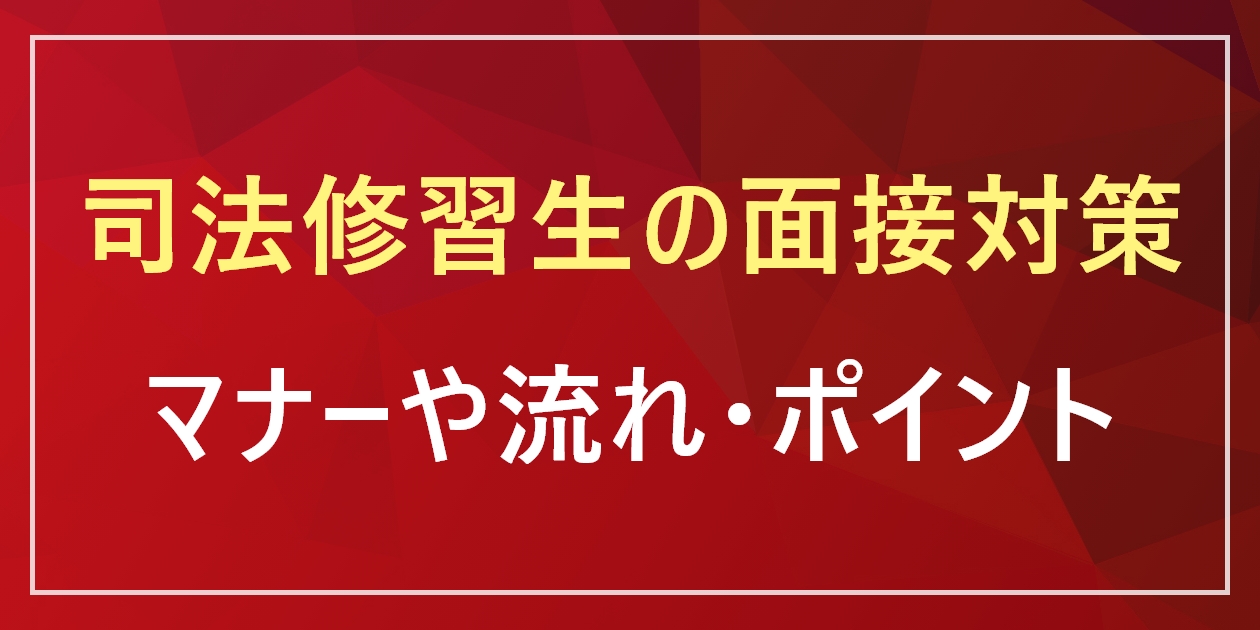
こんにちは。弁護士の転職エージェント「リーガルジョブボード」の森田です。
本記事では、司法修習生が内定を獲得するための「面接対策」について解説します。
面接では受け応え以外に、身だしなみや挨拶、入室の仕方、名刺交換の作法、話し方、面接後のコミュニケーションなど、様々な観点から評価されることになります。
また、コロナ以降は「オンライン面談・ウェブ面接」も主流になってきているので、オンライン面接の対策もあわせてご紹介します。
面接対策に必要なポイントを網羅した記事ですので、最後まで目を通してから選考に臨みましょう。
この記事の目次
面接開始から終わりまでの一連の流れの説明
まず、面接開始から終了までの流れを説明します。
面接会場到着
面接会場に到着したら、手鏡やお手洗いの鏡で身だしなみをチェックしましょう。スーツは乱れていないか、髪型は崩れていないかを見るだけではなく、表情にも気を付けてください。
身だしなみを確認するために一度立ち止まれば、気持ちを落ち着かせることもできます。
受付
当然ながら、指定された時間の10分前には受付に到着するようにしましょう。遅刻はもってのほかですが、あまり早すぎても相手に失礼になります。やむを得ない事情で遅れてしまう場合は、必ず電話で連絡を入れるようにしましょう。
面接会場に入ったら受付で、「本日○時(時間)に面接のお約束をさせて頂いております、〇〇(名前)と申します。〇〇様(約束している方の氏名)にお取次ぎをお願い致します。」と伝えましょう。
入室
入室時は軽くドアをノックします。中から「どうぞ」と声がかかってから開けるようにしてください。ドアをあまり勢いよく開かないよう注意し、閉める際はきちんと後ろを振り向いて静かに閉めます。
面接官を見て一礼し「よろしくお願いします」と声をかけましょう。面接官に進められてから着席してください。
面接
入室後は「今日は電車で来ましたか?」などの雑談で軽いコミュニケーションをとった後、面接官進行のもと面接が進んでいきます。面接が始まれば、基本的には面接官からの質問に答える形で、自身の経歴や強みをアピールしていきます。
面接中は、背筋を伸ばし手を軽く膝にのせておきます。話を聞くとき、話をするときは面接官の顔を見てしっかりと話をするように意識しましょう。
退室
面接が終わったら、椅子から立ち「本日はお忙しい中、お時間を頂きありがとうございました」と一言お礼を述べます。
その後に深いお辞儀をし、ドアの前で面接官の方を向き「失礼致します」と再度丁寧にお辞儀をしましょう。入室時と同じように、丁寧にドアを開け閉めして退室し、面接は終了です。
お礼メールについて
面接後は、何か特別なことをする必要はありませんが、
- 面接で伝えきれなかったことをどうしても伝えたい
- 面接で上手く答えられなかったことを補足したい
といった方は、お礼状やお礼メールを送ってもいいでしょう。
何人もの応募者を選考するため、お礼状によって合否が変わる可能性は低いですが、採用への最後の一押しになるかもしれません。
また、お礼メールで人柄を評価してもらえる可能性もあります。送って損はありませんので、特に志望度の高い事務所・企業の面接後は、お礼メールを送ると良いでしょう。
面接の種類
面接の種類について、以下で解説します。
グループ面接
グループ面接は、司法修習生3~4名程度で行われる面接です。採用側の弁護士は、1~2名ほどが参加することが多いです。
グループ面接は大手事務所において、採用活動の比較的初期に行われることが多いです。
受ける側は他の修習生を見ることができるのがメリットであり、デメリットでもあります。採用側からすると、一度に数名を比較できるメリットがあります。
食事会形式
食事会形式は、司法修習生数名と採用側弁護士が食事をしながら話をする形式です。
打ち解けた雰囲気で話ができ、司法修習生の人となりを確認しやすいうえ、食事時間で面接できるため、忙しい事務所が行う傾向にあります。
もし参加する場合は、口に食べ物が入った状態で話さないなど、基本的な食事マナーに注意しましょう。
個別面接
2回目の面接は、個別面接で実施されるケースが多いです。司法修習生1名に対し、採用側は弁護士1~2名で面接を行います。他の修習生はいないので、自身を存分にアピールできるメリットがあります。
しかし、うまく話をしていかないと、場の空気が温まらない面接になってしまいます。準備さえできていれば問題ありませんので、安心して挑んでください。
最終面接
最終面接は、個別面接と同じ形式です。内定を出した場合、入所する気があるかなど、踏み込んだ話が出てきます。
初任給や業務内容、雇用条件などの話がなされ、双方の最終確認の場にもなります。しっかりと疑問点や不安点を確認しましょう。
内定獲得のための面接対策(対面・オフライン編)
面接対策のポイントを解説します。まず、オフラインでの面接・対面編です。
①事務所のリサーチ
面接対策の一つとして、面接前の入念なリサーチが挙げられます。これは、オンライン・オフラインのどちらでも重要です。
事務所が請け負っている業務や、事務所の特徴、求人票に書いてある情報は、頭に入れておくようにしましょう。
その他に調べておくべき内容は、代表弁護士やパートナー弁護士の経歴です。経歴を調べることで、どういった内容の案件が多いのかを予測しやすくなります。また、所属弁護士の修習期を調べると弁護士の退職頻度も予測できます。
弁護士以外の職種(特にパラリーガルや事務員)の人数を見ておくと、事務業務を振り分けて効率的に業務を進めている事務所なのか、すべての業務に関われる事務所なのか、把握できます。
疑問に思ったことを聞ける機会は面接しかないため、希望の事務所は徹底的にリサーチし、理解しておくことが大切です。
②身だしなみ
男女ともにスーツ着用が基本です。スーツの色は黒やグレー、濃いめの紺など、シャツは白が無難です。派手な色や柄の主張が強いものは、避けたほうがよいでしょう。
髪型は、自然な黒髪が誠実さが伝わりやすいのでおすすめです。前髪が目にかからないようにし、男性は長すぎないか、女性は長ければ結んでおくと清潔感があり、顔の印象も明るくなります。
③面接先に入る時の表情に注意
面接官以外にも、事務所や会場で受付の人などに会うことになります。もしかすると、代表にばったり会うかもしれません。
真顔だと怒っているように見えてしまったり、マイナスイメージを与えてしまう可能性があります。眉間にしわが寄っていたり、機嫌が悪そうに見えないよう注意しましょう。
また、コートを着ている場合は綺麗に畳んで手に持ち、携帯の電源はオフにしてください。
④自己紹介・自己PRについて
自己紹介・自己PRは、ハキハキと明るい表情、謙虚な姿勢で伝えるようにします。第一印象で明るさ・謙虚さを伝えることで、面接官に「この人のことを知りたい・一緒に働きたい」と感じてもらえるようになります。
ちなみに、「経歴を踏まえて自己紹介をしてください」と言われることがありますが、司法修習生の場合は、
- 大学時代経験したこと(サークルや勉強、アルバイトなど)
- (社会人から司法修習生になった方は)今までの仕事の経歴
を話しながら、どんな分野・行動に長けているのかをアピールできるとベストです。また、アピールを通して「入職後にやりたいこと」も伝えられると、より好印象を与えられます。
⑤大学で学んだことや経歴について
採用側が大学で学んだことを聞くのは、事務所でどのように活躍してくれるのかを考える意図があります。以下のような内容を伝え、自分がどんな人物なのかをアピールします。
- 何を学んだのか
- 学んだことの詳細
- どんな結果がでたのか
- 結果からどう感じたのか
【例文】
「大学のゼミでは、実際の判例をもとに学生同士で討論を行いました。討論には法律の条文や相手の発言への理解が必要で、それをなくしては公平な契約成立につなげることは出来ないと考えています。」
⑥志望動機や弁護士を目指した理由
志望動機や、弁護士を目指した理由に関する質問も想定されます。特別なエピソードがなくてもかまいませんので、弁護士になるきっかけを話しましょう。
例えば、「冤罪事件や公害訴訟などでの弁護士の活躍をドキュメンタリーでみて、困っている人を助けたい。多くの人を助ける可能性を秘めている弁護士を目指そうと思いました。」といった方は多くいらっしゃいます。
志望動機は非常に重要なので、以下の記事で別途ポイントをまとめています。ぜひ一度ご確認ください。
合わせて読みたい記事はこちら
⑦面接で想定される質問の回答・聞くべき質問について
司法修習生の面接は、経験者よりも長くなる傾向にあります。「スキル(ポテンシャル)」や「弁護士の素質」を見極めるのが、未経験者ゆえに難しく、採用側が慎重になるためです。
前述した質問以外にも、様々な質問を想定し、回答を用意しておきましょう。例えば、以下のような質問が想定されます。
- 模擬裁判で困難に陥った点は何か
- 将来のキャリアプラン
- この事務所でないといけない理由
意地悪な質問はあまりないですが、ごく稀に実際の案件と絡めたような複雑な質問をされることがあります。例えば「こういった案件を頼まれたが、あなたならどのように解決しますか?」といったものです。
それらのほとんどは、発想や倫理観を確認する意図によるものです。答えが決まってないような質問もありますし、質問者は完璧な回答を求めていないことが多いので、焦らず回答するように心がけましょう。
⑧面接官への質問(逆質問)
面接の最後には、ほぼ確実に「何か質問はありますか?」と聞かれます。そのため、予め質問をいくつか用意しておくようにしましょう。逆質問することをおすすめしたい内容を2点まとめます。
①業務フローについて
業務フローについて質問すると、その事務所がどのくらい忙しいのか、どういった働き方をしているのかが把握できます。
例えば、「一つの案件に対して何人で対応しているか」という質問であれば、どのくらいの規模の案件が多いのか、ある程度把握できるでしょう。「業務分野やクライアント層、その業務にあたっているのは誰なのか」という質問であれば、自分がどのような仕事を任されるのかが予想できます。
実際に、入職前に質問できず、「海外案件に携わりたいと思って入社したけど、海外案件は所長が全部担当していた」といったケースもあります。業務に関して気になることを質問できれば、入職後のミスマッチの可能性も下がります。
②事務所の体制や制度について
事務所の体制や制度について、気になることがあれば質問してください。特に弁護士は、将来的に独立やパートナーといった道を選択する方も多いです。
事務所によっては、アソシエイトからパートナーへとなる方もいます。パートナーになれる制度がある事務所ならば、「アソシエイトからパートナーになる条件は?平均的に何年働いてパートナーになる人が多いか」といった質問をすると、キャリアプランが立てやすいでしょう。
独立志向がある方は、「新規営業活動をやっていいのか、やっている先輩はいるのか」などが気になると思います。独立志向が強い職種であることは、事務所側も理解していますので、そのような質問をしても悪い印象にはならないことがほとんどです。
⑨前日までの体調管理に気を付ける
体調不良での面接は、パフォーマンスを低下させます。最大限に自分をアピールするために、ベストな状態で挑みたいところです。どうしても体調が悪い場合は、応募先に連絡を取り、面接の日程調整を行うなどしてください。
内定を獲得するための面接対策(ウェブ面接・オンライン面談編)
コロナ以降、オンラインでの面接・面談は定番となりつつあります。ここからはオンライン面接のポイントを解説します。
①スマホよりパソコンの使用がおすすめ
スマホは手振れや倒れることがあるので、安定して使用できるパソコンでの面接がおすすめです。スマホは思っているよりも小さく映ってしまい、表情が見えづらいことがあり、パソコンの方が感覚的に「しっかりしている」印象を与えることができます。
また、パソコンに搭載されているマイクを使用するのではなく、マイク付きのイヤホンを準備することを推奨しています。搭載されているマイクやスピーカーの利用は、音を反響させてしまったり声が拾いづらい心配があるためです。
②使用するツールが入っているか、正常に繋がるかを事前にチェック
事前にZoomやGoogle meetなど、どのツールを使用して面接を行うか知らされます。面接までにアプリをダウンロードし、正常に使用できるかをチェックしましょう。
事前準備が甘く開始が遅れてしまった場合、印象を落としてしまう可能性が高いです。オンラインでのやり取りが苦手と思われるのは、現代においてかなりマイナスになってしまいますので、必ずチェックをしておきましょう。
③面接に集中できる環境づくり
ペットは違う部屋に連れて行ったり、お子様のいないタイミングで調整するなど、集中して面接を行える環境をつくりましょう。
また、宅配が来ないように時間指定をするなどの注意が必要です。宅配などで家のチャイムが鳴ってしまった場合、相手側から「大丈夫ですか?出ても大丈夫ですよ」など一言あるまでは対応しないようにしましょう。
④対面時よりリアクションは大きめに
対面と比べるとオンライン上では、互いの表情がわかりづらい、コミュニケーションがとりづらい、といった場合があります。そのため、いつもより少し大きなリアクションを取ると意欲が伝わりやすく、好印象を与えることができます。
また、対面時では直接顔を見て話せますが、オンライン上だとアイコンタクトを取ったりするのが難しくなります。オンライン面接時は、カメラやZoomなどの画面をパソコンの中央上部に移動させ、そこに目線を合わせて、相手の顔をみて話すようにしましょう。
⑤受け答えは短く、端的に
これはオフラインでも言えることですが、長くだらだらと話し続けてしまうのはタブーです。
オンラインの場合、温度感を把握するのが対面よりも難しく、人によっては長く話しすぎる傾向にあります。オンラインではより一層、「短く、端的に」話せるようにしましょう。
⑥退室は最後に
面接終了後、ZoomやGooglemeetから退室するタイミングですが、基本は一番最後に退室するようにしましょう。
面接官側から「では、退室してください」と促されたり、あまりにも相手が退室しない場合は「本日はありがとうございました。失礼致します。」と言ってから退室してください。一言添えれば印象を悪くすることはありませんので、安心してください。
司法修習生は転職エージェントを活用すると内定が出やすい理由
司法修習生の就活は、内定の可能性がグッと上がる「転職エージェント」の活用を強くおすすめします。
転職エージェントとは、弁護士業界に詳しいエージェントがあなたのスキルや資質を見極め、活躍できる・ミスマッチのない職場の求人を紹介してくれるサービスです。
また求人紹介に加えて、以下のサポートも無料で行ってくれます。
- 選考突破のための書類・面接対策の徹底
- 失敗しない法律事務所の選び方の情報共有
- キャリアパスの策定やご相談
- 求人の職場口コミやブラック度の情報提供
ちなみに、自分で求人に応募するより、転職エージェントを経由して応募した方が内定率が大きく上がることをご存知ですか?理由は以下の記事に書かれています。
合わせて読みたい記事はこちら
弁護士・司法修習生専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」では、法律事務所やインハウスの求人をご紹介できます。
ご登録いただくと、ウェブサイトには掲載されていない、登録者限定の「非公開求人」を数多くご紹介いたします。
いま転職活動中の方、転職をうっすらと考えている方、どんなご相談にも乗りますのでお気軽にご連絡ください。