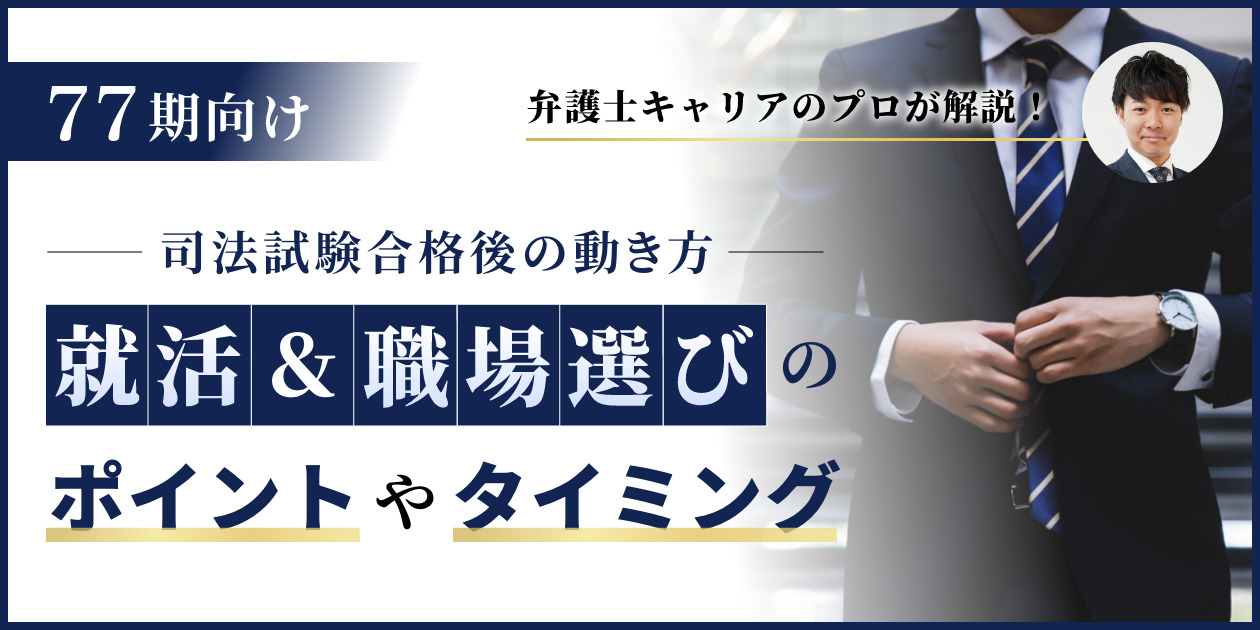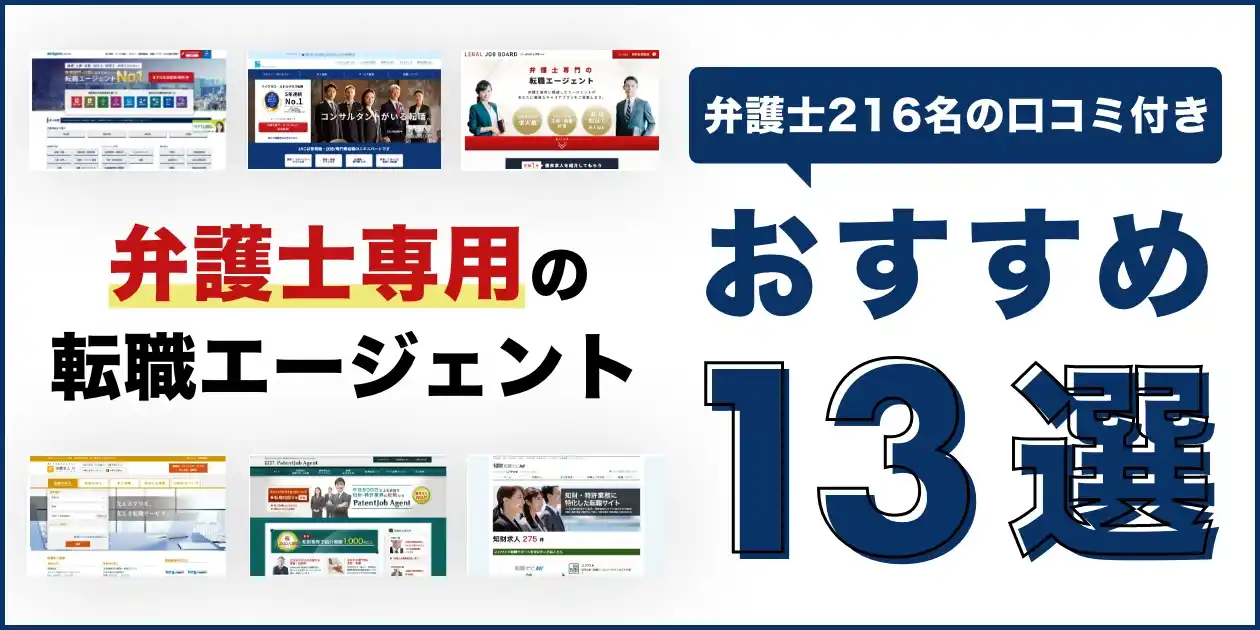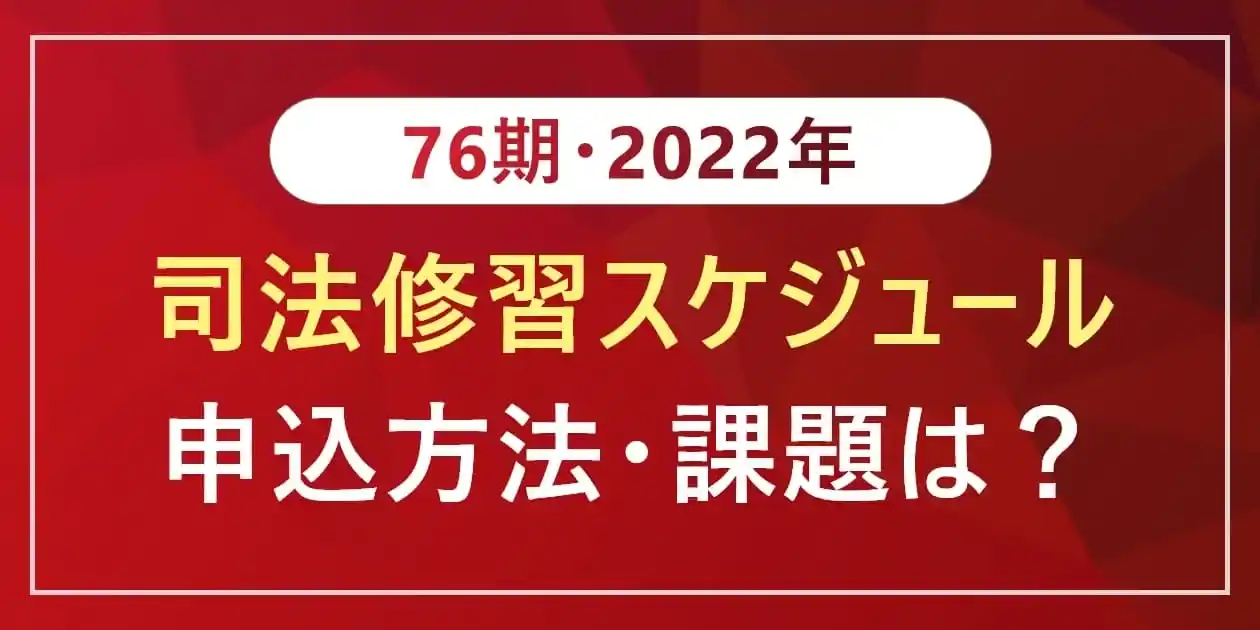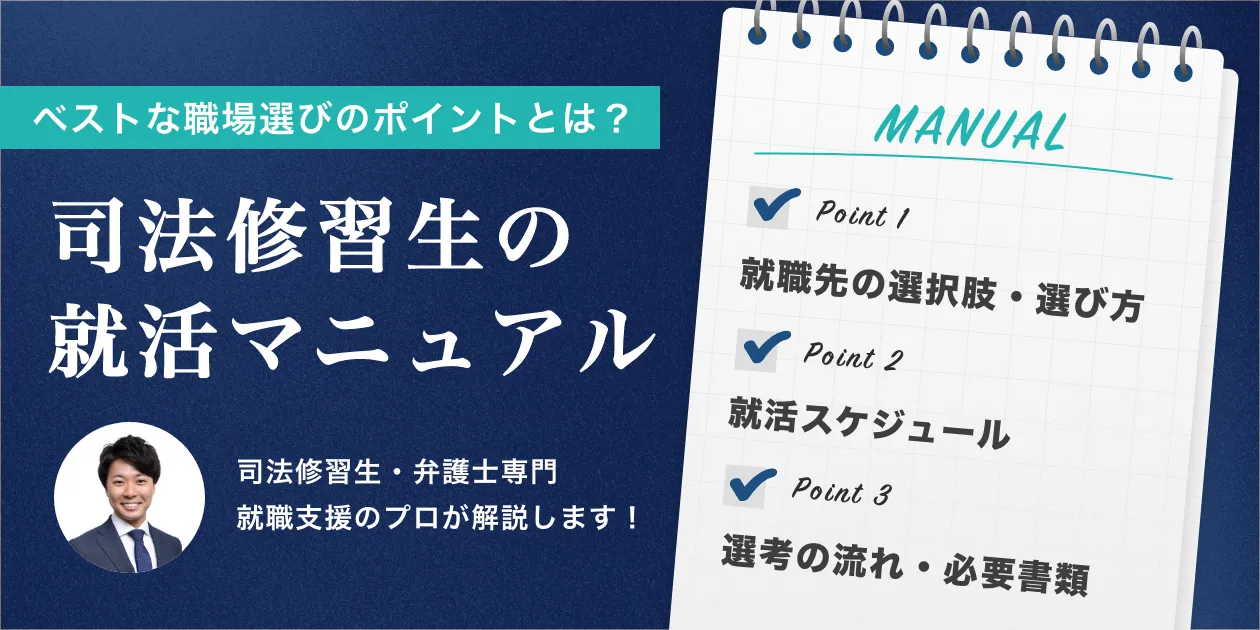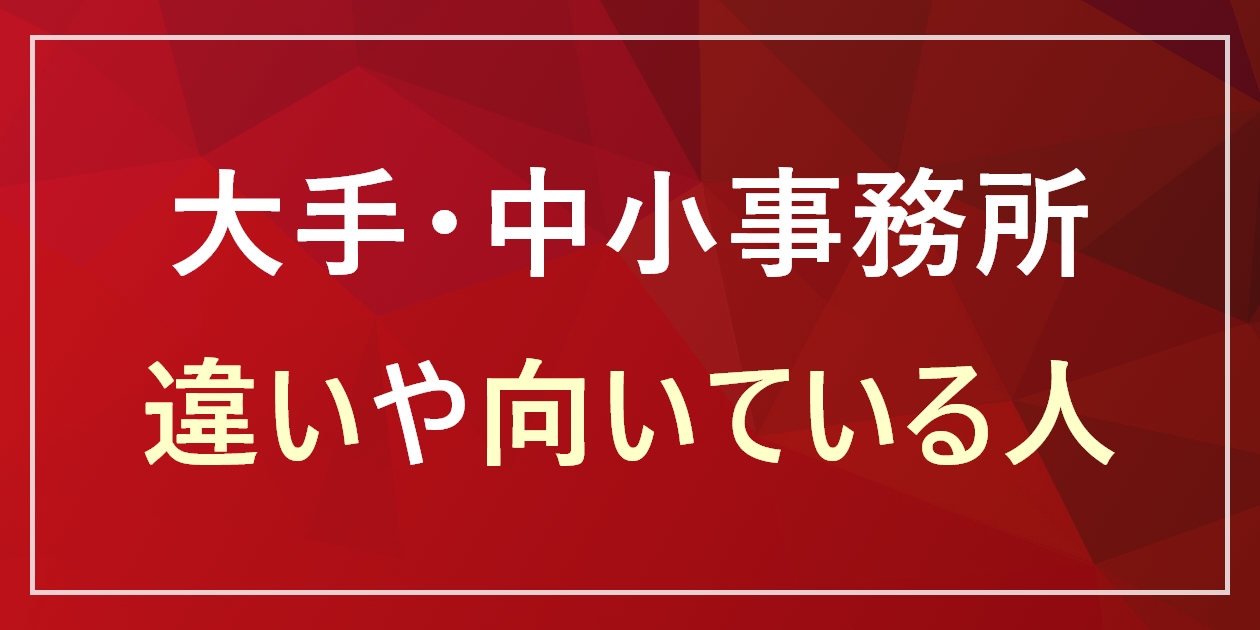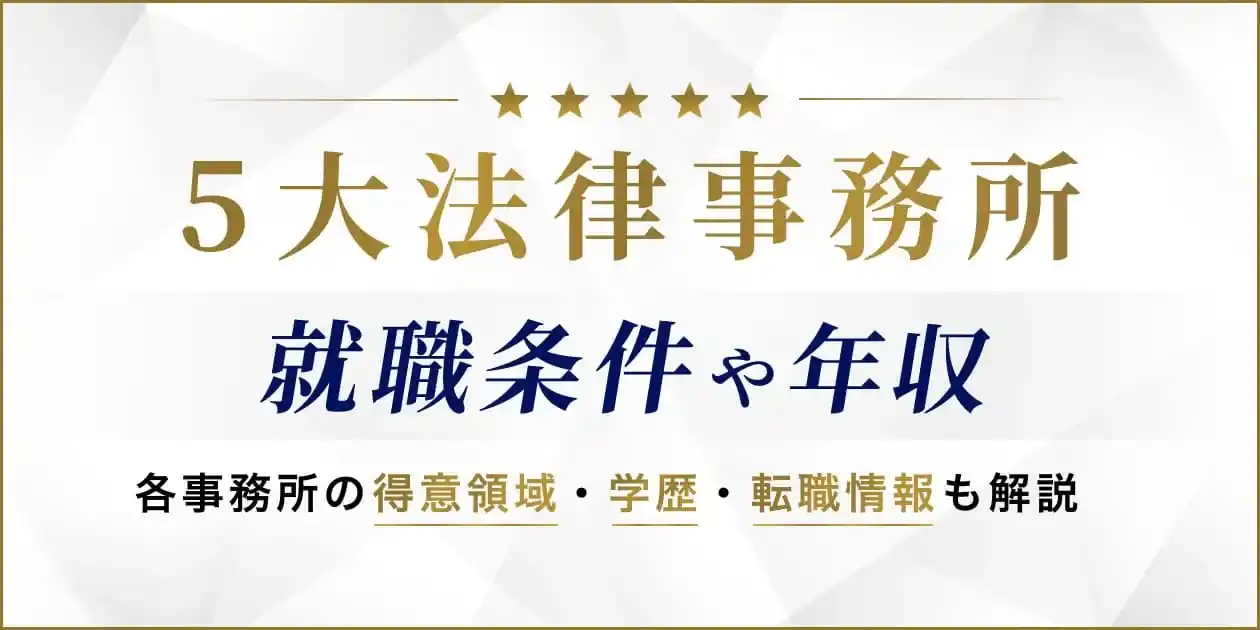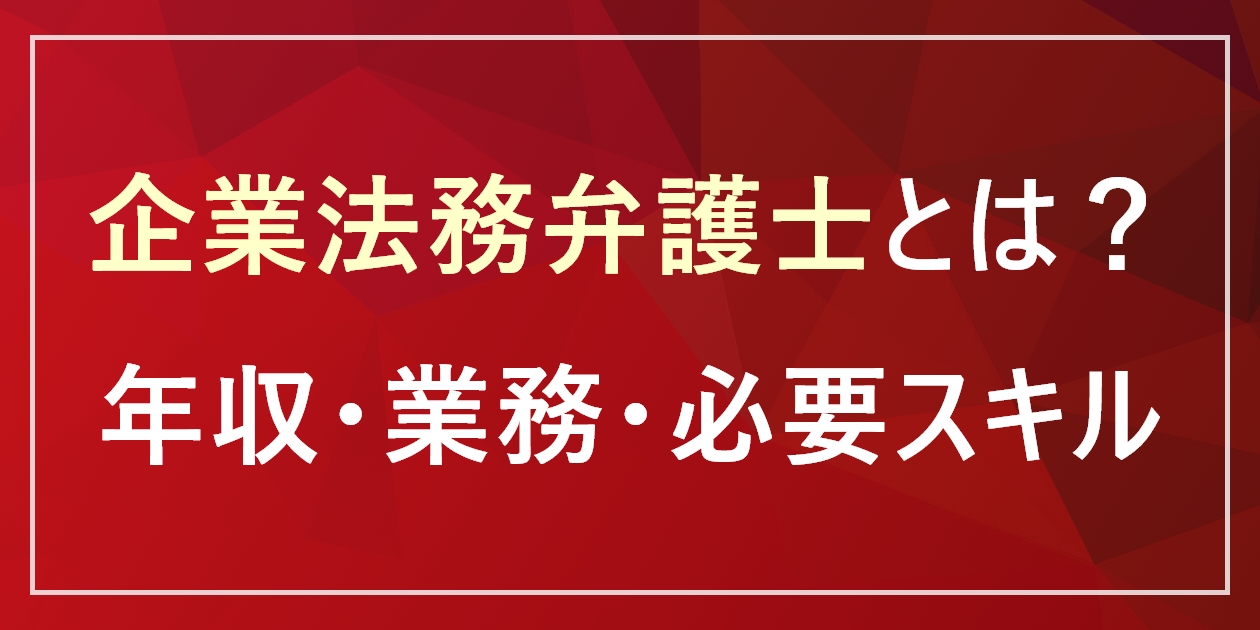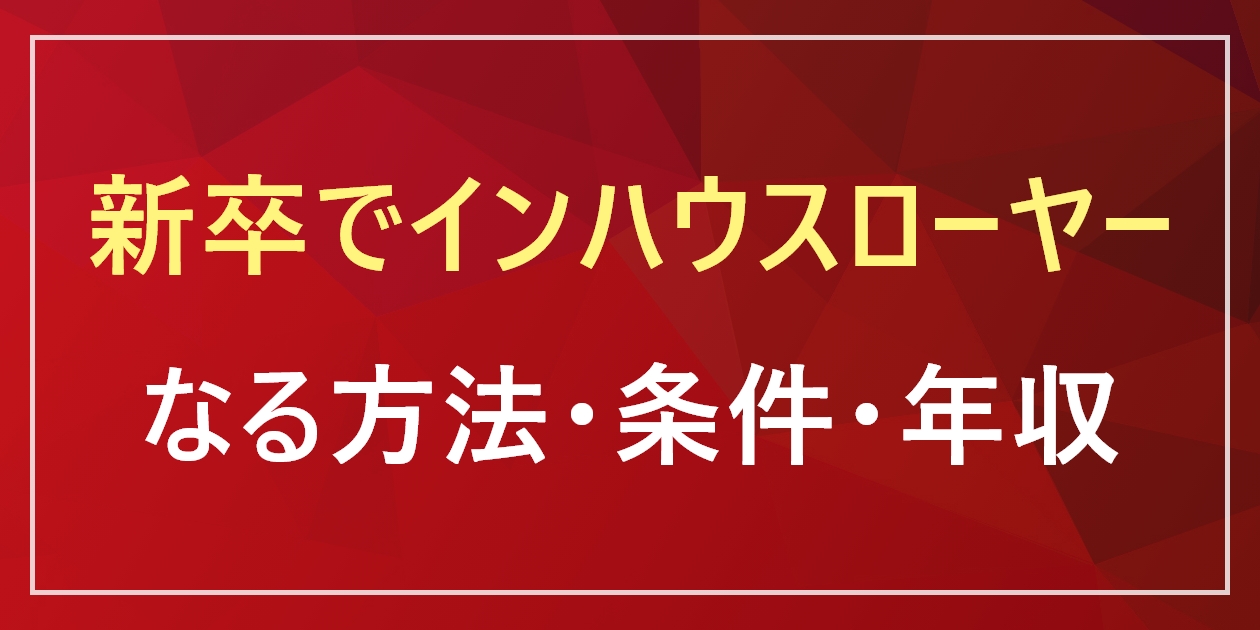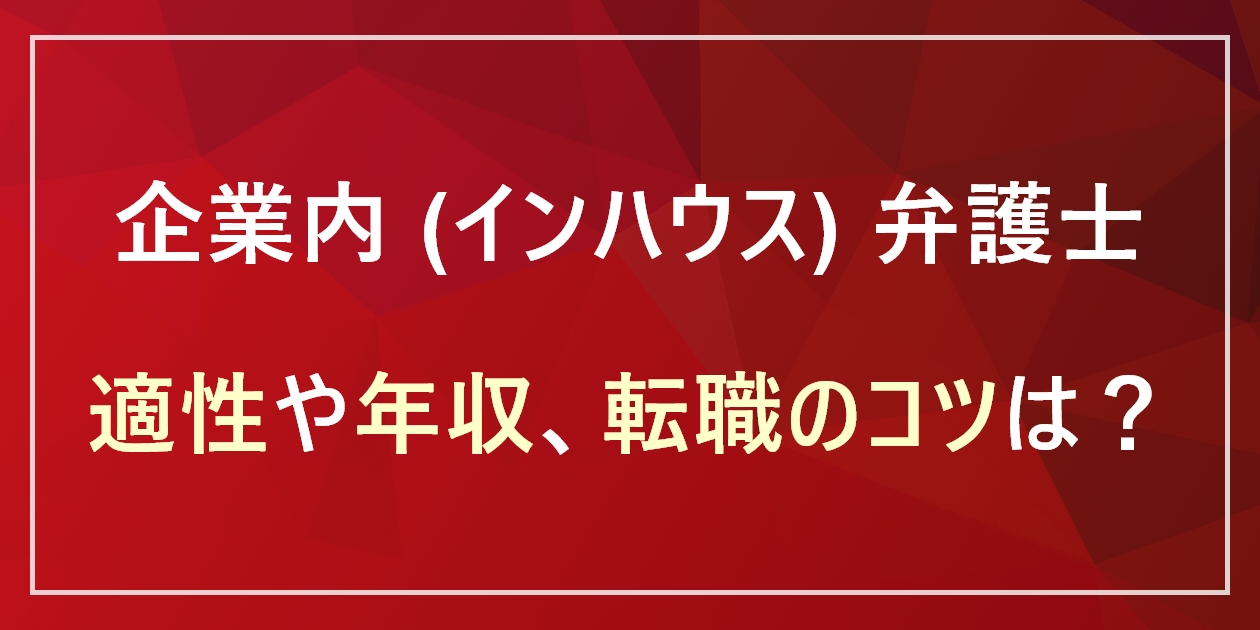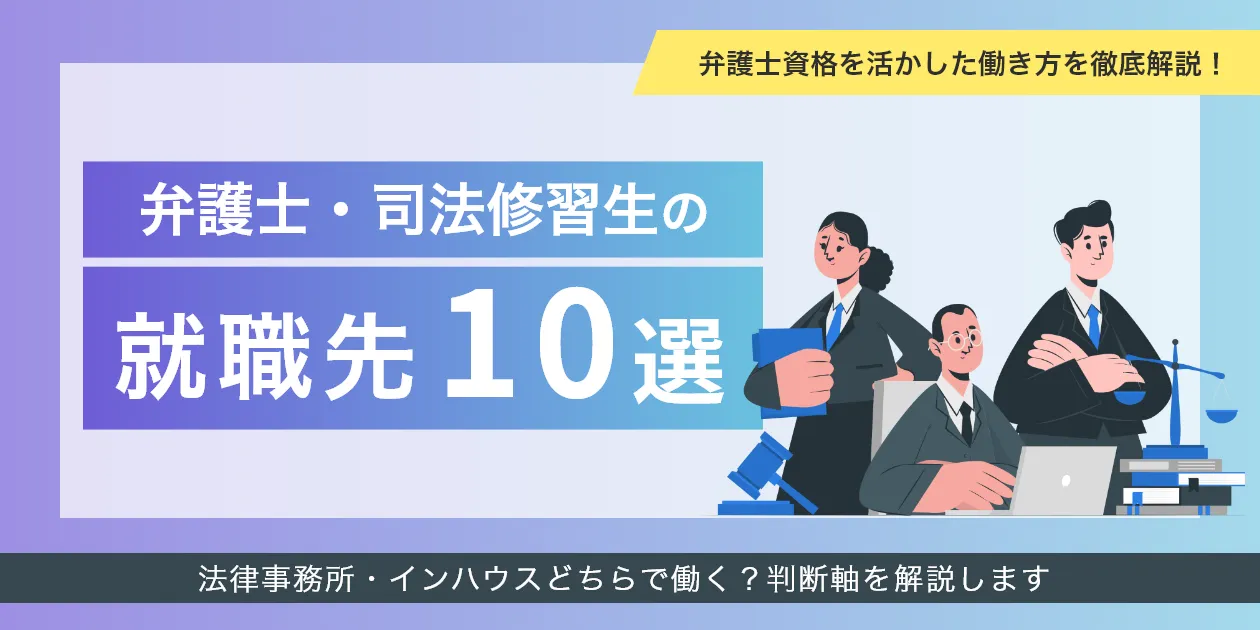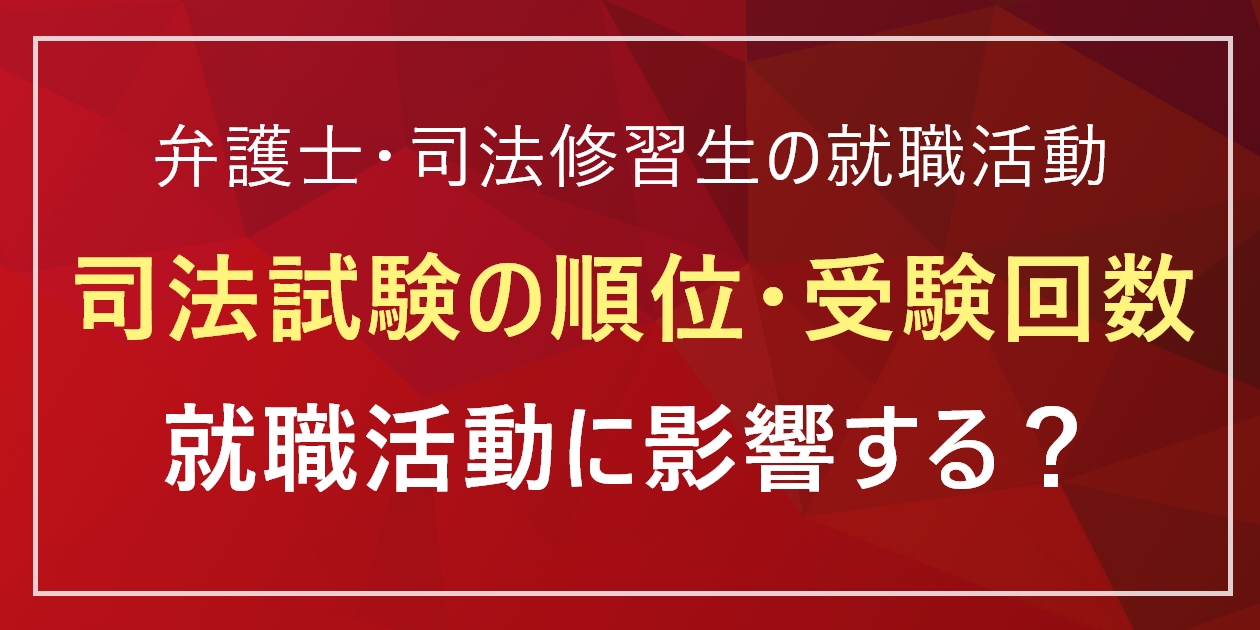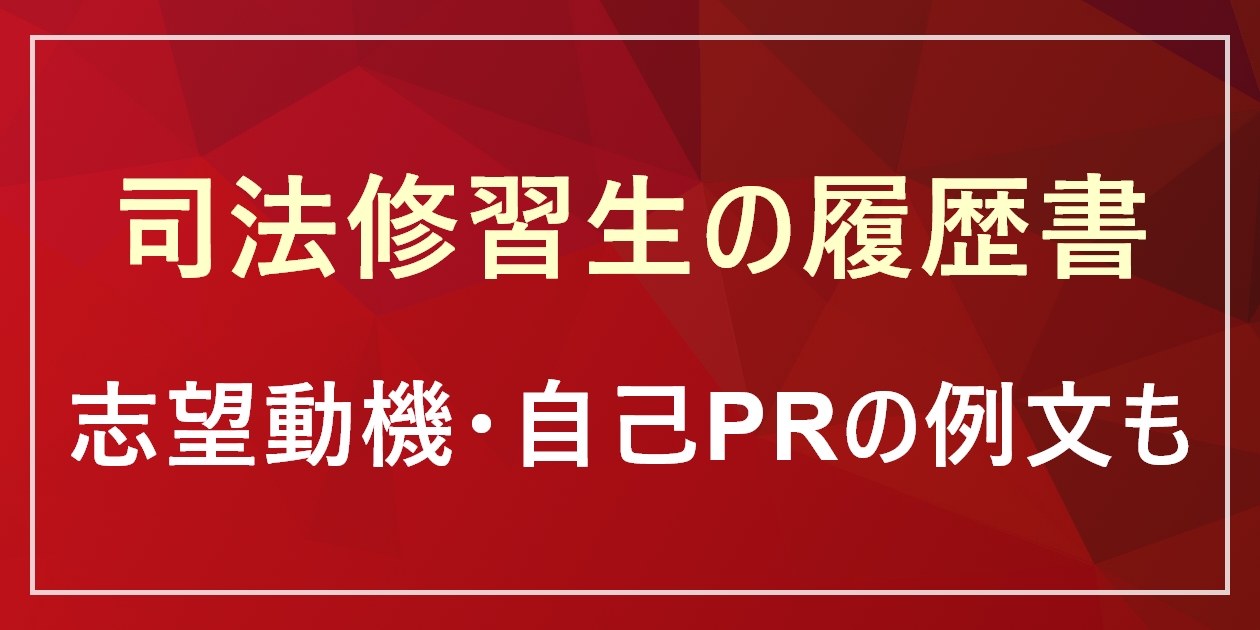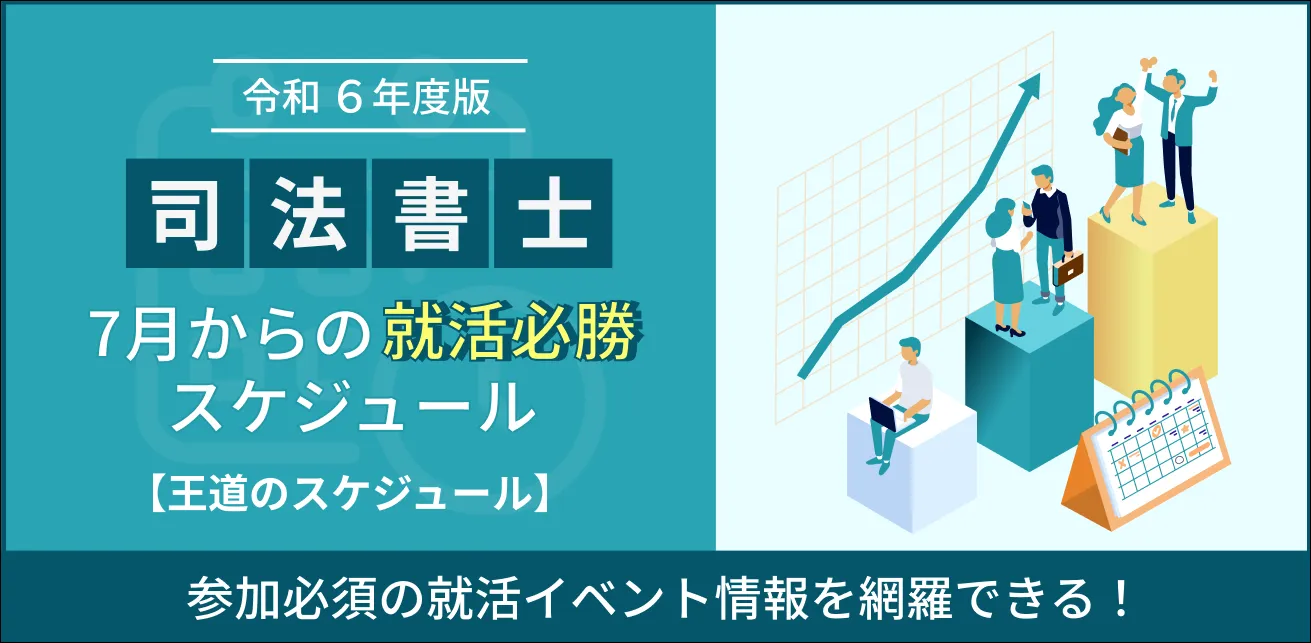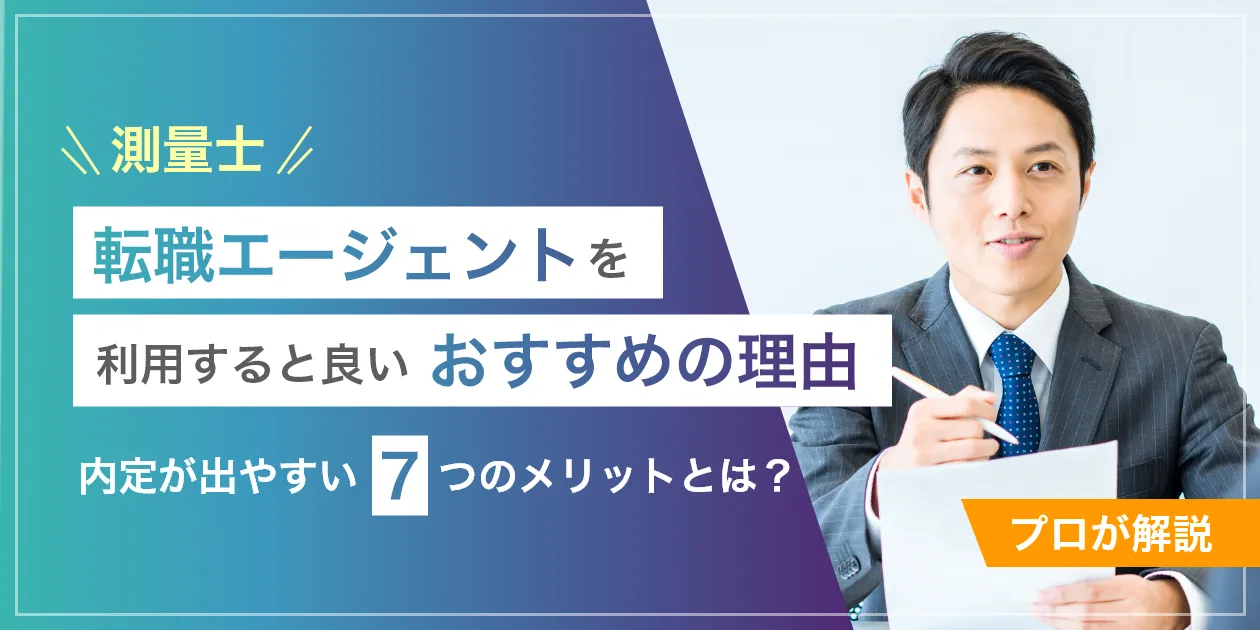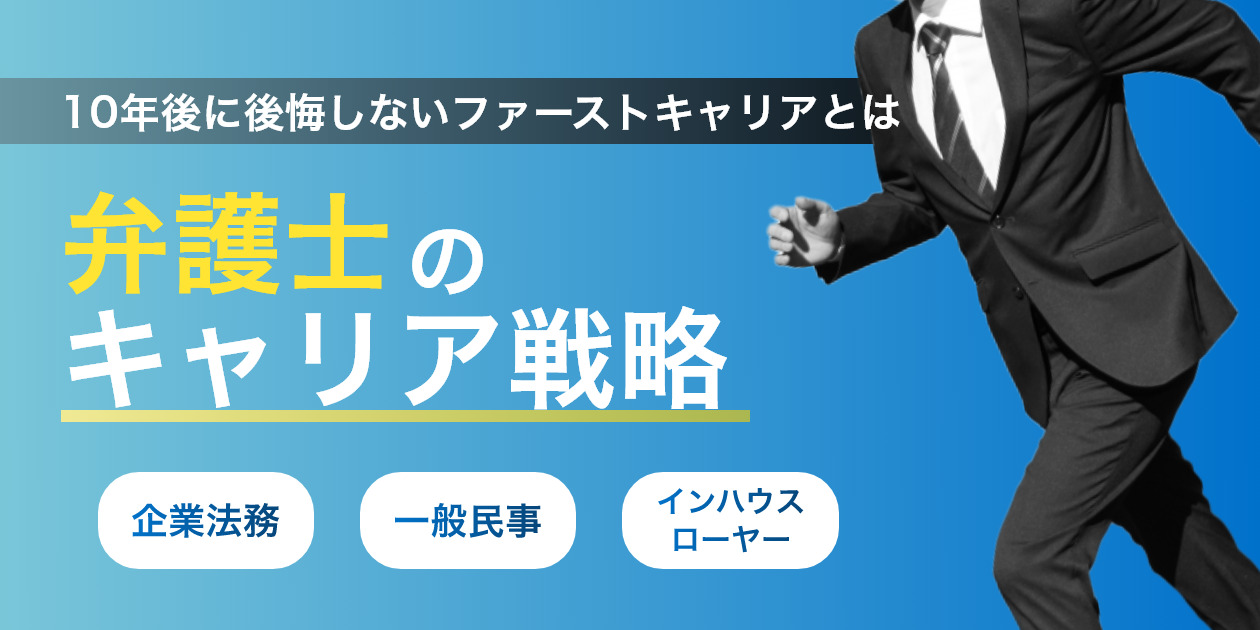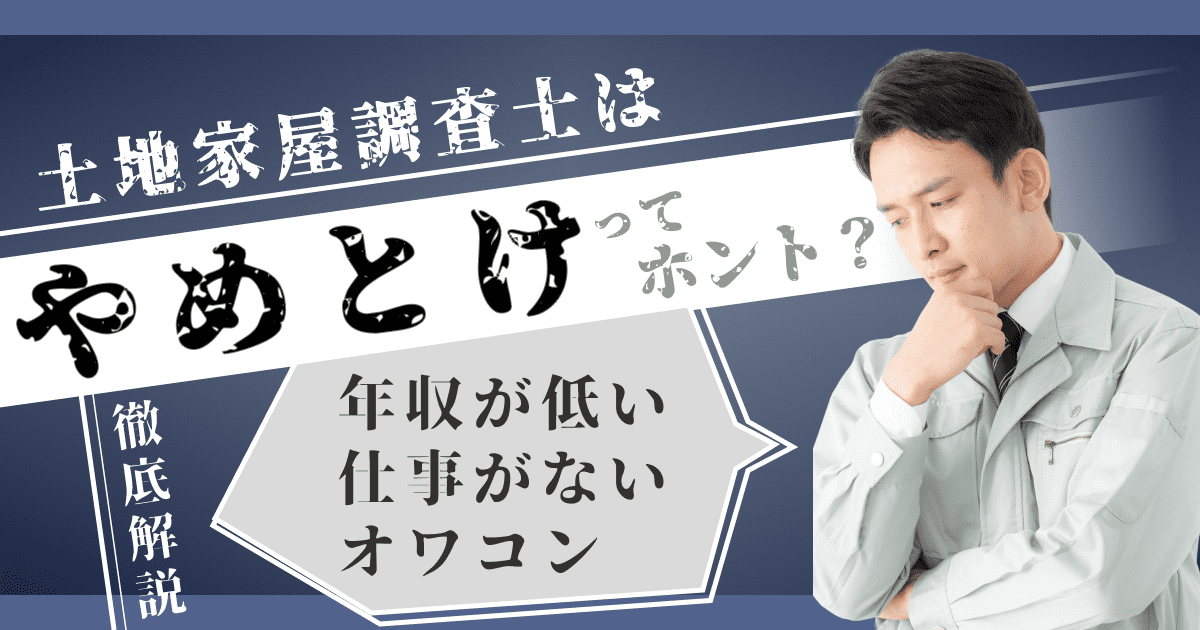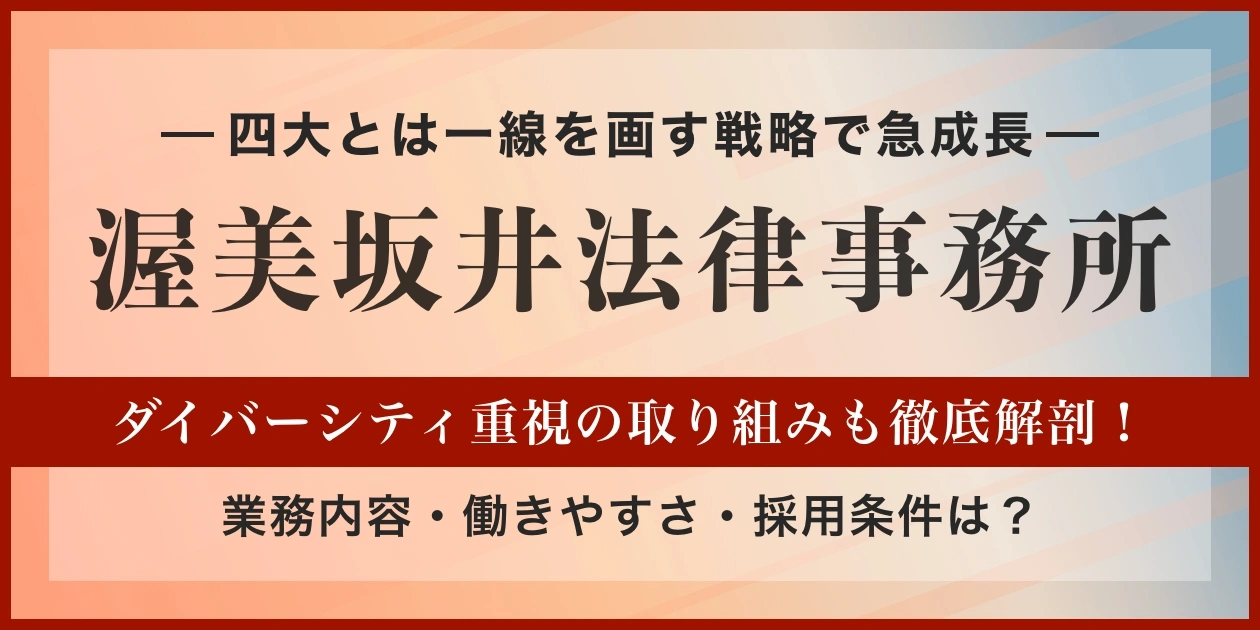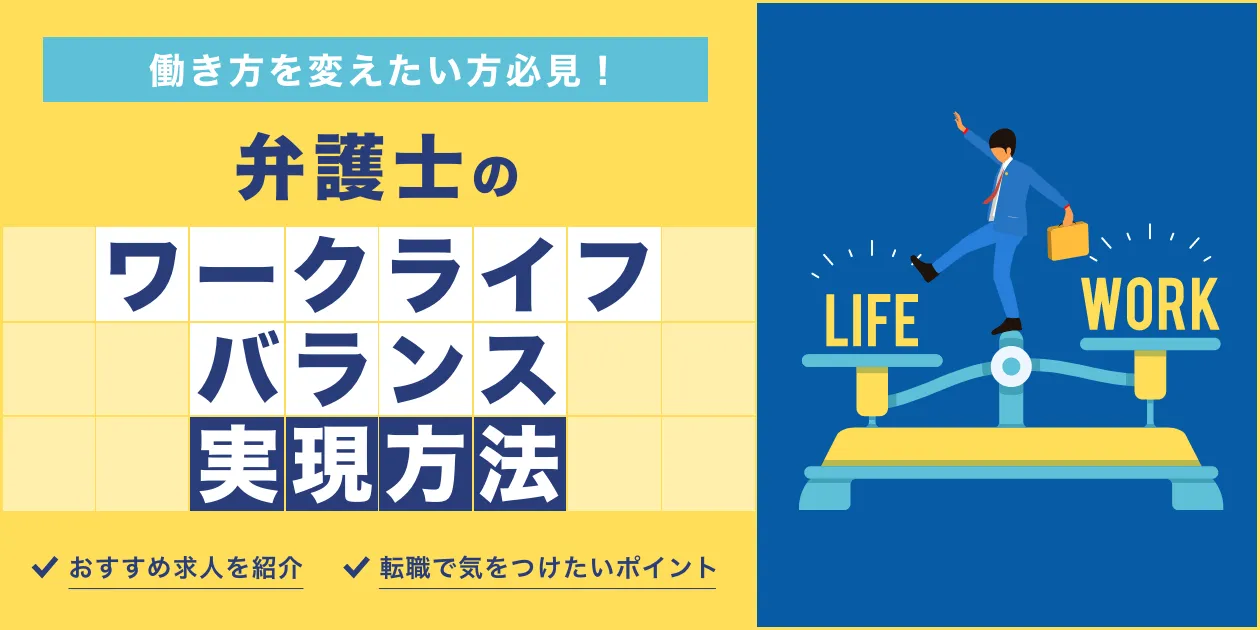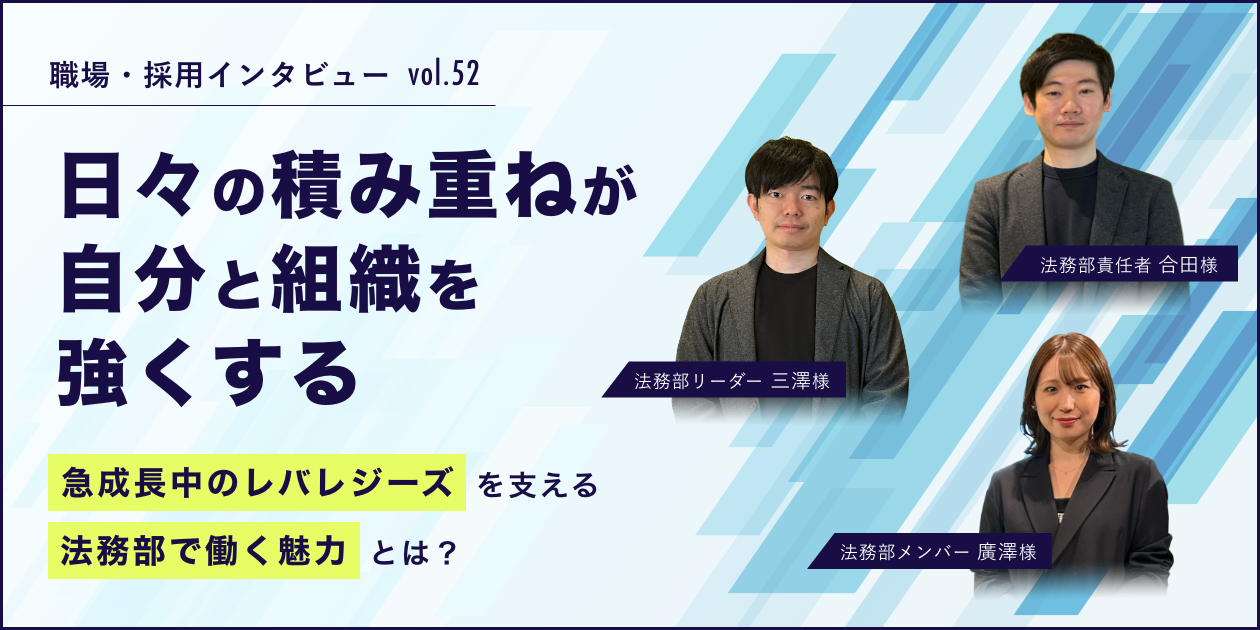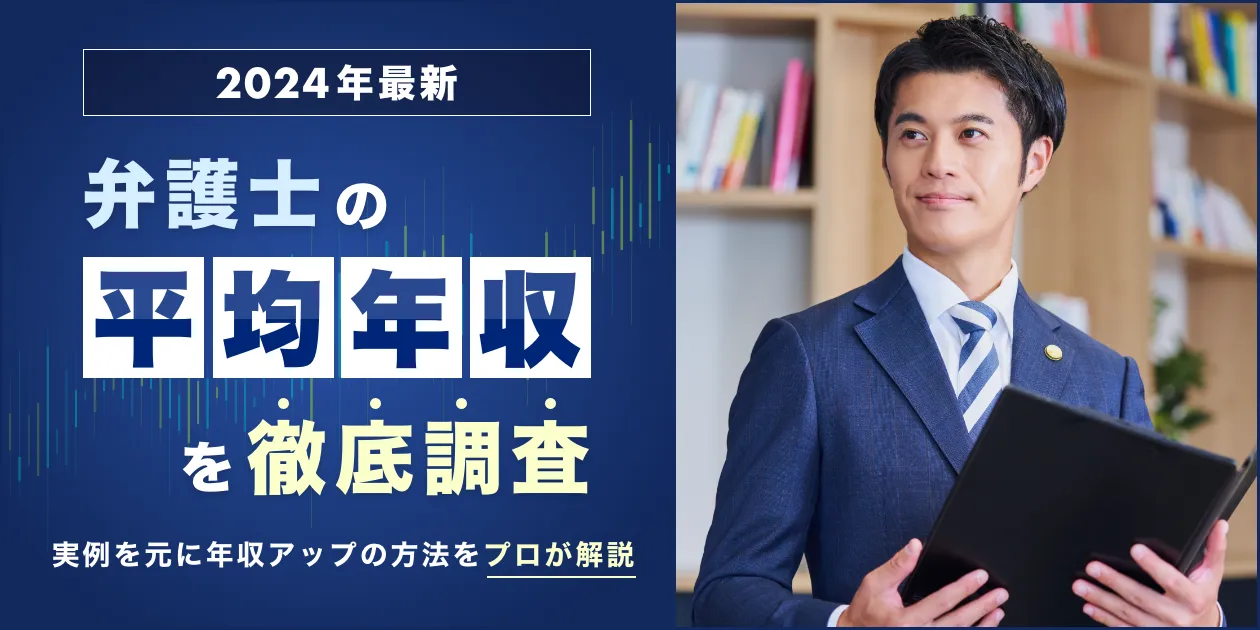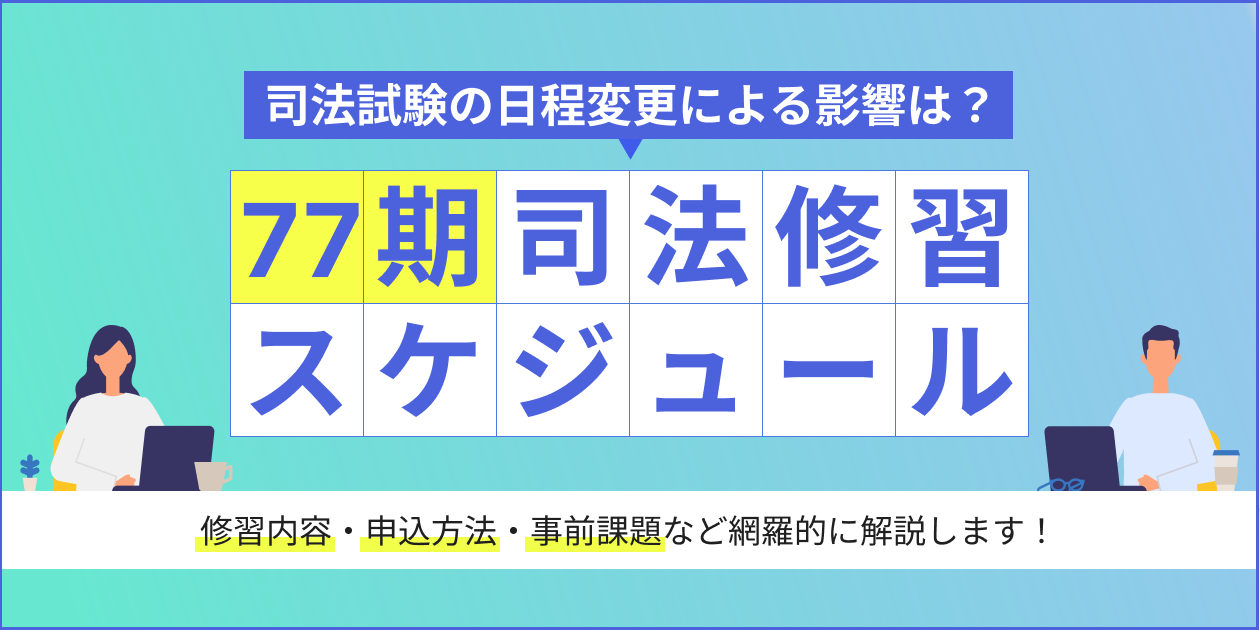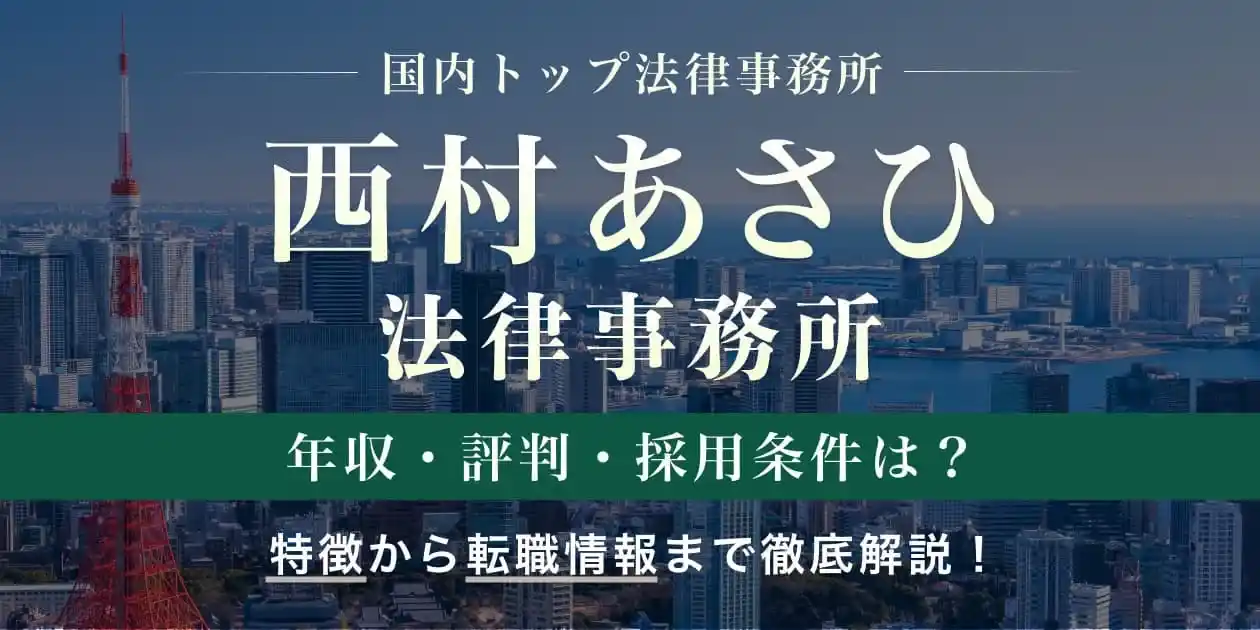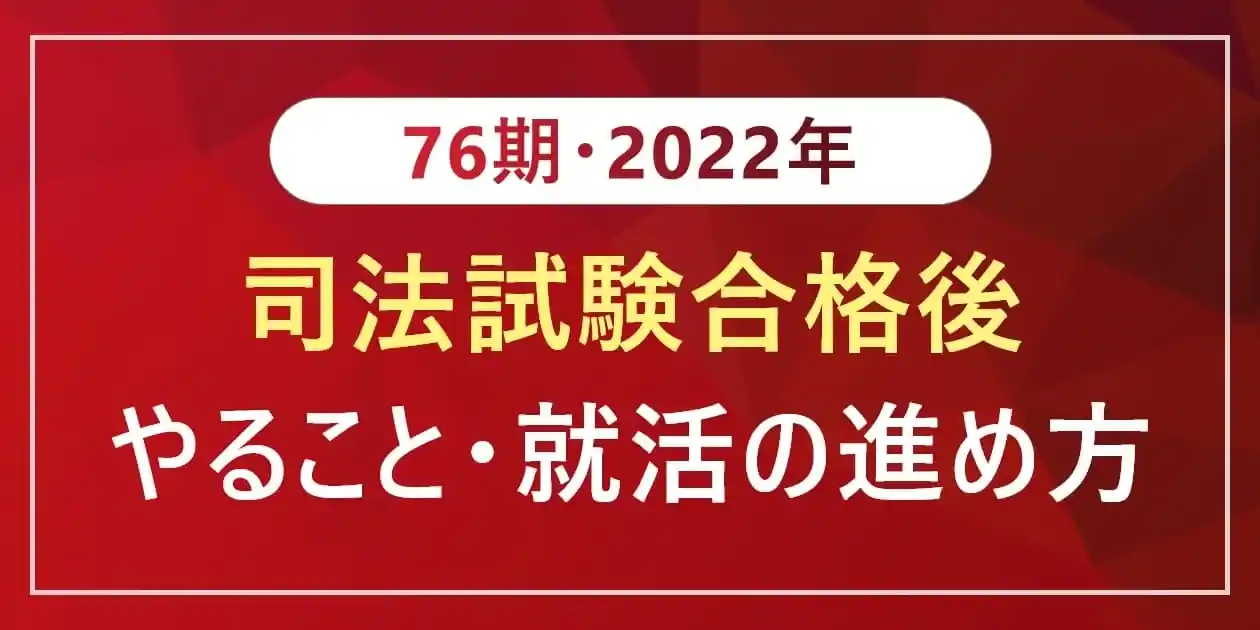
【76期|2022年】司法試験合格後のスケジュールや就職活動の進め方

by LEGAL JOB BOARD 増田
転職エージェント
- 担当職種:
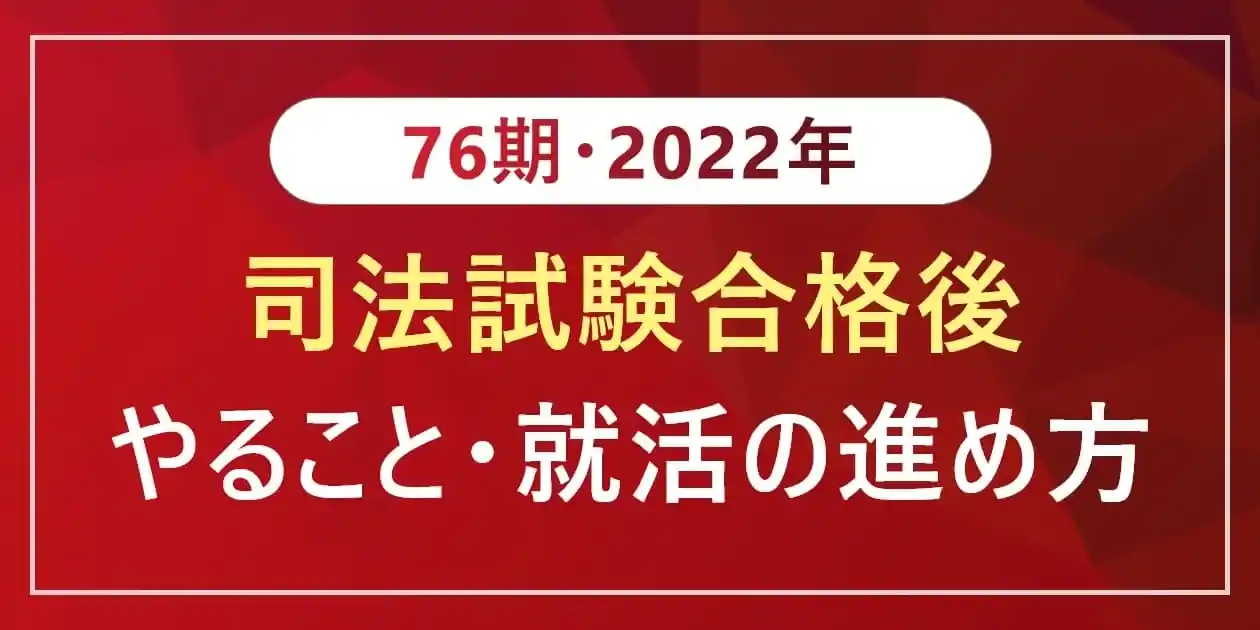
この記事の目次
2022年司法試験の合格発表日
2022年司法試験の合格発表は、9月6日(火)16時からです。
法務省ホームページにて、合格者の受験番号が発表されます。新型コロナウイルス感染症の影響で、法務省・各受験地での掲示は行われません。
合格後は、ほとんどの方が約1年間の司法修習を受け、法曹としての知識や考え方を学びながら身につけます。
司法修習を受けるには、司法修習生採用選考に申し込む必要があります。申し込み書類の提出期限は、2022年9月13日(火)です。合格発表から1週間しか時間がありませんので、早めに準備を進めておきましょう。
※参照:法務省「合格発表の日程等について」
司法試験合格後の動き方・やること
司法試験の合格後は、司法修習やその準備、就職活動などを並行して行います。
合格後、ほとんどの方は約1年にわたって司法修習を受けます。弁護士・検事・裁判官(判事補)となる資格を得るためには、修習の最後にある試験に合格しなくてはなりません。
司法修習の申し込み書類は、合格発表から1週間で提出する必要があり、まずは書類の準備から着手することになるでしょう。
修習関連ではその他に、事前課題が課されますので、11月末の修習開始までに取り組むことになります。
また、合格後には多くの方が就職活動を本格的にスタートします。修習中も合間を縫って、エージェントや求人サイトを活用しながら就職活動をしている方が多い印象です。
司法修習や就職活動について、このあと詳しく解説していきます。
司法修習の出願手続き
司法修習は、「法律実務に関する知識・スキルの習得」や「高い職業意識・倫理観を備えた法曹の育成」を目的に実施されています。
具体的には、
- 導入修習(約1ヶ月)
- 分野別実務修習(全4クール・約7ヶ月)
- 選択型実務修習(約1ヶ月)
- 集合修習(約1ヶ月)
があり、これらの修習を終えた後に「司法修習生考試(二回試験)」に合格することで、修了となります。
76期の司法修習は、2022年11月30日(水)~2023年11月14日(火)で、その後に考試が行われる予定です。
司法修習の申し込み書類の提出期限は、司法試験の合格発表から1週間後。申し込み方法や修習にかかる費用など、詳しく知りたい方はぜひ下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい記事はこちら
司法試験合格後の就職先や進路
司法試験合格後の進路は、大きく分けると以下の4つです。
- 法律事務所
- 企業内弁護士(インハウスローヤー)
- 裁判官(判事補)
- 検事
以前は弁護士として法律事務所で働くことが当たり前でしたが、時代の変化に伴い、司法試験合格者の就職先の選択は拡がっています。
近年では、企業内弁護士としての働き方も注目されており、少しずつ求人も増えています。
法律事務所
最も多くの司法試験合格者が選択する就職先は、法律事務所です。
法律事務所ごとの特色は、扱う案件のジャンルやその割合によって変化します。法律事務所勤務の弁護士は、長期的なキャリアを考える際に、どこでどんな経験を積むかが重要です
そのため、事務所選びで失敗することのないよう、ポイントを押さえておきましょう。事務所選びのポイントの詳細は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい記事はこちら
また、法律事務所は規模によって働き方や待遇が異なります。求められる人材も、事務所規模によって異なるケースが多いです。
大手と中小の違い、五大法律事務所の特徴、就職するのに必要なスキルなど、以下の記事でまとめています。ぜひ参考になさってください。
合わせて読みたい記事はこちら
合わせて読みたい記事はこちら
ちなみに、法律事務所に勤める弁護士の初年度年収は、
- 平均:550万円程度
- 五大・大手法律事務所(東京):1,000万円以上
- 中小規模の法律事務所(東京):700~800万円程度、300万円程度など様々
- 東京以外の都心の法律事務所:500~700万円程度
といった感じです。
五大・大手法律事務所に加え、「企業法務系の事務所」も初年度年収が高い傾向にあります。
五大法律事務所の就職難易度はかなり高いので、高年収を目指したい方は企業法務系の事務所も選択肢に入れてみてはいかがでしょう。
合わせて読みたい記事はこちら
企業内弁護士(インハウスローヤー)
司法試験合格者のなかには、企業内弁護士(インハウスローヤー)として、一般企業に入社する方もいます。
企業に所属するため、法律事務所と比べて「残業が少ない」「福利厚生などが整っている」などのメリットがあることが多いです。そのため、ワークライフバランスを重視する方に人気の就職先となっています。
企業内弁護士の求められる人材像は、「法務として法務関係に詳しい方を雇いたい」「弁護士資格を持つ方を企業所属の弁護士としておきたい」など、企業によって様々です。
法科大学院出身者や司法書士資格取得者など、ライバルとなり得る存在が比較的多く、倍率が高い可能性があります。
また、仕事の特性上、どうしても「経験者」を求める企業が多いです。とはいえ、未経験でも企業内弁護士を目指せます。企業内弁護士に興味をお持ちの方は、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい記事はこちら
合わせて読みたい記事はこちら
企業内弁護士の初年度年収は、400万円程度です。
全体の平均年収は500〜750万円程度で、役職に就くと年収1,000万円を越えるケースもあります。
弁護士資格を持つ方を重宝する企業であれば、司法修習後すぐの弁護士でも年収500~600万円程度を提示されることも。ただ、基本的には無資格の法務の方と同等の金額になると思って良いでしょう。
裁判官(判事補)
司法試験合格後、裁判官を目指すこともできます。
合格者のなかでも、特に優秀で人間性に優れた人材が選ばれるとされています。司法試験の成績に加え、司法修習中の成績・振る舞いも考慮されるようです。
そんな難関の裁判官ですが、初年度から年収500~600万円程度の高給与が目指せます。
裁判官のキャリアは、「未特例判事補」からスタート。この階級では単独で裁判が行えず、裁判長を務めることもできません。任官から5年が経つと「特例判事補」となり、単独で裁判を行えるようになります。10年目で「判事」になると、一人前の裁判官に。
その後は「高等裁判所長官」「最高裁判所判事」「最高裁判所長官」と、キャリアアップしていく可能性があります。しかし、「判事」以上のキャリアを積む人はほんの一握りです。
検事
弁護士、裁判官(判事補)以外に、検事になる道もあります。
検事を志望する場合、司法修習生考試(二回試験)に合格した後、採用面接を受けなくてはなりません。検事の採用は、能力・適性・人格・識見に優れた方を総合的に判断して行われます。検事に任官されるのは、例年65~75人前後です。
検事の初年度年収は、600万円前後と推定されます。検事の給与は20号~1号の階級に応じて、法律で定められています。現行の法律では、検事14号で月給30万円を超え、検事2号の月給は100万円以上です(2022年8月時点)。経験に応じて確実に給与があがる体系であり、昇給のペースも比較的早いように思われます。
検事のキャリアパスは以下の通りです。
- 新任検事(1年目)
- 新任明け検事(2~3年目)
- A庁検事(4~5年目)
- シニア検事
- 三席検事
- 次席検事
- 検事正
- 検事長
- 検事総長
新任検事、新任明け検事は力をつける期間とされ、5年目以降になると一人前として認められる存在になります。
※参照:法務省「検事に採用されるまで」
司法試験に合格するなど、法律の知識があれば他の職場でも活躍することができます。詳しくは下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい記事はこちら
就職活動を開始するタイミング
例年、司法試験受験生は、最終的な合否が分かる9月に就職活動を始めている印象です。
五大法律事務所を狙っている方、試験結果に自信のある方などは、短答式試験合格後の8月頃から就職活動をスタートし、早々に内定をもらうケースもあります。
ですが、急がないと内定をもらえないわけではありません。落ち着いて、余裕をもって就職活動を始めましょう。
就職活動の第一歩として、
- 論文式試験の合格後、合同説明会に参加する
- 司法修習時にエージェントや求人サイトを利用する
といったアクションがあります。
就職活動の成功には、情報収集が欠かせません。複数の説明会に参加する方が多いです。
また、エージェントを利用して、求人の動向や自分に合った事務所を教えてもらうのも良いでしょう。
本格的に就職活動を開始するにはまだ早いと感じている方も、求人サイトを活用した情報収集はしておくことをおすすめします。人気の求人は応募が集まりやすく、すぐに募集募集を締め切ってしまうケースがあるためです。
できる限り多くの方法で就職活動をしていくことが、自身に合う事務所へ就職するためのポイントです。
就職活動に向けて準備すべきもの
就職活動を進めるにあたり、いくつか準備すべきものがあります。
- 司法試験の成績通知書のコピー
- 大学・法科大学の成績表
- 履歴書・職務経歴書
以上の書類は、準備はしておいた方が良いでしょう。司法試験や大学・法科大学院の成績は、履歴書・職務経歴書と一緒に提出を求められるケースが多いです。
合わせて読みたい記事はこちら
また、履歴書・職務経歴書は、あなたの第一印象を決定づける大切な書類です。
面接官は現役弁護士ですので、志望理由と自己PRに説得力がないと、興味を持ってもらえないかもしれません。そのため、応募事務所ごとに内容を作り込むのがベターですが、いざ応募書類を作ろうとしても難しいという方が多いです。
そんな時は、弁護士専門エージェントの「リーガルジョブボード」にお気軽にご相談ください。履歴書・職務経歴書作成のレクチャーから添削、模擬面接など、就職活動をお手伝いをいたします。
合わせて読みたい記事はこちら
司法試験に不合格だった方の進路・就職
もし、司法試験に落ちてしまっても、法律の知識を学んだことは就職に役立ちます。
ロースクールを卒業していたり、短答式試験に受かっていれば、就職活動において評価される場面も多いです。
司法試験には、法科大学院修了または司法試験予備試験合格から「5年間で5回」と、受験回数に制限があります。受験回数の上限に達してしまった場合は、再度受験資格を得なければ、司法試験を受けることができません。
不合格だった場合、進路や就職の選択肢としては、
- 次回の司法試験合格を目指す
- 司法書士などの「同じ領域の違う職種」を目指す
- 法律の知識を活用できる「企業法務」を目指す
などがあるでしょう。
なかでも、特におすすめなのは「企業法務」としての就職です。
企業法務は、法律の知識が求められるため、司法試験のための勉強を活かすことができます。近年、企業法務の求人数は増加傾向にあり、注目されている職種です。
司法修習生こそエージェントを利用するのがおすすめ
司法試験の合格発表の前後で、新人弁護士を取りたい多くの法律事務所が求人を掲載します。
年間で最も求人数が増える時期ですが、誰でも希望する事務所から内定をもらえるわけではありません。
それは、人気の事務所には応募が殺到することが原因の一つ。希望する事務所に就職するための第一歩は、書類選考に通過することです。
「リーガルジョブボード」のようなエージェントを利用すると、書類選考に通過しやすくなるのをご存じですか?
理由は下記の3つです。
- 履歴書・職務経歴書をブラッシュアップできるため
- 「求職者様の推薦文」を一緒に提出できるため
- 他の書類に埋もれないよう配慮して事務所に提出するため
人気の事務所には多くの応募書類が届くため、大量の書類に埋もれてしまい、履歴書・職務経歴書を流し見されてしまうケースが多いです。
エージェントを介して応募する場合、送付後に電話等の確認連絡を行い、しっかりと書類を確認してもらうよう配慮します。そのため、「流し見されて書類選考に引っかからなかった」といったことを極力減らすことができます。
エージェントを利用するメリット
書類選考に通過しやすくなる以外にも、エージェントを利用するメリットとして、
- 複数の選考を効率よく進められる
- 業界知識や裏事情を把握しながら就職活動ができる
- 給料や入社時期などの交渉が可能
- 入社後のミスマッチを防げる
などがあります。詳しくは、下記の記事をぜひご覧ください。
合わせて読みたい記事はこちら
法律事務所や企業法務への就職をお考えの方、自分に合った求人が知りたい方は、弁護士専門エージェント「リーガルジョブボード」にお気軽にご相談ください。