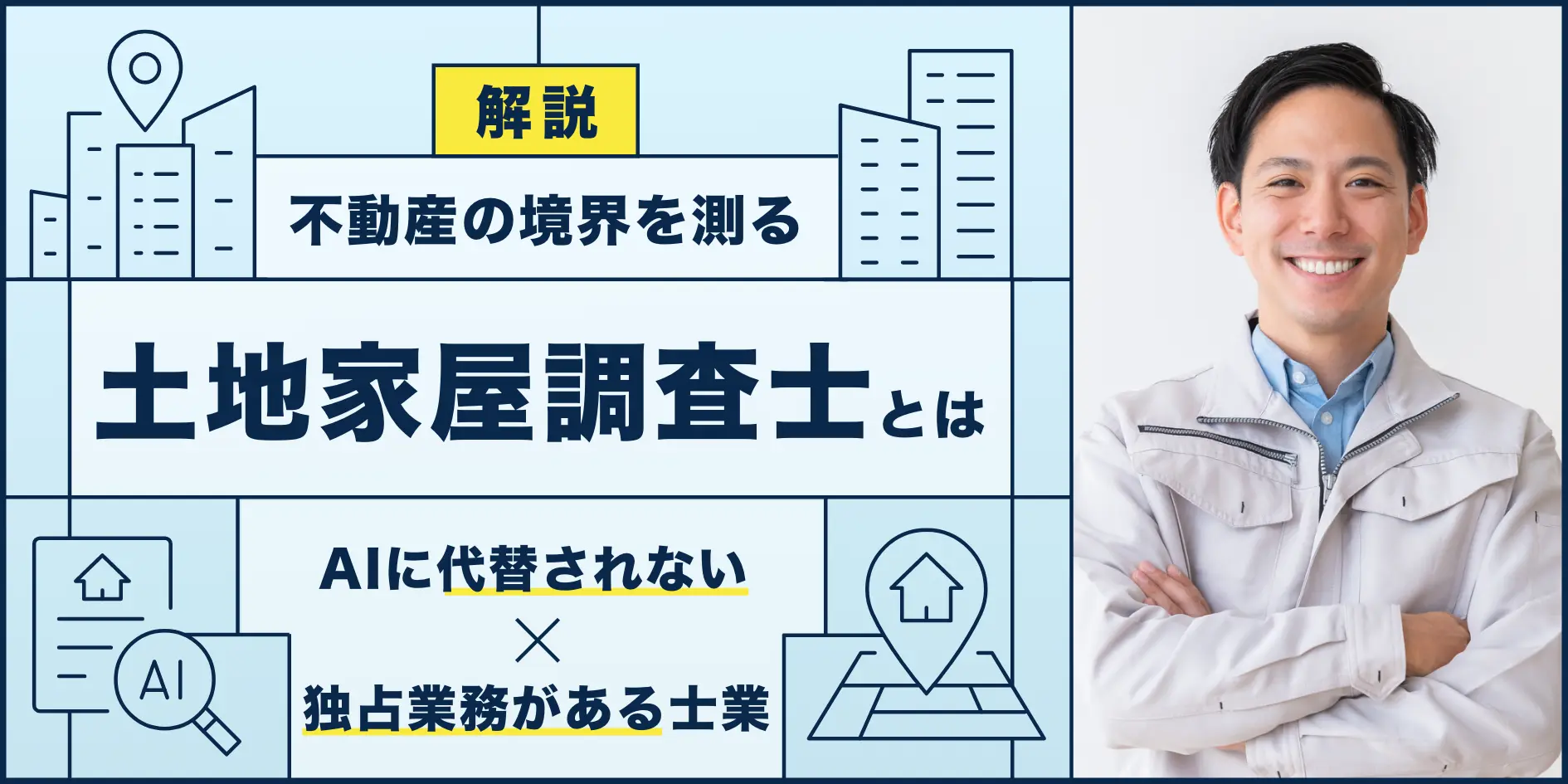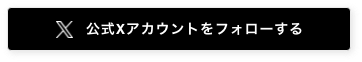【土地家屋調査士】試験の難易度や働きながら取得する方法

by LEGAL JOB BOARD 篠原
転職エージェント
- 担当職種:

こんにちは。土地家屋調査士の転職エージェント「リーガルジョブボード」の篠原です。
今回は、「調査士試験の難易度や働きながらの取得方法」について解説します。
土地家屋調査士の試験の合格率・合格者の平均年齢や、試験に合格するために大切なポイントについてもご紹介しています。
また、「働きながら調査士の資格を取得する方法」についても触れているので、本業を行いながら資格取得を目指している方は必見の内容です。
この記事の目次
調査士試験の概要
土地家屋調査士試験は、毎年10月に行われる筆記試験と、翌年1月に行われる口述試験で構成されています。
筆記試験は相対評価となっており、上位の約400名程度が合格となります。
筆記試験の合格者のみが翌年の口述試験に進むことができ、口述試験も通過すれば土地家屋調査士となる資格を得ることができます。
今回は土地家屋調査士の試験の概要や、働きながら取得することについて解説していきましょう。
受験資格・免除制度
土地家屋調査士試験は、受験資格の制限がなく、どなたでも受験することが可能です。
筆記試験は、午前の部と午後の部に分かれています。
また、以下に該当する方は午前の部の試験を免除できます。
- 前年度に行われた土地家屋調査士試験で筆記試験を合格した者
- 測量士・測量士補・一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者
- 午前の部の試験合格した者同等以上の知識及び技能を有する者として法務大臣が認定した者
免除には事前申請をする必要があるため、要項を確認し、忘れずに申請を行ってください。
試験科目
続いて、筆記試験と口述試験の出題内容です。まずは「筆記試験」の試験内容から。
筆記試験の試験内容
不動産の表示に関する登記につき、必要と認められる事項であって次に掲げるもの。
(1)民法に関する知識
(2)登記の申請手続、及び審査請求の手続に関する知識
(3)土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって、次に掲げる事項
ア. 平面測量
イ. 作図
(4)その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
午前の筆記試験では(3)が問われ、択一式問題が10問で10点満点、記述式問題が1問で40点満点。
午後は(1)、(2)及び(4)の範囲で、択一式問題が20問で50点満点、記述式問題が2問で50点満点。
それぞれ基準点があるため、どちらかが満点でも片方が基準を満たしていないと合格できません。
免除されてる方以外は、満遍なく勉強をする方がいいでしょう。
令和2年度 新型コロナウイルス対応について
新型コロナウイルスの感染対策として検温などがあるため、コロナウイルスが流行っている状況では、早めに会場へ向かうことをオススメします。
また、試験中のマスク着用の義務、フェイスシールドや手袋の着用、ウェットティッシュの使用がOKになるなど、今までとは違った会場の雰囲気となるでしょう。
また、コロナの影響により、以下に該当する方は受験できないため気をつけてください。
- 37.5度以上の発熱が確認された方
- 新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方
- 濃厚接触者として健康観察の指示を受けている方
- 新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる体調異常(せき, くしゃみ,呼吸困難,息切れ,強いだるさ)がある方
- 海外からの帰国者等,政府又は自治体の要請により自宅待機を求められている方
※受験しなかった場合の追試験や受験手数料返還等の特別措置は予定していないようなので、ご注意ください。
また会場内は随時換気を行うため、服装には注意した方がいいでしょう。
▼引用元
法務省「令和2年度土地家屋調査士試験における新型コロナウイルス感染症への対応について」
調査士試験の難易度
続いて、土地家屋調査士の試験の難易度についてです。
試験の合格率は例年8~9%の間で推移していますが、近年は受験者数の減少に伴ってやや合格率が上昇傾向にあります。
令和元年度の試験では9.68%でした。
筆記試験のうち「午前の部」につきましては、測量士・測量士補・一級建築士・二級建築士のいずれかの試験に合格していれば免除されることになっています。
そのため、ほとんどの受験生は、毎年5月に行われる測量士補試験に合格して免除を受けます。
また、口述試験はほぼ受験者全員が合格するので、難易度と呼べるようなものはありません。
調査士試験に関するその他の補足事項
これまで、試験の概要や難易度についてご紹介しました。その他の情報についても補足しておきます。
受験者数
平成24年に受験者数が5000人を切ってからは,ほぼ横ばいで推移しており,4500-4700人程度の受験者数となっています。
合格者数も約400名、合格率も9%程度で推移しており、難易度も横ばい状態といえるでしょう。
合格者の平均年齢
合格者の平均年齢は40歳です。
毎年この年齢に変化はありません。
受験者の半数以上はご高齢の受験生ですので、20代〜40代前半の比較的まとまった勉強時間を確保することのできる受験生には有利な試験だと言えます。
難しいと言われている試験のポイント
「調査士試験の難所」とも言われているいくつかのポイントをまとめます。以下のような点が、調査士試験の難易度を上げていると言えます。
①細かい計算や作図
調査士試験を受験する方は文系の大学出身の方が多いです。
そのため大多数の方は計算で時間を取られるでしょう。
問題自体の難易度はそこまでハイレベルではありませんが、苦手意識を持つ方にとっては難所だと言えます。
ここで時間を使いすぎてしまうと、図面作成で十分に力を発揮できません。
ズレや記入漏れがあると減点対象となるため、確認までの時間を残しておきたいところです。
②時間がとにかく短い
- 午前の部→2時間(択一式問題が10問で10点満点、記述式問題が1問で40点満点)
- 午後の部→2時間半(択一式問題が20問で50点満点、記述式問題が2問で50点満点)
午前の部に関しては時間に余裕があるように感じますが、午後の部は30分しか変わらないにもかかわらず、問題数は倍です。
出題されるボリュームを考えるとかなり短い試験時間となります。
対策としては、試験時間を2時間半と考えるのではなく「2時間15分」に設定した上で過去問を解くように訓練を積むことです。
③勉強時間の確保
土地家屋調査士は補助者の受験が多く、働きながら勉強して取得しようと考える人が多いです。
しかし、『とりあえず実務経験を積みたいから補助者をしながら、空いている時間に勉強して取得しよう』と「気楽に」考えてしまうと、取得は難しいのです。
対策しなければいけないことは多くあるため、実は勉強時間の捻出が、働きながらだととても大変です。もし取得を真剣に考えている場合は、計画的に勉強することが大切です。
体力的にも、記憶力の面でも、早めに決断し計画を立てた方がオススメです。
これらを踏まえた上で、働きながらの取得は可能かということについて言及していきます。
働きながら土地家屋調査士になることは可能か
働きながら土地家屋調査士の資格を取得することは、可能です。
ただ、決して簡単ではないので、これからお話することをしっかりと踏まえることが大切です。
まず、働きながら取得する際に重要なことは「計画性」です。
「とりあえず空いている時間に勉強しつつ、ある程度できるようになったら受験しよう」というような中途半端な気持ちですと、合格は難しいです。
事務所で測量士補として働きながら資格取得を目指す方の多くが、実際は残業などで勉強に時間を裂けないという話を多く聞きます。
そして合格までずるずると時間がかかってしまったり、取得自体を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
本当に調査士として働きたいのかという意思を確認して、計画的に勉強の予定を立てれば必ず受かるはずです。
働きながら資格取得を成功させるポイント
働きながら資格を取得するには、以下の点を踏まえることです。
- 「○年までに取得する」という具体的な目標を掲げる
- 勉強時間は3年間を目安に考える
- ワークライフバランスの取れた事務所に転職する
これら3点を踏まえることです。
2点目についてですが、あまり勉強期間が長すぎると最初の方に勉強したことを忘れてしまうため、3年くらいがちょうどいいです。
以上を目安に取得の時期を逆算して、勉強の計画を立てましょう。
実情は、早い方だと1~2年で取得されていますが、5年以上かかる方も多いです。
残業が多い職場では、働きながら資格取得は難しい
また上の3点目の「ワークライフバランスの取れた事務所に転職する」のように、働きながら資格取得するには「残業が少ない職場」に就くことが非常に大切です。
もしハードワークである場合は、パート勤務が可能な職場や、残業が少ない職場への転職を推奨します。
ちなみに、リーガルジョブボードでは「働きながら資格取得を目指しやすい調査士事務所の求人」をご紹介しています。
《土地家屋調査士の試験勉強と両立しやすい求人を紹介してもらう(無料)》
こういった求人は人気であり、かつ数も限られているため、ネットで検索してもなかなか見つけられません。見つけられたとしても、すぐに埋まってしまう場合もあります。
そこで、弊社リーガルジョブボードにご登録いただくと、働きながら資格取得が目指しやすい求人が出たタイミングでお声がけさせていただきます。
登録時、担当のエージェントに現状や今後の予定、要望をお話することで、ご希望の求人を定期的に紹介してもらえるようになります。ぜひお気軽にご相談ください。
働きながら調査士の資格を取得できた合格体験記
ここからは、実際に働きながら取得された方の合格体験談や例をご紹介します。
【体験談①】実務経験を積みながら資格取得に成功した例(29歳男性)
補助者として一般の調査士事務所で働き始めました。
その次の年くらいから調査士試験を受験しようと決め、勉強をし始めました。
しかし初めのうちは仕事に慣れることに精一杯で、少ない休みの時間をなかなか勉強に費やせず、ずるずると時間だけ経過していきました。
数年後、仕事も慣れてきたため、このままではいけないと思い真剣に勉強を始めることに。
結果的に取得までかかった期間は約5年間と長めですが、その分実務経験を積めたため、調査士になってから就職する際とても有利だった覚えがあります。
実務経験を積むことと試験勉強の両立は難しいですが、自分自身の糧となります。
そしてその頑張りは後に、報酬や役職となって自分に帰ってくるので頑張って良かったと思います。
【体験談②】転職先の選択を工夫して最短合格(39歳男性)
私は勉強時間を確保したかったため、残業がない事務所を中心に求人検索していました。転職先となった事務所では、残業無しで休みもあり、十分な勉強時間を作ることができました。
またこの事務所は資格取得に大変理解のある職場だったため、試験直前になると長い休みをいただけたんです。
その甲斐もあってか、勉強を開始して1年で最短合格をすることができました。
私から言えることは、取得まであまり時間をかけたくない方は私のように残業のない事務所を選ぶか、一定期間の勉強する期間を設けるか、どちらかだと思います。
年齢が上がってくると、覚えることには時間がかかるのに忘れるのは一瞬。
早いうちに取り掛かった方がいいとアドバイスさせてください。
働きながらの取得は推奨しています
- 実務経験を積みながら、隙間時間で勉強
- 残業のない事務所を選び、短期間で取得
悩んだらとりあえず実務経験を積むというのは一つの手です。
実務を積むと就職の時に有利になります。
勉強だけだと想像しづらい事柄も、実務と並行しながら勉強すると「こういう登記はこういう場面で必要なんだ」と実践的に内容を理解できる利点もあります。
今一度なぜ自分が調査士を目指したいのか考えてみてください。
長期的に見て調査士になりたいのか、早めに取得した方が良いのかによって選択が変わってくると思います。
働きながら合格を目指す方を歓迎する補助者の求人の紹介
前述したように、働きながら合格を目指すなら「実務経験を積みながら勉強する」方が有利です。
そのため、勉強に専念するために転職する場合は「土地家屋調査士補助者として勤務しながら資格勉強がしやすい事務所」「資格取得の勉強に理解のある事務所」が良いと言えるでしょう。
リーガルジョブボードでは、そのような求人もご紹介しています。ご登録いただき、
- 働きながら資格取得したいこと
- ワークライフバランスの取れた事務所を探していること
をお話いただければ、そのような求人が出たタイミングでお声がけさせていただきます。
もちろん、現在掲載されている中にもワークライフバランスの取れた求人はございますので、お気軽にご連絡ください。
まとめ
働きながら資格取得するには計画性が大事です。
自分を律する力だけでなく、事務所の方の協力が助けになることもあります。
短期間で合格したい方は、
→転職をする際に残業のない事務所を選ぶ
→今の事務所の方に協力してもらう
こういった工夫が必要になります。
弊社リーガルジョブボードでは、求人のご紹介やキャリアプランのご相談なども承っているので、お気軽にご連絡くださいませ。


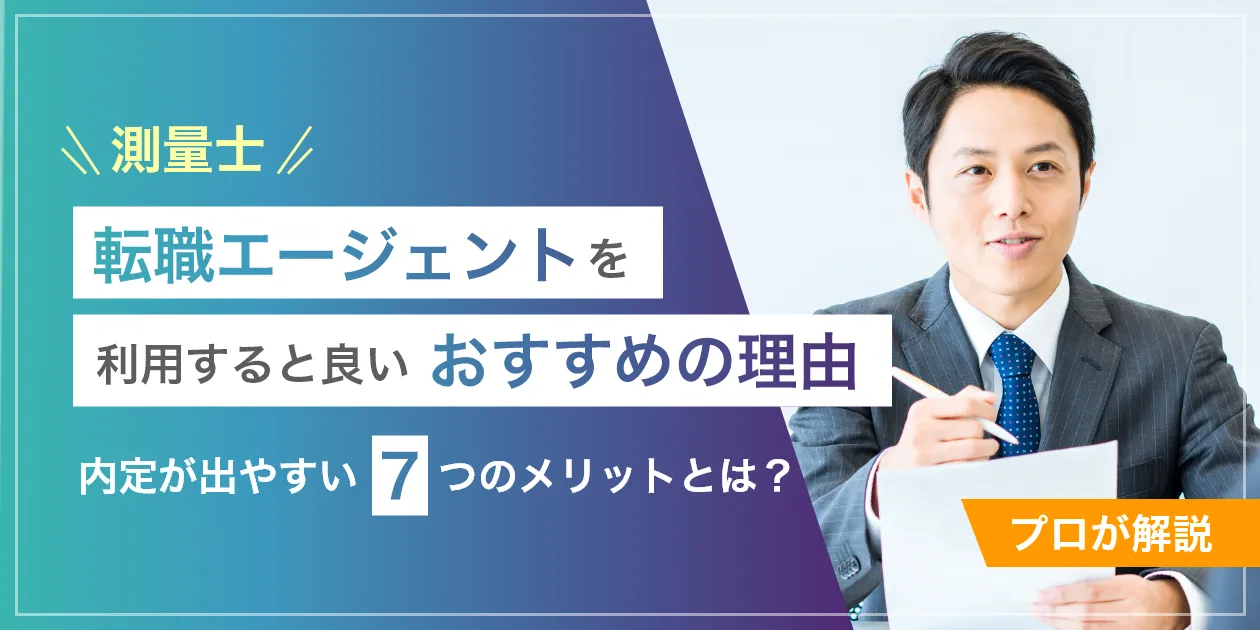
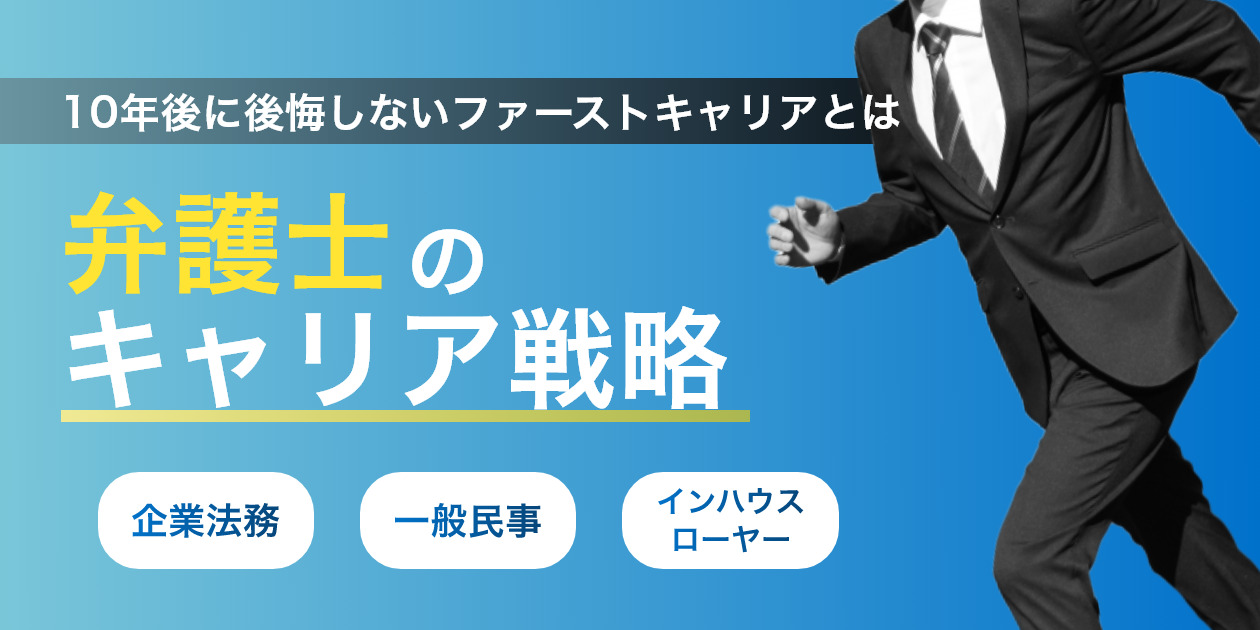
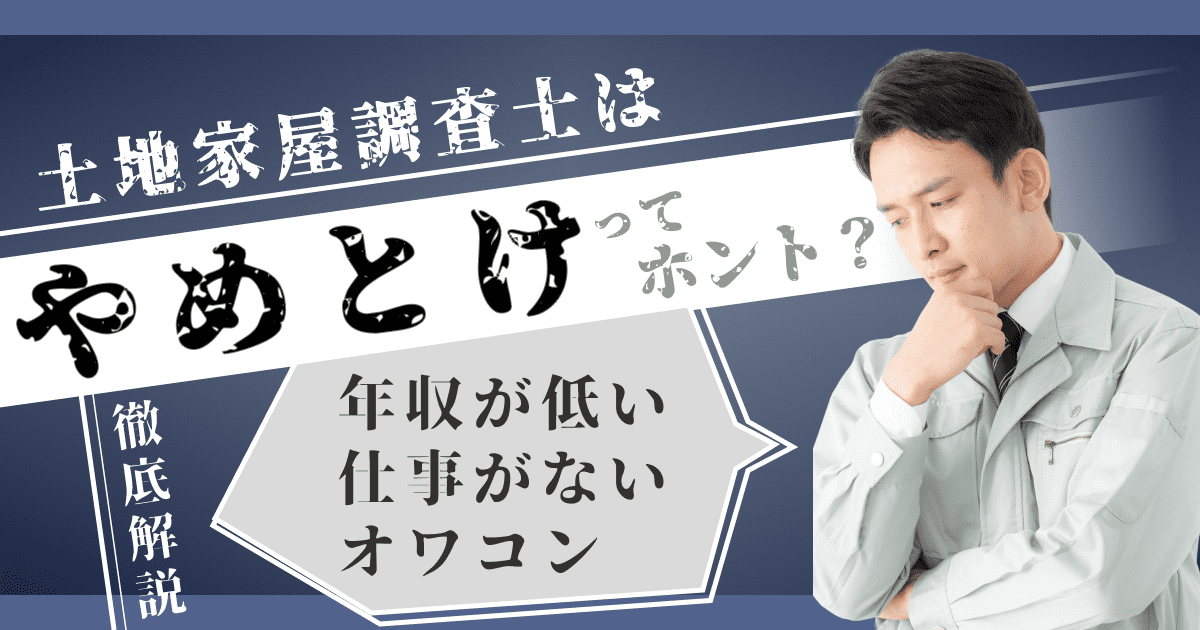
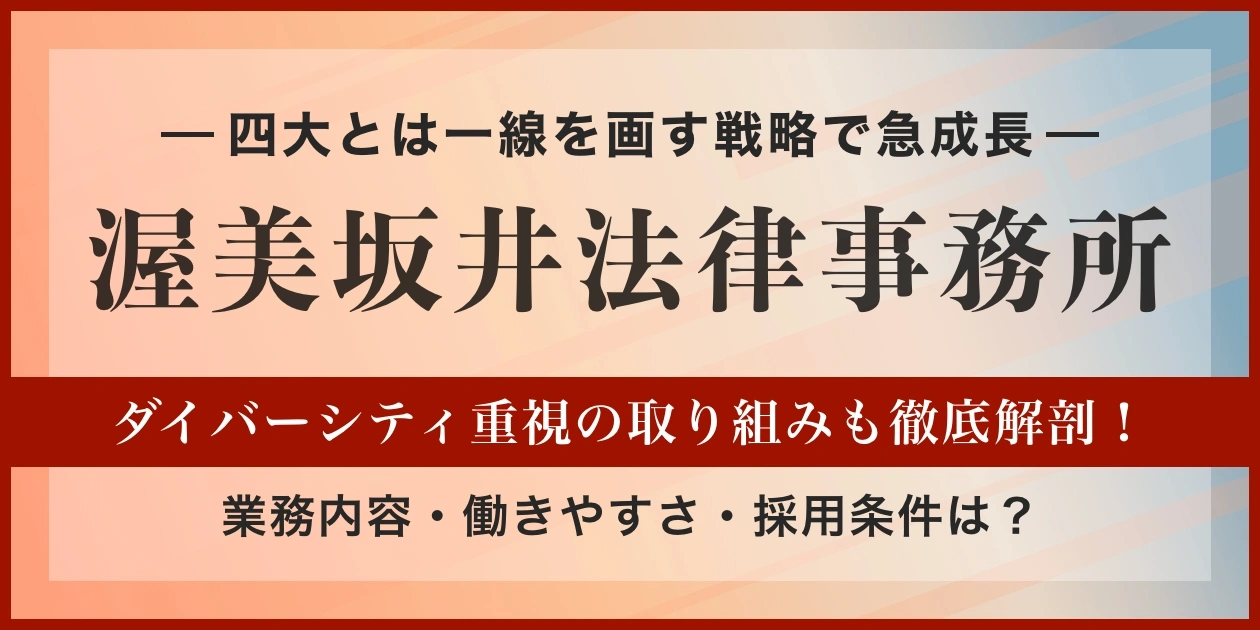
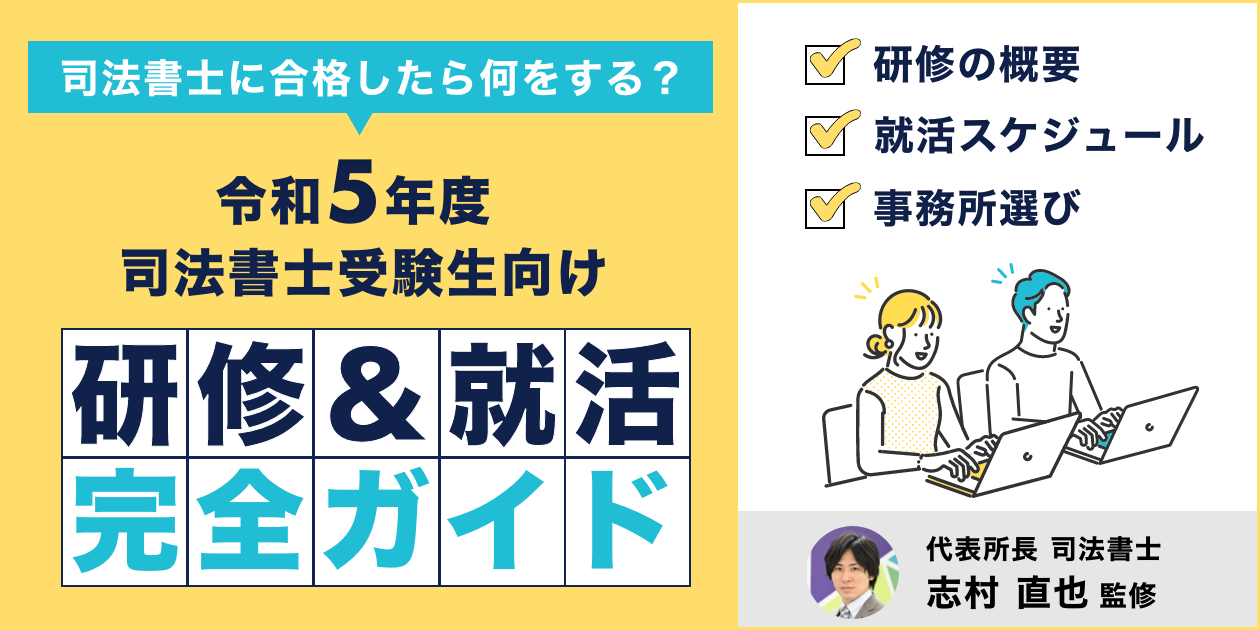
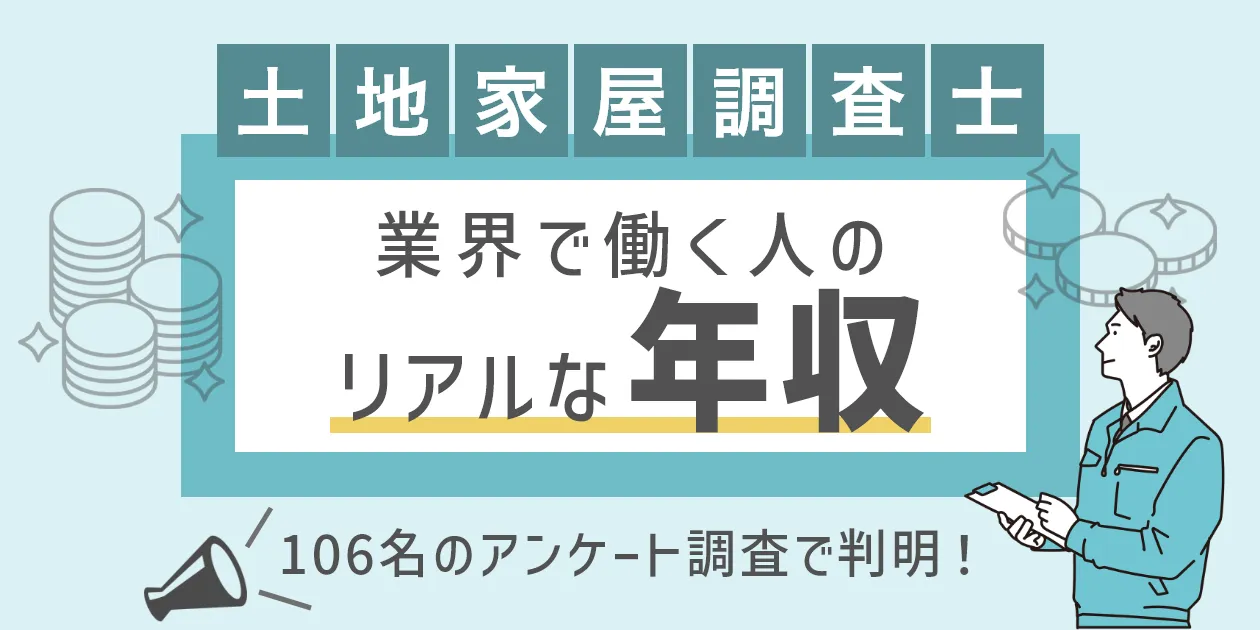
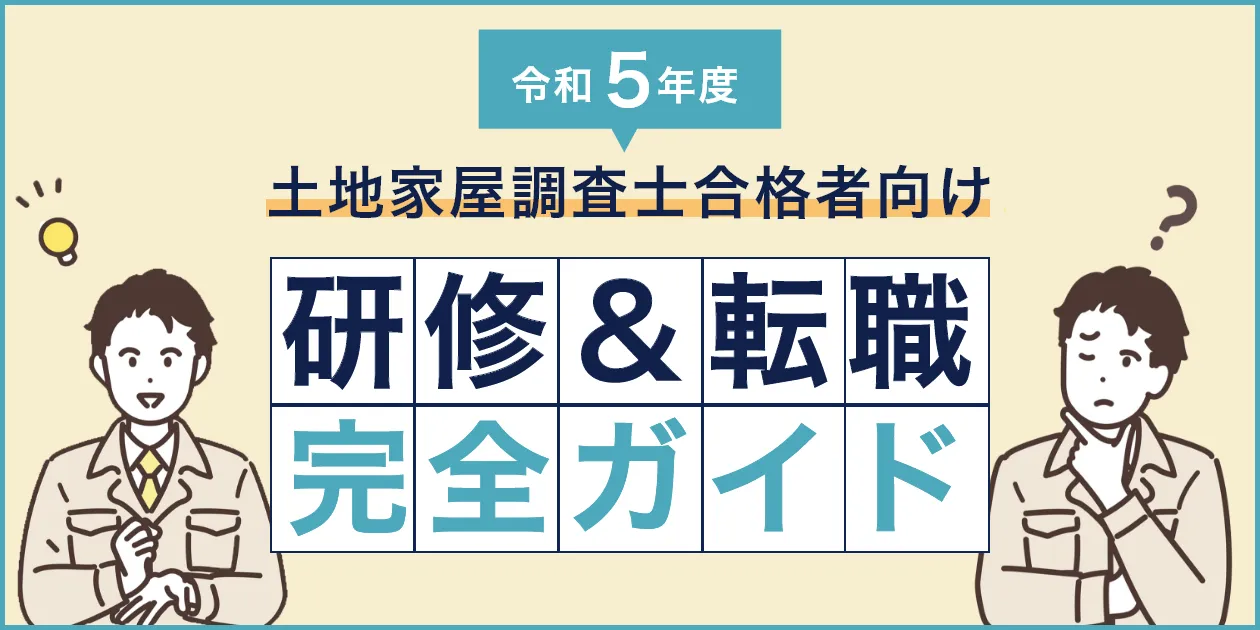

やボーナス・賞与額・昇給方法.jpeg)